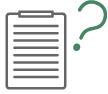遺言が不公平に感じた場合は専門家に相談
遺言書を見つけた後、いざ中身を読んでみると、遺言の内容が平等ではなかったという場合には、遺留分侵害額請求という手続きを取ることで一定程度の相続分を受け取ることができます。
この手続きは「被相続人が死亡して相続が開始したこと」及び「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知ってから1年以内に行わなければ時効によって消滅してしまいます。
少しでもご不安や違和感をお持ちの場合には、一度専門家への無料相談を活用されることをおすすめします。
遺留分侵害額請求を行ううえでのポイント
遺言書の内容の有効性

このお話をする上でご留意いただきたいのが、遺留分侵害額請求については、あくまで遺言書の内容が有効であるということが大前提であるということです。
判断能力がない状態で書いた遺言の内容だったり、無理やり書かされたのではないかという疑問があったりという場合は、遺言書自体が有効なのか無効なのかという争いになってきます。
そのため遺留分を考えるうえでは、遺言書自体は有効である必要があります。
そして、冒頭の話に戻るのですが、仮に遺言書の内容に納得がいかなかったとしても、遺言書が有効な場合は、その内容に納得がいくかどうかというのは法的に考慮されません。
不平等な内容だったとしても、遺言書を書いたその人の意思が尊重されますし、それが法律です。
ですが、あまりにも不公平な内容だと、それはそれで可哀そうだよねということで、そこの救済措置として、法律が遺言書のある場合でも最低限奪われない相続分を定めており、この最低限の相続分のことを遺留分と呼びます。
遺留分として認められるのは、法定相続分の2分の1となります。
この相続分については、たとえ遺言書がどんな内容だったとしても堂々と請求してよいものになりますので、きちんと請求していきましょう。
遺留分請求を行うための財産等の情報収集

遺留分を請求するにあたって、一番大変になってくるのが財産状況の調査です。
例えば、長男・長女が相続人だったものの、残された遺言書には全て長男に相続させるという内容だったパターンで見てみましょう。
この場合ですと、長男が全ての財産を相続するという前提で相続手続を進めていることが多いので、遺言書の原本を含めて、財産の情報や実際の相続手続まで、全て長男が握っており、他方の長女が情報を一切もらえていないということが起こり得ます。
ここが、本人で解決するのが一番難しい部分になってきており、長女としては情報を持っていないので長男に情報を教えるように伝えても、長男が全く取り合ってくれなければ、遺留分を請求する段取りが組めません。
時効を踏まえた計画的な対応
冒頭でもお伝えをした通り、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「被相続人が死亡して相続が開始したこと」及び「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知ってから1年以内に行わなければ時効によって消滅してしまいます。
なお、相続が開始したことを知らなかったり、贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すれば、事情の如何を問わず、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

期間内に権利行使したことを証明するためにも、ぜひ配達証明付内容証明郵便によって相手方(受遺者、受贈者)に通知をすることをお勧めします。なお、実際に遺留分としていくらが請求できるかという算定をするとなると、なかなか骨の折れる話になり、この金額がはっきりしないと上記の内容証明を送ることが出来ないと思ってらっしゃる方が結構多いものです。しかし、金額がはっきりしなくても、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示さえ1年以内に行えば、請求権は維持することができます。時効等を考慮しながら計画的に対応をしていくことが重要です。
Nexill&Partnersでは、遺留分侵害額請求を行ううえでの、財産状況の調査から請求に向けた手続きまで、ワンストップで対応いたします。
Nexill&Partnersの遺留分侵害額請求サポートの特徴
相続財産の調査から関与
遺留分を請求するうえでは、まずは相続財産をはっきりさせるところが大事になります。当事務所では財産状況等の情報がない場合、相続財産の調査からご依頼いただき対応しております。専門家にご依頼いただくことでスムーズに財産状況が把握できることはもちろんのこと、財産調査の結果をご共有したうえで、遺留分についての請求を行うかどうかについてもアドバイスさせていただきます。
相続案件に関する豊富な対応実績
実際に請求を行うことになったとしても、相手のとの話し合いでスムーズに回収できるかどうかは状況によって様々です。協議で解決しない場合は、訴訟や強制執行等の手続きも検討する必要が出てきます。弁護士にご相談をいただくことで、協議・調停・訴訟等の対応はもちろんのこと、過去の対応事例を踏まえたうえで、遺留分の請求・回収に向けた最適な対応策をご提案いたします。
遺留分回収後の相続税申告等の手続きも対応
遺留分の回収を行って相続した財産が基礎控除を超える場合、相続税申告を行う必要があります。また相続税申告の申告期限は原則として延長はできないため、相続が開始した翌日から10ヵ月以内が期限です。当事務所では弁護士法人のみではなく、税理士法人、司法書士法人の5士業法人を持つワンストップ事務所ですので、回収後の相続税申告についても対応が可能です。
遺留分侵害額請求に関する弁護士費用
当事務所に遺留分侵害額請求をご依頼いただく場合の弁護士費用は以下の通りです。
また、状況・条件によっては「着手金無料プラン」の適用も可能です。詳細な金額について、無料相談にてご案内をさせていただきます。
※寄与分、特別受益について主張がある場合は、上記着手金を165,000円加算させていただきます。
※不当利得返還請求を行う場合は、一般民事の基準に従い追加費用が発生いたします。
※依頼者が複数名の場合は、上記着手金を1名追加ごとに50%加算させていただき、報酬金はそれぞれ算定させていただきます。
遺留分侵害額請求の協議
相手との話し合いを行って、遺留分の請求を行います。相手の合意を得られた場合、
| 着手金 | 440,000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 440,000円+取得する相続分の11% |
遺留分侵害額請求の調停代理
| 着手金 | 550,000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 550,000円+取得する相続分の13.2% |
遺留分侵害額請求の訴訟代理
| 着手金 | 660,000円 |
|---|---|
| 報酬金 | 660,000円+取得する相続分の15.4% |
遺留分侵害額請求に関するご相談はNexill&Partnersへ
遺言の内容について問題がある場合でも、遺留分は法律上認められている権利です。しかし、時効が過ぎてしまえば権利は消失してしまうため、請求が可能かどうかの判断が難しい場合についても、まずは専門家にご相談をされることをおすすめいたします。Nexill&Partnersでは初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、「相続LOUNGE福岡オフィス」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。