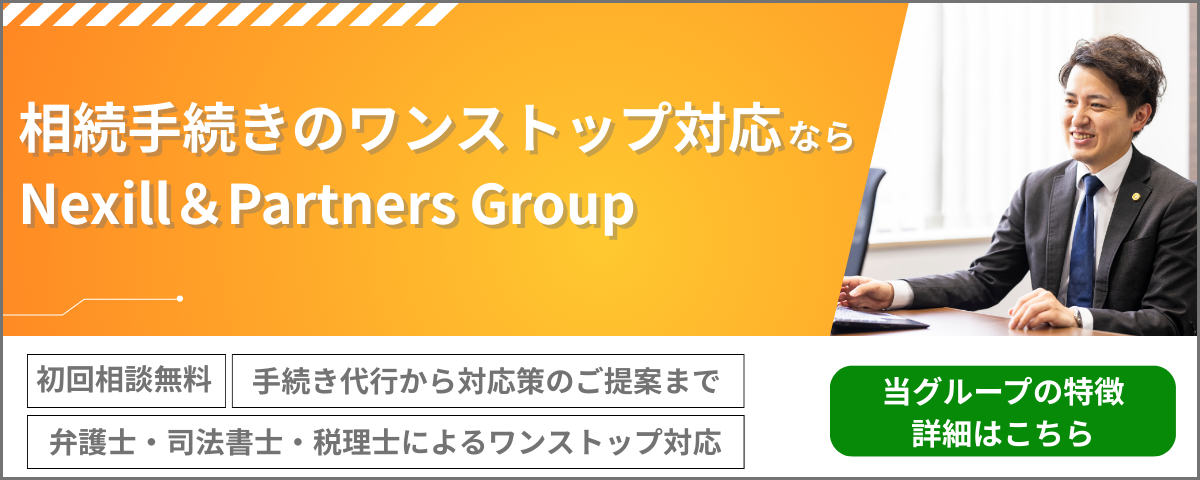相続が発生すると、まず検討すべきなのが「どんな財産を、どれだけ受け継ぐのか」という点です。
預貯金や不動産のように目に見えやすい資産だけでなく、故人が知らないうちに負債を抱えていたり、遠方に使われていない不動産があったりする場合もあるため、相続財産を正しく把握するのは意外に難しい作業といえます。
本記事では、財産調査の重要性や具体的な進め方、財産の種類別のポイントを詳しく解説します。
専門家に依頼する際の費用感も紹介しますので、相続手続きを円滑に進めたい方はぜひご覧ください。
1.なぜ財産調査が重要なのか
相続財産は、相続人間の遺産分割協議や相続税申告の算定根拠となります。
もし調査が不十分で、あとから追加で財産や負債が判明した場合、遺産分割協議をやり直したり、相続税の修正申告が必要になったりします。
1-1.遺産分割や相続税申告では正確な財産把握が必須
相続税は、被相続人(亡くなられた方)の財産を総額で評価したうえで計算します。
申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)があるため、期限内にすべての財産を把握できなければ、申告漏れや延滞税といったペナルティを負う可能性が高まります。
また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですが、協議後に新たな口座や不動産が見つかると、新たに出てきた相続財産をどう分けるかを再度話し合わなければなりません。
何度も遺産分割協議を実施するのは時間のロスですし、相続人同士の関係性があまり友好でない場合は関係性の悪化を引き起こしかねませんので、最初の段階で正確に調査しておくことが重要です。
1-2.負動産や負債の発見リスクとトラブル回避
相続財産はプラスのものばかりとは限りません。
いわゆる「負動産」(利用価値が低く、維持費や管理コストばかりかかる不動産)や借金、連帯保証といったマイナスの財産も相続対象になります。
これらを放置して相続すると、想定外の出費が発生する可能性があり、最悪のケースでは相続人が多額の借金を背負う事態に陥ることもあります。
調査をしっかり行い、必要に応じて相続放棄や限定承認を検討できるようにしておくことがリスクヘッジの第一歩です。
2.財産調査のやり方:全体的な流れ
2-1.戸籍・登記・預金口座情報などの基本的確認
1.被相続人の戸籍謄本・住民票の除票の取得
- 目的:相続人の確定や、被相続人の生前の住所遍歴を知るため。
- 具体的な手順:
1. 市区町村役場で戸籍謄本や除票を請求する。
2. 被相続人が複数回住所を変更している場合は、必要に応じて戸籍の附票を取得し住所の異動履歴を確認する。 - 実務のポイント:
▪ 住所地の最寄りの支店で▪金融機関の口座を開設している場合が多いので、支店単位での取引照会をかける際のヒントとして使用する。
▪ 住所が変わるたびに本籍地も移転している場合は戸籍の附票でもすべての住所履歴が出ないため、本籍地ごとに戸籍の附票が必要になる。
2.故人宛ての郵便物や通帳・カード明細の整理
- 目的:被相続人が利用していた金融機関・クレジット会社・保険会社などを特定するため。
- 具体的な手順:
1. 本人宛の過去数か月~1年分の郵便物を確認し、取引明細、クレジット明細などが届いていないかを確認する。 - 実務のポイント:
▪ 最近使われていない口座でも、残高があるかもしれない。少額でも相続手続きの対象となる。
▪ ネット銀行やネット証券の場合は「紙の通知」が少ないため、パソコンやスマホのアプリ・メール履歴もチェックする。
3.納税通知書や固定資産税の領収書の有無を確認
- 目的:不動産の所在や種類を把握するため。
- 具体的な手順:
1. 毎年送られてくる固定資産税通知書や、領収書の宛名・物件情報を確認する。
2. 過去の保管資料があれば「所有している不動産の一覧」をざっくりと作る。 - 実務のポイント:
▪ 相続人の現住所以外の不動産の場合は見落としがちなので注意が必要(投資用不動産、空き家など)
2-2.法務局・金融機関・証券会社への照会
1.法務局で不動産登記情報を取得
- 目的:所有者・地番・家屋番号・抵当権設定の有無などを把握するため。
- 具体的な手順:
1. 固定資産税通知書や地番をもとに、法務局で登記事項証明書を請求する。 - 実務のポイント:
▪ 相続登記の申請を見据えて、相続人全員の印鑑証明書や戸籍類の準備時期も検討しておく。
▪ 高齢の被相続人が「先々代からの不動産を相続したまま名義変更していない」ケースもあるため、確認漏れに注意。
2.銀行・金融機関への問い合わせ
- 目的:口座の有無や残高、取引履歴を確認し、預貯金を洗い出すため。
- 具体的な手順:
1. 故人の口座があるとわかっている銀行支店や本店に連絡し、相続手続きの窓口を確認する。
2. 必要書類(被相続人の死亡診断書の写し、相続人の戸籍、依頼書など)をそろえて手続きを進める。 - 実務のポイント:
▪ 口座名義人の死亡を知らせると、その口座は凍結される。引き落としや支払いに支障が出ないよう、引き落とし先がある場合は先に確認を。
▪ どこの金融機関に口座があるか分からない場合は、めぼしいところに手あたり次第照会をかけるしかない。
▪ 支店単位での照会が必要な金融機関もあるので、その場合は被相続人の住所地を手掛かりに住んでいた場所の最寄りの支店に照会をかけるなどで調査を進める。
3.証券会社・投資信託会社への問い合わせ
- 目的:株式・投資信託・債券などの有価証券の保有有無を確かめるため。
- 具体的な手順:
1. 郵送物や取引明細に記載された証券会社名・口座番号をもとに問い合わせる。
2. ネット証券の場合はログイン情報や電子交付書類(メール)を確認し、残高証明を取得する。 - 実務のポイント:
▪ 証券会社によっては、相続専用の書類請求フォームや問い合わせ窓口があるため、公式サイトを確認するとスムーズ。
▪ 一時期だけ投資をしていた可能性もあるため、念のため数年前の取引履歴も見てもらうと安心。
2-3. その他の確認・調査
1.保険金や年金の確認
生命保険は契約者・被保険者・受取人を整理し、保険会社に連絡して保険金請求の手続きを確認しましょう。
年金や死亡退職金は、故人が勤めていた企業や共済組合、年金事務所などへ問い合わせます。
大企業や公務員として長く勤務していた方の場合、企業年金があるケースも珍しくありません。
2.負債や連帯保証などの負の財産調査
クレジットカード会社や消費者金融からの郵便物や明細書があれば、早めに問い合わせをして残高を確認します。
被相続人が誰かの保証人になっていた場合、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。
負債が大きい場合は、期限内に相続放棄などの判断を行わなければなりません。
3.動産(貴金属・骨董品など)の調査
貴金属や骨董品は銀行の貸金庫に保管されていることもあり、一般の方では価値や真贋を判断しづらい場合があります。
専門の鑑定士やオークション会社に依頼して評価額を見積もると、適切な相続税申告がしやすくなります。
3.財産の種類別にみる具体的調査方法(その他の発生しうる財産)
3-1.事業用資産(自営業・法人オーナーの株式・出資金など)
自営で事業を営んでいたり、会社の経営者・役員として未上場株式を保有していたりする場合、事業用資産や株式・出資持分が相続財産に含まれます。
1.具体的な財産例
- 個人事業の設備・在庫・原材料:店舗備品、機械、在庫商品、原材料など。
- 法人オーナーの未上場株式や出資金:株式会社の株式、合同会社の持分、医療法人や社会福祉法人の出資持分など。
- 売掛金や受取手形:得意先が存在する場合、未回収の売上代金が相続の対象となる。
2.調査のポイント
- 決算書類・帳簿類の確認
▪ 個人事業であれば「青色申告決算書」「総勘定元帳」「在庫台帳」など。
▪ 法人の場合は「直近期の決算書」「株主名簿」「法人税申告書」などをチェック。 - 取引先・債権債務の洗い出し
▪ 売掛金や買掛金、借入金の存在を忘れずに確認する。 - 未上場株式の評価
▪ 相続税申告で株価算定が必要。税理士に早めに依頼することで、適切な評価方式を用いた計算が可能になる。
3.実務上の注意点
- 相続税の納税猶予制度(事業承継税制)を活用できるケースがあるため、経営者の相続であれば検討したい。
- 法人の株式や持分が複数の相続人に分散すると、経営権が不安定になる場合もある。生前に株式の帰属を整理しておくのが理想的。
3-2.知的財産権(著作権・特許権・実用新案権・商標権など)
クリエイターや研究者、発明家などが保有する著作権や特許権、商標権といった無体財産も、相続の対象となります。
使用許諾料やロイヤリティ収入が継続的に発生するケースもあるため、見落とすと大きな損失につながりかねません。
1.具体的な財産例
- 著作権:作曲家や作家の楽曲・文章・イラストなど。著作財産権の存続期間中はロイヤリティ収入が発生。
- 特許権・実用新案権:特定の技術や発明に関してライセンス収入がある場合。
- 商標権・意匠権:ブランド名やロゴデザインなどに係る権利。
2.調査のポイント
- 権利登録情報の確認
▪ 特許庁のデータベースや管理番号で、登録状況や権利者を調べる。
▪ 著作権は公的な登録制度がない場合も多いが、出版社や音楽出版社との契約書を確認する。 - ロイヤリティの受取実績
▪ 銀行口座の入金履歴をさかのぼって、著作権使用料や特許使用料が振り込まれていないかをチェック。 - 契約内容の確認
▪ 他者に使用許諾を与えている場合、ライセンス契約の締結状況や契約期限を調べ、相続後も継続収入があるかを把握。
3.実務上の注意点
- 権利の有効期限や、死亡後にも存続期間があるか(著作権の存続期間など)を要チェック。
- 管理や行使には専門知識が必要なため、弁護士や弁理士への相談も検討する。
3-3.デジタル資産(暗号資産・NFT・電子マネー・オンラインアカウントなど)
近年増加しているのが、デジタル上の財産です。暗号資産(仮想通貨)やNFT(Non-Fungible Token)、ゲーム内通貨、オンラインサービスのポイント・電子マネーなど、多岐にわたります。
1.具体的な財産例
- 暗号資産(仮想通貨):ビットコイン、イーサリアムなど。取引所の口座やウォレットを通じて保有。
- NFT(デジタルアートなど):専用のマーケットプレイスやウォレットで管理。
- 電子マネー・オンラインポイント:Pay系アプリ残高、ECサイトのポイント、マイルなど。
- オンラインゲーム内通貨やアカウント:換金性が高いものや、実質的に資産価値がある場合。
2.調査のポイント
- 故人のスマホ・PC・メールをチェック
▪ 取引所のログイン情報やウォレットID、NFTマーケットの登録情報が手がかり。 - 定期的な明細・通知メールの存在
▪ 暗号資産取引所は本人確認(KYC)が必須のため、取引履歴や残高証明の取得も可能。 - パスワード・秘密鍵の保管状況
▪ ウォレットの秘密鍵を失念すると資産を引き出せない。故人のPCやノート、クラウドストレージなどを丹念に探す。
3.実務上の注意点
- 法整備が進行中の分野であり、税務上の取り扱いも複雑。暗号資産は相続税計算の際に時価評価される。
- ログイン情報や秘密鍵がわからない場合、事実上引き出し不可能になるリスクがあるので注意。
3-4.ゴルフ会員権・リゾート会員権・各種クラブ・サロン会員権
ゴルフ場や高級リゾート施設、スポーツクラブや会員制サロン等の会員権も相続の対象となります。売買市場が存在する場合、一定の資産価値を持つことが多いため、忘れずに調査しましょう。
1.具体的な財産例
- ゴルフ会員権:預託金制のものや株主制のものなど形態は様々。
- リゾート会員権:有名リゾート施設やホテルの会員権で、譲渡制限がある場合も。
- スポーツクラブ・会員制サロン:一時金を支払った入会権利が売買できる場合は資産価値が生じる。
2.調査のポイント
- 会員権証書や契約書、会員番号
▪ 被相続人が保管していることが多いが、不在の場合は施設に問い合わせ。 - 譲渡の可否
▪ クラブや施設によっては第三者への譲渡が認められておらず、相続人が利用権を継承する形となるケースもある。 - 時価評価
▪ 会員権の市場価格を扱う業者や、ゴルフ会員権売買会社などに査定を依頼するとよい。
3.実務上の注意点
- 名義変更手数料や年会費の支払い義務があるため、放置すると管理費がかさんだり失効したりするリスクがある。
- 会員権によっては、相続手続きに施設側の承認が必要な場合があるので注意。
3-5.車両・船舶・農機具・家畜等の特殊動産
自動車や船舶、農業機械、大型の工業機器、さらには牧場経営などで保有される家畜なども相続財産となります。
これらは登録手続きや名義変更が必要で、特別な許可が関わるケースもあります。
1.具体的な財産例
- 自動車・バイク:自動車検査証(車検証)や軽自動車届出済証などで所有者を確認。
- 船舶・小型船舶:船舶検査証書、登録事項証明書などで名義や所有者を特定。
- 農機具・大型機械:トラクターやコンバインなど。農協やリース会社との契約状況も確認。
- 家畜(牛・馬・豚・鶏など):畜産業の場合、生体そのものが財産価値を持ち、飼養頭数などの把握が必要。
2.調査のポイント
- 登録証や許可証の所在
▪ 車検証、船舶登録、家畜伝染病予防法に基づく登録など、個別に役所や運輸局等で情報を取得できる。 - 保管場所や管理状況
▪ 遠方に駐車・係留・飼育されている場合、現状を把握するために現地確認が欠かせない。 - リース契約・ローン残債
▪ リース契約中やローンが残っている場合、相続人が引き継ぐか、相続放棄を検討するか判断が必要。
3.実務上の注意点
- 公道を走行する車両は、名義変更をしないと保険や税金の問題が生じる。
- 船舶や家畜は維持費や管理責任が重く、売却・譲渡手続きも簡単ではない場合が多い。
3-6.その他の特殊な権利(漁業権・水利権・鉱業権・山林共有持分など)
地域や家業によっては、漁業権・水利権・鉱業権などの「免許制・許可制」の権利を相続することがあります。
また、山林や原野を一族で共有しているケースもあり、書類上は把握しにくいことが少なくありません。
1.具体的な財産例
- 漁業権:漁協への加入権や、漁場の使用許可など。
- 水利権:農業用水や発電用水など、取水に関する権利。
- 鉱業権:鉱物の採掘許可。地域によっては古くから権利が引き継がれている。
- 山林・原野の共有持分:過去に親族間で持分登記したまま放置されているケース。
2.調査のポイント
- 協同組合・行政機関での照会
▪ 漁協や水利組合などで権利の有無や名義を確認。
▪ 山林・原野は法務局の登記や、市町村の森林簿・林地台帳もチェック。 - 免許・許可の更新状況
▪ 鉱業権や漁業権などは定期的な更新手続きがあるため、期間満了で消滅していないか要確認。
3.実務上の注意点
- 地域コミュニティで権利が実質管理されており、名義変更の手続きが独特な場合がある。
- 山林・原野の共有持分は買い手がつきにくく、負動産化している可能性もあるため、国庫帰属や相続放棄の検討要素になりうる。
4.よくある質問Q&A
Q.財産を全く知らされていない場合、何から着手すれば?
まずは自宅にある郵便物、クレジットカード明細、銀行の通帳類を一通りチェックしましょう。
故人宛ての手紙や領収書、公共料金の引き落とし履歴などから金融機関や保険会社、クレジット会社を特定し、問い合わせを行うことが最初の一歩です。
Q.相続財産を調べる期限はあるの?
「財産調査」のための期限は法的に定められていませんが、相続税の申告期限(10か月)や相続放棄の期限(3か月)があります。
手続きをスムーズに進めるためには、相続開示後速やかに調査を始めるのが望ましいでしょう。
Q.債務調査も同時にする必要がある?
もちろんです。
マイナスの財産を見落とすと、相続税申告での債務控除に影響が出るほか、負債額によっては相続放棄を検討すべきところ相続放棄申述の期限を逃してしまう可能性があります。
プラスだけでなく、マイナスも含めて相続財産の全体像を把握することが大事です。
5.相続財産調査を専門家に頼む場合の費用はどれぐらい?
相続財産調査を専門家に依頼する場合の費用相場としては、財産調査だけをお願いするなら数万~十数万円程度が目安となります。
費用はかかってきますが、時間と労力の負担を減らしつつ、専門家の知見を活かして確実に財産調査を進めたい方にとって、専門家への依頼は大きなメリットがあるといえます。
事務所によって報酬の設定の仕方は異なりますので、実際にどれぐらいの費用がかかるかは相談の際に確認をされてください。
6. 本コラムのまとめ
相続財産の調査は、相続税の申告や遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせない重要ステップです。
預貯金や不動産だけでなく、保険金や負債、動産など、多岐にわたる財産を一つひとつ確認する必要があり、個人で進めるには大きな負担がかかります。
ご自身での財産調査の時間が取れない方、手続に不安がある方は、専門家へ依頼されることでスムーズに手続きが進められるでしょう。
財産調査から遺産分割協議、税申告、名義変更までは一連の流れで行うのが理想的です。
途中で専門家を切り替えるより、最初からすべて任せられる体制が整えられるとベターです。
当事務所では、税理士・司法書士も在籍するワンストップ体制で、財産調査から相続手続、そして紛争解決までを一貫してサポートいたします。
まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
専門家を味方につければ、複雑な相続手続きもスムーズに進められます。
ぜひお気軽にご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。
こちらもぜひご活用ください。