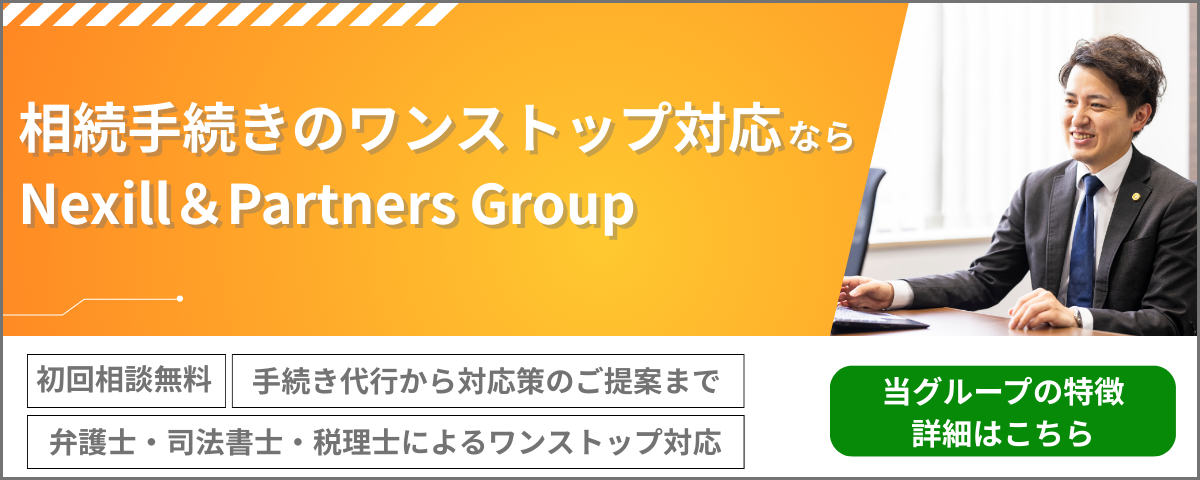相続が始まると、「プラスの財産だけでなく借金も引き継いでしまうのでは」と不安になる方は多いでしょう。相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法がありますが、なかでも相続放棄を検討している方が注意しなければならないのが「熟慮期間」です。通常は3カ月とされるこの期間内に判断・手続きを完了できない場合もあり、そんなときは熟慮期間の“伸長(延長)”ができるケースもあります。本記事では、熟慮期間の基本的なルールや、家庭裁判所での手続き、実務上の注意点などをわかりやすくまとめました。相続放棄を検討しているが、「期限に間に合わないかもしれない」「なかなか意思決定ができない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.熟慮期間とは何か?その基本と相続放棄の概要
1-1.「熟慮期間」とは?法律上の定義と趣旨
相続が開始されたとき、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶ必要があります。民法上、どの方法を取るかを選択するために与えられる期間が「熟慮期間」です。原則として被相続人が亡くなった事実を知り、自身が相続人であることを知った日から3カ月以内がこの期限になります。 熟慮期間の趣旨は、相続人に「財産の調査を行い、相続するかどうかを冷静に判断する時間」を確保することです。
1-2.相続放棄・限定承認・単純承認の3つの選択肢
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も全て引き継ぐ方法。特に手続きをしなくても、熟慮期間を過ぎれば単純承認したものとみなされます。
限定承認
相続によって得た財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法。財産と債務を差し引きしてプラスであれば相続人の利益となりますが、手続きが複雑で、全相続人が共同で行わなければならない点に注意が必要です。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄によって負担を回避できますが、熟慮期間内に手続きが必要になります。
1-3.熟慮期間が問題になるケースとは?
相続人が「借金があるかわからない」「遠方に不動産があるかもしれない」など、相続財産の内容を短期間で把握しづらい場合や、急に入院をすることになってしまったなどで、相続手続を行うことが難しいようなケースもあります。
3カ月という期間は長いようで意外と短いため、上記のような事情があるときは、熟慮期間の伸長を検討するという選択肢を頭に置いておく必要があります。
2.熟慮期間の起算点と計算ルール
2-1.被相続人の死亡と「自己のために相続の開始があったことを知った時」
熟慮期間の起算点は、単に被相続人が亡くなった日から一律3カ月というわけではありません。法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされており、例えば被相続人が死亡してからしばらく経って初めて死亡事実を知った場合、起算点はその時点から数えます。遺産の存在を知らずに後から見つかったケースなどでは、熟慮期間の起算が後ろにずれる可能性があります。
2-2.複数の相続人がいる場合の注意点
相続人が複数いると、それぞれの熟慮期間の起算点が異なることがあります。たとえば、相続人Aは相続開始をすぐに知ったが、相続人Bは後から知った場合には、AとBで熟慮期間の開始時期がずれます。財産調査を共同で進める場合でも、熟慮期間は相続人ごとに計算される点は注意が必要です。
2-3.熟慮期間が過ぎるとどうなる?単純承認のリスク
熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きを行わないまま放置してしまうと、自動的に「単純承認」とみなされます。借金などの負債も引き継ぐことになり、後から放棄することは基本的にできなくなるため、特に気を付けておきましょう。
3.熟慮期間は延長できる?伸長手続きのポイント
3-1.家庭裁判所に申立てが認められる要件
熟慮期間は絶対的な3カ月ではなく、正当な理由があれば家庭裁判所で「伸長(延長)申立て」をすることが可能です。例えば、相続財産の調査が思うように進まない・遠方の不動産の実態確認に時間がかかるなど、合理的な理由があれば申立てが認められることがあります。ただし、裁判所が「その事情なら期限延長もやむを得ない」と判断するだけの客観的な根拠が必要です。
3-2.実際の手続きの流れ:必要書類・費用・審判のイメージ
熟慮期間の伸長を求めるには、書面(申立書)を家庭裁判所に提出します。あわせて以下のような書類が求められるケースが一般的です。
- 被相続人の戸籍や住民票の除票
- 申立人(相続人)の戸籍や住民票
- 相続財産を特定するための書類(登記事項証明書、残高証明など)
- 収入印紙・郵便切手代等の費用
裁判所が申立内容を審理し、「延長を認める」審判が下りれば、一定期間熟慮期間が伸びます。具体的な延長幅は状況によって異なるため、事前に弁護士などへ相談しておくと安心です。
3-3.新型コロナウイルスなど特別な事情がある場合
近年では新型コロナウイルスの影響で自由に移動できず、財産調査や書類収集が間に合わない事例も見受けられます。こうした事情を裁判所が考慮してくれる場合もあるため、早めに現状を説明し、伸長申立てを検討することが大切です。
4.熟慮期間を延長しやすい具体的な事例
4-1.相続財産の調査が終わらず3カ月で判断できない場合
相続税申告や遺産分割を考えるうえでも、遺産の全容を把握するのは不可欠です。被相続人が複数の銀行口座や証券口座を持っていたり、遠方に不動産があったりする場合は、3カ月で全ての情報を集めきれないことがあります。こうした状況を家庭裁判所へ具体的に示せば、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。
4-2.相続人の行方不明・債権者対応に時間がかかるケース
相続人の一人が行方不明だったり、多数の債権者がいて対応に時間を要したりする場合も、3カ月での判断が難しくなります。相続人同士の話し合いや調停が必要になるケースでは、熟慮期間内に結論が出ないことも珍しくありません。
4-3.その他、やむを得ない事情がある場合の考慮要素
大病で入院中の相続人がいたり、裁判所からの書類を受け取れない事情があったりするなど、やむを得ない理由があるときにも伸長の申し立てが検討されます。裁判所が「合理的な理由あり」と認めれば、熟慮期間を延ばせる可能性があります。
5.相続放棄の手続きとは?熟慮期間内であれば取り下げはできる?
5-1.相続放棄を申述する手順と必要書類
相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所への「相続放棄申述書」の提出が必須です。被相続人の戸籍謄本や財産を特定するための書類を添付し、申述が受理されると相続放棄が確定します。熟慮期間内に手続きを完了する必要があるため、財産調査や他の相続人との情報共有をできるだけ早めに進めましょう。
5-2.相続放棄の取り下げ(撤回)はできるのか?
一度相続放棄をすると、原則として撤回は認められません。熟慮期間内だからといって、「やっぱりやめたい」と取り下げが自由にできるわけではないので、慎重な判断が求められます。財産調査の途中で方針が変わるかもしれない場合は、まずは熟慮期間の延長を検討するのが適切です。
なお、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったという扱いになるため、その後の遺産分割協議には参加できなくなります。
6.専門家に頼むメリットと費用相場
熟慮期間が迫っている場合、迅速かつ正確な財産調査や手続きが求められますが、「あと数週間で3カ月が経過してしまうが、遺産内容がまったく分からない」という状況で、個人だけで必要な手続きを終えるのは簡単ではありません。
こういった場合でも、相続案件の経験値がある専門家であれば、対応方法を熟知しているため、裁判所への伸長申立てを含めてスピード感をもって動くことができますので安心して手続きを進められるでしょう。
相続放棄を専門家に依頼する場合の費用相場は、数万円から十数万円程度が目安といわれています。こちらも事務所によって報酬規程が異なりますので、相談に行かれる際に費用とサポート内容を確認されるようにしてください。
本コラムのまとめ
相続放棄を考えるうえで重要な「熟慮期間」は、原則3カ月と定められています。
正当な事情がある場合には家庭裁判所へ伸長(延長)を申し立てることができ、実際に延長が認められた事例もありますが、裁判所が納得できるだけの合理的な理由付けが必要となります。熟慮期間を超えてしまうと原則として単純承認となり、負債も含めた相続を避けられなくなるリスクがあるため、やはり期日内での対応が非常に大切となります。 もし「財産の全容が分からない」「判断に迷っている」「相続人が多く調整に時間がかかる」などの事情がある場合は、早急に専門家に相談のうえでアドバイスを受けることをお勧めします。
当事務所では、弁護士・税理士・司法書士が在籍のうえで、ワンストップでスムーズに相続問題をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、初回無料相談で現状をお聞かせください。時間的な余裕を確保し、納得のいく相続手続きを進めるためにも、早めの行動が不可欠です。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。