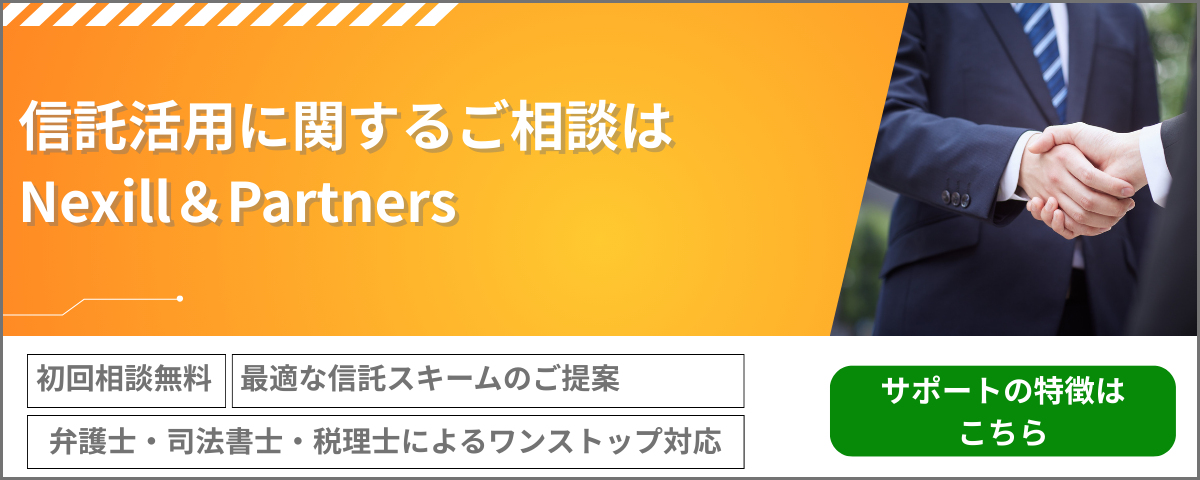家族信託を検討するとき、真っ先に浮かぶ疑問のひとつが「信託契約書は公正証書にしたほうがいいのか、それとも私文書で十分なのか」ということではないでしょうか。
家族信託は財産管理や相続対策の手段として注目度が高まっていますが、その契約書の作り方を誤ると将来のトラブルにつながる恐れがあります。
本記事では、公正証書で信託契約書を作成する際の注意点、そして契約書を作成する際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
家族信託に興味をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧いただき、疑問を解消していただければ幸いです。
1. 家族信託とは何か?基本的な仕組みのおさらい
1-1. 家族信託の目的と主なメリット
家族信託とは、「財産を持つ親(委託者)」が、その管理・運用を「信頼できる家族(受託者)」に任せ、運用益や最終的な財産の帰属先を「受益者」に定める仕組みです。高齢化社会で注目される理由は、次のような利点を持つからです。
財産の管理が安定
認知症や要介護状態になる前から、家族が正式に管理権を持つため、銀行口座や不動産の運用がスムーズに続けられる。
生前対策と相続トラブルの回避
遺言では死後の財産分配を定めることが主目的ですが、家族信託は生前から財産管理を委託できるため、将来の紛争リスクを下げやすい。
1-2. 任意後見制度や遺言との違い
家族信託は、判断能力が保たれているうちに契約を結び、財産の管理・処分権を受託者に移転できる点が特徴です。
一方、任意後見は本人の判断能力が低下してから発効する仕組みであり、財産管理の柔軟さが異なります。
また、遺言はあくまで死後の分配を決めるものですが、家族信託では生前から契約を発効させて資産を効率的に運用することが可能です。
2. 家族信託契約書は公正証書で作成するべき?
2-1. 私文書(自分で作成)との比較
家族信託契約書を私文書で作る場合、自分で内容を決められる自由度は高いものの、書式不備や契約内容の不明確さが原因で後々トラブルになるリスクが上がります。
公正証書を選ぶと、公証人が方式面をチェックしてくれるため、無効・不備が起こりにくく安心度が高いという利点があります。
2-2. 公正証書にするメリットとデメリット
メリット
- 公証人が法律に即した書式を確保する
- 原本が公証人役場に保管され、紛失や改ざんリスクを大幅に減らせる
- 裁判などで契約書の有効性を争われにくい
デメリット
- 作成手数料がかかる
- 公証人役場へ出向く手間や証人の確保が必要
3. 公正証書の作成手順とポイント
3-1. 公証人役場での流れ
- 内容の事前相談:家族信託の契約目的や財産の範囲を弁護士や税理士と詰める
- 公証人と打ち合わせ:必要書類(登記簿謄本・固定資産評価証明書など)を用意し、契約書案を公証人に渡す
- 証人2名以上の準備:公正証書には証人が必要。親族ではなく第三者を手配するケースもある
- 署名押印と手数料支払い:正証書が完成し、原本は公証人が保管。契約者は正本・謄本を受け取る
3-2. 事前に準備しておく書類
- 委託者・受託者・受益者の身分証明書
- 財産に関する資料(不動産、預貯金、株式など)
- 相続対策を考慮する場合は家族構成図や財産目録
3-3. 費用・証人確保の実務的注意点
公証人手数料は財産額や契約内容に応じて変わり、大きな資産を信託する場合は費用が高額になることも。
証人には法律で「利害関係のある人はなれない」などの制限があり、準備に時間がかかる可能性もあります。
4. 公正証書化を検討する際に迷う人への判断基準
4-1. 財産規模とリスクの度合い
不動産や大きな金融資産を含む信託であれば、公正証書化する意義は高いです。
後から「信託契約が無効だ」と争われて手間とコストがかかるリスクを下げるには、専門家のレビューを経て公正証書にしておくのが確実といえるでしょう。
4-2. 親族間の関係性と専門性のニーズ
親族全員が納得している場合でも、将来的に相続人が変わる恐れや、状況が変動する恐れがあります。
公正証書化すれば、公証人の認証という客観的な裏付けがあるため、後から別の親族が疑義を呈しても契約書の正当性を守りやすくなります。
4-3. 紛争予防と費用対効果
公正証書にはコストがかかる一方、紛争を回避できれば将来生じる可能性のある調停・訴訟費用や精神的負担を考えると、費用対効果の面で有利になるケースが多いです。
「少し面倒でも公正証書にしておいたほうが、結果的に家族のためになる」という意識で検討するとよいでしょう。
5. 家族信託契約書を作成する際のチェックリスト
5-1. 受託者や受益者の正確な特定
家族信託契約で重要なのは、委託者・受託者・受益者の情報を間違いなく記載することです。
名前の漢字、住所、続柄などを戸籍や住民票で確認しておきましょう。
5-2. 信託財産の範囲・評価
どの財産を信託に入れるかを明確にし、対象が不動産の場合は登記簿謄本、預貯金の場合は口座情報などを整理します。
財産評価や分割内容が曖昧なままだと、将来の管理・処分に支障が出るため注意が必要です。
5-3. 信託目的と終了事由の明記
「財産管理」「介護費用の捻出」「相続税対策」など、信託を行う目的を契約書にしっかり書いておくことで、家族や関係者が理解しやすくなります。
信託をいつ・どういう条件で終了させるかについても明確化しましょう。
6. よくある質問Q&A
Q. 公証人役場で家族信託を作成する費用はどれくらい?
公証人手数料は財産評価額などによって変動します。
数万円から数十万円の範囲が一般的ですが、高額財産の場合はさらに上積みされることもあります。
具体的には公証人と相談して見積もりを取るのがおすすめです。
Q. 親族を受託者に指定するときの注意は?
信託契約では受託者に大きな権限が渡るため、不正リスクが懸念されるケースもあります。
公正証書にし、契約内容を第三者が確認することで、将来的なトラブルを防ぎやすくなります。
Q. 契約後に不動産を追加して信託したくなった場合は?
新たな不動産を信託に組み入れたい場合、追加の契約書(変更契約)を作成する必要があります。
公正証書で作成した契約を修正するなら、変更部分だけを公正証書にする方法も検討できます。
Q. 家族信託と遺言は併用したほうがいい?
家族信託は生前の財産管理に強みがありますが、死後の分配を最終的にどうするかは遺言書で定めるのが確実です。
相続税や相続人の構成を考慮して、家族信託と遺言を併用するケースも多いです。
Q. 認知症が進んでいる親には家族信託は使えない?
家族信託を結ぶには「契約を結べるだけの判断能力」が必要です。
認知症が進んでしまった場合は、法定後見制度を検討するほうが現実的です。
認知症リスクが出る前に動くのがベストといえます。
7. まとめ:公正証書での信託契約書作成は安心への近道
家族信託は、財産管理や相続対策の有効な手段ですが、契約書の作成方法ひとつで将来のトラブルリスクが大きく左右されます。
とくに高額資産や不動産を含む場合、「契約書は公正証書にする」という選択肢が安全性や安心感で勝ることが多いでしょう。
当事務所は弁護士・税理士・司法書士が在籍するワンストップ体制で、家族信託の契約書案作成から公正証書作成、さらに信託不動産の登記や将来の遺産分割協議への対応まで、相続に関して総合的にサポートいたします。
「信託契約書を公正証書にすべきかどうか分からない」「信託契約書の内容に不安がある」という方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。