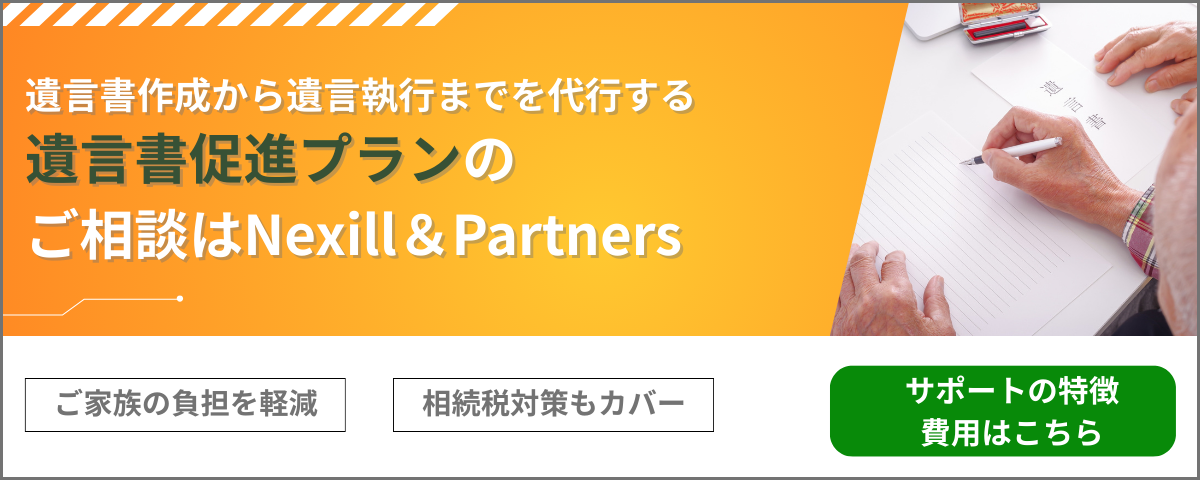銀行や信託銀行が提供する遺言信託サービスでは、公正証書遺言の作成支援から保管、死亡後の遺言執行までを一括して任せられる仕組みが整えられており、特にご高齢の方や一人暮らしの方にとっては心強い選択肢に見えることでしょう。
金融機関が提供する遺言信託は“サービス商品”であり、法的な設計や紛争予防まで対応できないケースもあり、ご自身の希望や家庭の事情とミスマッチを起こすリスクもあります。
本記事では、遺言信託がマッチする場合とそうでない場合という点を含めて、遺言信託のデメリットと弁護士に相談した場合との違い、自分に合った制度の選び方を詳しく解説します。
1. 「遺言信託」とは?よくある誤解と正しい意味
1-1.金融機関が言う「遺言信託」はどういうサービスか
銀行や信託銀行が提供している「遺言信託」といわれるものは、遺言書の作成支援・保管・遺言執行までを一括して行う、いわば遺言関連業務のアウトソーシング商品です。
詳細なサービス内容は金融機関によって異なりますが、基本的には以下のような業務の流れになっています。
金融機関での遺言信託の流れ
- 生前:銀行で公正証書遺言を作成し、原本または写しを預かってもらう
- 死後:銀行が遺言執行者として、遺言書に基づき相続財産を分配・処理する
このように、「遺言の作成+執行」を一括で任せられるという点が大きな魅力とされています。
1-2. 信託法上の「遺言による信託」との違い
「信託」という表現を使っているものの、金融機関が提供している遺言信託はあくまで遺言書作成+遺言執行を請け負っているものとなり、信託法上の信託とは異なります。
遺言書を作成する中で、遺言書の中に信託条項を設けることで、遺言者の死後に信託契約を発効させることができますが、金融機関における遺言信託の中ではここまでサポートされていないケースが一般的です。
1-3. 金融機関における遺言信託の業務範囲
金融機関の遺言信託サービスの主な対応業務としては、以下の3つに集約されます。
金融機関での遺言信託の業務範囲
遺言作成支援
銀行職員または提携弁護士による文案作成の補助、公証役場の手配
遺言書の保管
原本または写しを保管(費用がかかる場合あり)
遺言執行
相続発生後に遺言の内容に沿って預金払い戻しや名義変更、資産分配などを代行
上記を金融機関に一括で任せられるという仕組みになっていますが、後述する通り、「遺言内容の自由な設計」や「遺留分・紛争リスクを踏まえた調整」までは原則対応していないところが多く、弁護士に遺言作成と遺言執行を依頼する場合と比較すると対応できる範囲に制限があることが一般的です。
1-4. 金融機関の遺言信託は誰が利用対象となるのか?
金融機関の遺言信託サービスは、主に次のような方を想定した商品設計になっています。
金融機関での遺言信託を活用しやすい方
- ある程度の資産(概ね5000万円〜)をお持ちの方
- 相続人間に目立った対立がないと予想される方
- 定型的な相続(配偶者→子)で、特段の支給条件や管理要望がない方
これらに該当する場合には、金融機関の遺言信託でも一定の目的を果たせる可能性がありますが、それ以外のケース(家族構成が複雑、遺留分に配慮した遺言書作成、事業承継など)では金融機関での遺言信託ではニーズを満たせない可能性があります。
2. 知らずに契約すると後悔するかも?遺言信託の主なデメリット
2-1. サービス内容に限界がある(法的アドバイスは不可)
金融機関が提供する遺言信託サービスでは、遺言の作成支援は受けられますが、内容の法的妥当性を検証・助言するのは本来、弁護士の職域です。たとえば、「この内容では遺留分を侵害してしまうかもしれない」「後の争いの火種になる」といったリスクは、金融機関の担当者では判断できません。その結果、形式的には整っていても、実質的にトラブルを生む遺言になってしまうケースが現実に存在します。
2-2. 複雑な家族関係・紛争案件には対応できない場合がある
家族構成が複雑(再婚・非嫡出子・内縁関係など)な場合や、相続人同士の関係が不安定な場合には、法的に慎重な設計が必要です。 しかし、金融機関の遺言信託はこうした個別事情の調整や争いへの対応に対応していないようなケースも多く、紛争性のある案件は引き受けを断られることもあります。
2-3. 財産価格により手数料が高額になることがある
信託銀行の遺言信託は、相続財産の額に応じてにはなりますが、100万円を超える手数料が発生するのが一般的です。財産が高額の方ですと、数百万単位での費用がかかってしまうこともあります。
2-4. 途中解約・変更が難しい場合もある
遺言信託サービスは、死亡時に効力を発する契約である以上、「やっぱり内容を変更したい」「執行者を別の人にしたい」と思ったときには、再契約や手数料の払い直しが必要になるケースがあります。 特に、金融機関側が一定の条件で「遺言執行を辞退する可能性がある」としている場合もあるため、契約内容の確認と将来的な変更可能性は慎重に見極めるべきです。
3. 弁護士に相談する「遺言書作成+遺言執行」との違い
3-1. 弁護士は遺言書の設計段階から法的リスクをカバー
弁護士に依頼すれば、遺言書の文案設計段階から、遺留分侵害・遺言の無効リスク・遺産分割の実行可能性などを見越したアドバイスを受けられます。 形式的に正しいだけでなく、将来トラブルにならないことを目指した遺言書の内容設計が可能です。
3-2. 万が一紛争化した場合の対応まで一貫対応
金融機関では取り扱いが難しい紛争化してしまった相続手続についても、弁護士であれば継続して対応ができます。遺言執行を進めるうえで相続人同士でトラブルになってしまった場合でも、弁護士を遺言執行者として就けておくことで安心して進められます。
4. 金融機関と弁護士による対応の違い(比較表で整理)
4-1. サービス範囲・費用・対応可能な家族事情で比較
「遺言信託はどこに頼むべきか?」と考えたとき、重要なのはサービスの中身とその業務範囲を把握することです。以下に、金融機関と弁護士による遺言対応の違いを比較表でまとめました。
| 比較項目 | 金融機関の遺言信託 | 弁護士に依頼する遺言書作成+遺言執行 |
|---|---|---|
| 作成サポート | 公正証書遺言の文案支援(形式中心) | 家族構成・税務・紛争リスクを踏まえた個別具体的な遺言書作成 |
| 執行対応 | 定型的相続手続(名義変更など) | 紛争時も対応可能。調停・訴訟対応も可 |
| 対象者 | 標準的な家族構成・高齢者中心 | 複雑な家族構成、事業承継など多様なケースに対応 |
| 柔軟性 | ひな型での作成が一般的 | 家族構成や事情に応じて個別に作成 |
| 費用感 | 100万円超〜が一般的 | 40万〜80万円程度 |
4-2. 金融機関・弁護士どちらを選ぶべき?
遺言信託サービス(遺言書作成+遺言執行)をどこに頼むかを考えるときには、ご自身が「どちらのタイプに近いか」をもとに検討するのがよいでしょう。
金融機関への依頼でもよいケース
- 財産内容が比較的シンプル(現金・預金中心)
- 配偶者と子どもというような典型的な相続関係
- 遺産分割でもめる見込みがなく、相続手続だけ淡々と進めてもらえればよい
- 担当者に定型的な処理を一任したい
- 法的アドバイスや柔軟な設計までは不要
弁護士に依頼をする方が向いているケース
- 家族構成が複雑(事実婚、法定相続人以外に財産を残したい、養子がいるなど)
- 生前贈与や遺留分をめぐるリスクがある
- 不動産や自社株など、相続処理が煩雑な財産がある
- 認知症や障害のある家族への支援設計が必要
金融機関での遺言信託をご利用中の方からのセカンドオピニオンのご相談にも対応しています。すでに遺言を作成された方でも、「この内容で本当に問題ないか?」と不安を感じたときは、ぜひ一度ご相談ください。
5. 遺言信託を選ぶ際に気を付けておきたい点
遺言信託サービスを契約したから、自分の死後の準備は万全と安心していたにもかかわらず、実際には相続人が遺言内容に不満を持ち、執行に協力してくれないというケースがあります。 たとえば、特定の相続人に偏った内容だったり、遺留分の考慮がされていなかったりすると、遺言執行に対して「不公平だ」との反発が生じることがあります。遺言執行者の権限で相続手続自体は遺言執行者のみで進めることはできますが、遺言無効の訴訟や遺留分の請求を受けた場合、金融機関では代理人として紛争調整を行えないため、遺言執行自体がストップしてしまう可能性すらあります。
その他、金融機関での遺言信託サービスでカバーできない対応事項が発生し、結局弁護士に相談し直したというような方も珍しくありません。遺言信託を検討する場合は、こういった点にも留意が必要です。
6. 遺言信託に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 金融機関の遺言信託で相続税対策はできますか?
A. 遺言信託サービスそのものには、相続税対策の機能は基本的に含まれていないことが一般的です。そのため、相続税対策や節税を重視される方は、遺言書の作成段階から税理士を含む体制での設計をおすすめします。当事務所ではグループ内に税理士法人がございますので、遺言を作成する時点から相続税や納税資金の確保を考慮した作成を行っております。
Q2. 生前に遺言信託を契約しても、財産や相続人が変わったら無効になりますか?
A. 無効にはなりませんが、遺言書の内容が実態と合わない内容になるリスクがあります。たとえば、新たに子どもが生まれた、財産の大半を売却した、関係が悪化した相続人がいる──などの場合は、遺言の内容が現実と乖離し、トラブルのもとになる可能性があります。 こうした事態を防ぐには、遺言信託の内容の定期的な見直しと、必要に応じた遺言書の書き換えが重要です。金融機関での遺言信託の場合、内容の変更には別途費用がかかる場合もありますので留意が必要です。
Q3. すでに遺言信託を契約していますが、内容に不安があります。見直しできますか?
A. はい、できます。すでに遺言信託を契約済みの場合でも、弁護士にご相談されたうえで内容を見直し・再度作成することは可能です。当事務所でも「他社で作成した遺言信託に不安がある」「家族の状況が変わったので見直したい」というご相談をいただいております。 まずは現状の内容を確認し、法的・実務的に問題がないかをご相談されることから始めてみられては如何でしょうか。
7. 当事務所での遺言信託サポート内容
7-1. ご相談から遺言書作成・遺言執行まで、全体を見渡した一貫対応
当事務所では、遺言書の作成から将来の執行・名義変更・税務対応まで、遺言信託に関するすべての工程を一貫してサポートしています。 はじめにご相談いただく際には、家族構成・財産状況・過去の贈与・将来の懸念点を丁寧にヒアリングし、その方にとって最もリスクが少なく、希望を実現しやすい遺言内容を設計しご提案します。
また、相続税や遺留分の観点についても考慮した形で遺言書作成を行いますので、相続発生後の紛争予防や税務面まで踏まえた相続対策が可能です。
7-2. 将来の遺言執行に備えた独自サービス
当事務所では、将来の遺言執行費用を前払いできるサービスをご用意しております。事前にお支払いただいた金額の1.2倍を上限として遺言執行報酬に充当させていただきますので、将来的な遺言執行費用負担の軽減につながります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「とりあえず遺言を書きたい」だけでなく、 「将来の相続手続が滞りなく進むか心配」 「家族が困らない仕組みを作っておきたい」 といった方には、ワンストップ体制による相続の全体設計をご案内しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。