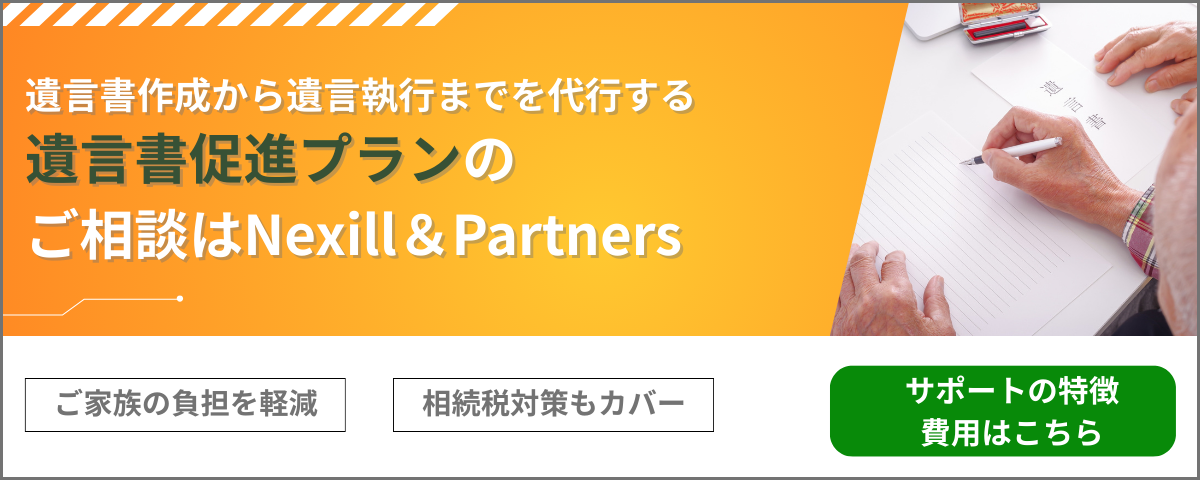遺言書で遺言執行者に選ばれたものの、遺言執行の手続を一手に引き受けるのは負担が大きいと感じる方は少なくありません。
仕事が忙しくて手が割けない、遠方に住んでいて動きづらい、相続人とのやり取りが難しいなどの理由で「誰かに代理をお願いしたい」という声も多く聞かれます。
そこで本記事では、遺言執行者の代理の可否や具体的な手続きの流れを弁護士の視点で解説していきます。
1. 遺言執行者に選任されたら何をすればいい?
1-1. 遺言執行者の基本的役割
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実行するために法律上認められた存在で、被相続人の「代理人」に近い立ち位置を担います。
具体的には、不動産や預貯金などの名義変更、遺産の分配、遺言書に書かれた寄付・遺贈の執行など、多岐にわたる手続きを担当します。
このように、相続人との調整を行いながら、遺言内容を円滑に実行していくことが遺言執行者の最大の役割です。
たとえば、遺言書で特定の相続人に多くの財産を与える旨が書かれているとき、他の相続人との折衝が必要になるケースもあるでしょう。
さらに、金融機関や法務局での各種手続にも着手しなければならず、遺言執行者自身が遠方に住んでいる、または日中動きづらい環境にある場合は実務を進めるだけでも相当な負担となります。
相続人が複数いる場合や、財産の数が多い場合には特に時間と労力を要するため、遺言執行業務の代理を検討する方が増えています。
2. 代理人に遺言執行の手続きを委ねることは可能か?
2-1. 遺言執行者の代理と法律上の考え方
結論からいえば、遺言執行者に選任された個人が第三者を代理人として遺言執行業務を委任することは、法律上可能です。
そのため、通常の代理権の範囲であれば一部の行為を委任状で代理人に任せることができます。
たとえば、司法書士や弁護士などの専門家に相続登記や書類作成を代行してもらうことは日常的に行われているため、どの範囲を委任し、どの範囲を遺言執行者自身が担うかを明確化するのがポイントとなります。
参考・民法第1016条(遺言執行者の復任権) 「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。」と定められており、第三者に業務を依頼することが民法上も想定されています。
2-2. 遺言執行の代理が必要になる典型例(遠方在住・多忙・相続紛争のリスクなど)
遺言執行者が第三者の力を借りたいと強く感じる典型的な場面としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 遠方に住んでいるため、金融機関や役所へ何度も足を運べない
- 多忙で相続人と連絡を取る時間がなかなか取れない
- 相続人同士の折衝が難航し、法律知識や調整力が必要
- 不動産の相続登記や税務申告など専門的な作業が多い
こうした状況では、専門家に代理をお願いすることで、実務の一部または大半を任せられ、結果的に遺産分割をスムーズに進めることが期待できます。
3. 専門家を代理人として立てることのメリット・デメリット
ご自身の代わりに遺言執行を代理する人間として弁護士や司法書士を選任すれば、法的手続や書類作成において高い専門性を発揮できます。
とくに相続トラブルが想定される場合は、弁護士に依頼することで万が一揉めてしまった場合でもその後の交渉・訴訟対応まで業務対応範囲を広げられるのでスムーズな問題解決が可能です。
一方で、専門家に代理を依頼すると報酬が発生するため金銭的な負担は一定程度発生するほか、遺言執行者はあくまで最終的な責任を負う立場にあり、想定外のトラブルが発生した際に遺言執行者自身が相続人から責任を追及される可能性をゼロにはできません。
それでも、スムーズな相続手続とトラブル回避の可能性を高める選択肢として、特に相続人間の意見対立が予想される場合や、財産が多岐にわたる場合は、専門家による遺言執行を行うことで遺言執行者の負担を軽減しつつ確実に手続きを進められるメリットの方が大きいでしょう。
4. 具体的な代理人選任の流れ
4-1. 委任契約締結・委任状等の準備
遺言執行業務において代理人を立てるには、遺言執行者と代理人の間で「委任契約」を結ぶのが基本です。
委任契約の内容には、「具体的にどの行為を代理するのか」「報酬はいくらで、いつ発生するのか」などを明記し、合意後に遺言執行業務に着手します。
また、遺言執行を行う上で役所や金融機関で提出する場面があるため、書面による委任状の作成や、必要に応じて印鑑証明書や身分証明書などの確認書類の準備を行います。
4-2. 相続人への共有と合意確認
遺言執行における代理人を選任する際、相続人全員への告知や同意が必須とまでは言えませんが、後々「知らされていなかった」「勝手に代理人を立てられた」との不満が生じると、トラブルを招きかねません。
なるべく全相続人へ代理人選任の意図を説明し、必要に応じて同意を得ておくことで、遺言執行手続きの透明性を高められます。
また、実務を進める段階でも、定期的に相続人へ状況を共有し、経過を可視化しておく方がよいでしょう。
4-3. 代理人就任後の実務と報酬支払いのタイミング
代理人が就任した後は、不動産名義変更や預金解約、相続税申告など、委任された範囲内の業務を実施します。
報酬の支払いは、着手金と報酬に分かれる場合や、着手時に支払う場合、作業が完了したタイミングでまとめて支払う場合など、契約形態によって異なります。
ここは各事務所によって報酬規程が異なりますので、依頼時に確認をされてください。
5.よくある質問Q&A
Q. 遺言執行者が複数いる場合でも代理人を立てられますか?
A:
遺言執行者が複数人選任されているケースでも、一部業務の委任や代理人選任は可能です。
ただし、どの執行者がどの範囲を担当し、どこを代理人に委託するのかが不明瞭だと手続きが混乱しがちです。
複数の執行者間で役割分担を明確にしたうえで、代理人の権限や責任範囲を協議しておくことがポイントです。
Q. 遺言書自体に「執行者は代理人を使ってはいけない」と書いてあったらどうなりますか?
A:
民法1016条第1項において、遺言執行者の復任権が定められていますが、その但し書きにおいて、遺言書に復任を禁止する旨が記載されていれば、復任はできない規定となっています。
遺言執行を第三者に委任させず、遺言執行者本人に必ず行わせる遺言書は、あまり見かけることは多くないですが、念のためそのような規定が入っていないか確認しなくてはなりません。
Q. 遺言執行者が高齢・認知症になってしまったらどう対応すればよい?
A:
遺言執行者が判断能力を失ったり、大幅に低下したりした場合、代理人を立てるだけではなく、家庭裁判所で執行者の変更・解任を求める手続をとることが考えられます。
任意後見制度などを利用して判断能力の補完をすることも検討されますが、状況によっては新たな執行者を選任するほうが手続がスムーズになるケースもあります。
Q. 代理人を途中で変更・解約することは可能?
A:
委任契約ですから、基本的に「委任者または受任者はいつでも契約を解除できる」と民法に定められています。
ただし、一方的な解除をすると、契約上の違約金や作業実費の精算などが発生する場合があります。
相続手続が長期化するケースもあるため、「ここまでは旧代理人が担当し、途中から新代理人が引き継ぐ」という明確な引き継ぎ手順を定めることが重要です。
本コラムのまとめ:代理人の活用で負担を軽減し、円満な遺言執行を
遺言執行者に選ばれたものの、多忙や遠方在住など様々な事情から「すべてを引き受けるのは難しい」と思われる方は少なくありません。
そこで、弁護士や司法書士など専門家を代理人として立てることで、必要な場面を確実にサポートし、スムーズに手続きを進められるメリットがあります。
当事務所では、弁護士だけでなく税理士や司法書士も同じグループ内に在籍していますので、相続税申告や不動産登記など、遺言執行時に必要となる専門業務をまとめて担当可能です。
遺言執行者と代理人の関係で生じる複数の手続きを一体的に進められるため、二度手間やコミュニケーションロスを減らせます。
遺言執行者になったものの業務が進められていないとお悩みの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。