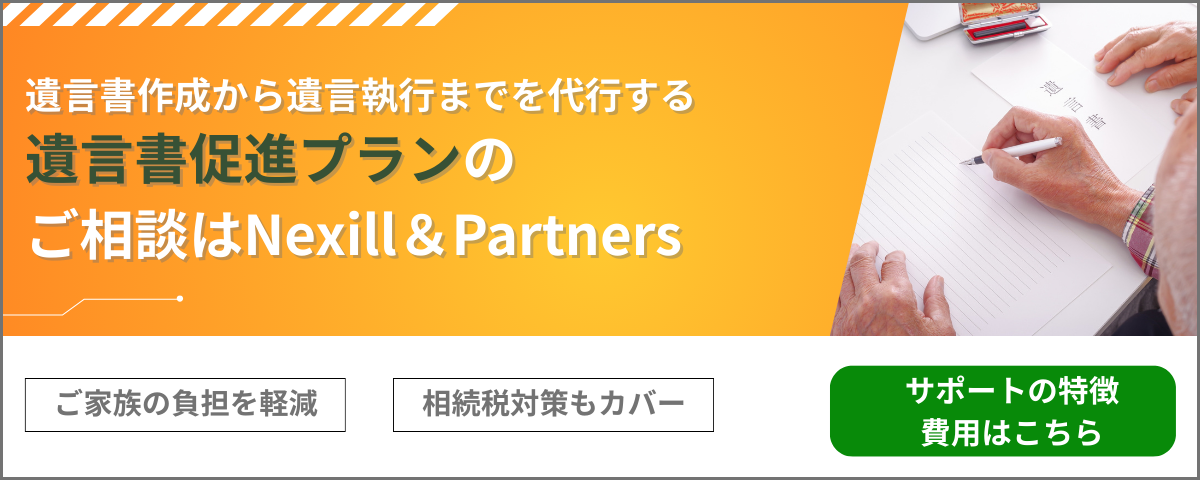遺言書があるにもかかわらず、実際に相続が発生したときに「遺言の内容が正しく実現されるのだろうか」「相続財産をどうやって分配していくのか」と悩む方は少なくありません。
特に、遺言執行者に指定されている場合や、遺言執行の流れそのものを把握していないと、何から手をつければよいのか戸惑ってしまうこともあります。
本記事では、遺言執行がどのように進められるのか、その全体像や具体的な手続きのステップを詳しく解説します。
弁護士・税理士・司法書士といった専門家を交えながら遺言内容を実現していく重要性もふまえ、遺言執行におけるポイントや注意点をわかりやすくまとめました。
ぜひ参考にしていただき、円滑な相続の実現にお役立てください。
1.遺言執行とは何か
遺言執行の基本的な意味と目的
「遺言執行」とは、故人(遺言者)の遺言書に記載された内容を現実に実行し、相続財産の分配や名義変更などを滞りなく進めるための手続きです。
遺言書に書かれているとおりに財産の管理・引き渡し・各種届出を行うことで、遺言者の最終的な意思を実現する役割を担います。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類がありますが、いずれの場合も遺言執行者が手続きを主導することでスムーズに相続が進められます。
特に、「遺贈(特定の受遺者へ財産を与える行為)」や「相続人の廃除/廃除の取消」といった手続きが含まれるときは、遺言執行が不可欠です。
遺言執行が必要となるケース
遺産分割の具体的な指定がある場合
たとえば「不動産は長男に相続させる」「預貯金を特定の受遺者へ渡す」といった指定があるケースでは、その内容を実現するために遺言執行が求められます。
相続人の認知・廃除が含まれている場合
遺言書によって新たに認知をする、あるいは相続人廃除を行うには、家庭裁判所へ申し立てる手続きが必要です。
これらを行うのは基本的に遺言執行者の役割とされています。
遺言執行者が明記されているケース
遺言書の中で「〇〇を遺言執行者とする」と指定があるときは、その人物が遺言執行者として正式に手続きを行います。
遺言執行者の役割と権限
遺言執行者は、相続財産を管理し、各種名義変更や財産分配を実行し、最終的に遺言の内容を実現するための中核的存在です。
具体的には以下のような権限・義務があります。
2.遺言の内容に沿った形で不動産・預貯金・株式などの名義変更を行う権限
3.受遺者(遺贈を受け取る人)への財産引き渡し
4.家庭裁判所に対して相続人廃除や認知届出を申し立てる
遺言執行者が対応を怠ると、他の相続人や受遺者に財産分配が行き渡らない、相続税の申告に間に合わない等のトラブルへ発展するおそれがあります。
そのため、選任されたら早期に手続きを開始し、計画的に進めることが大切です。
2.遺言執行者が指定されている場合の最初のステップ
①就職通知の送付と受領
遺言書により遺言執行者が指定されている場合、指定を受けた人は「遺言執行者に就任するかどうか」を判断し、就任するのであれば「就職通知書」を相続人に送付します。
就職通知書の意味
遺言執行者が「自分は執行者としての任務を受ける(就任する)」ことを正式に表明するための文書です。
就任しない(辞退)場合は、相続人や家庭裁判所に辞退を伝える必要があります。
②遺言書の写し・内容の開示
遺言執行者が就任すると、相続人全員に遺言書の内容を開示するのが一般的です。
とくに自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認した後に内容を開示する流れとなります。
また、公正証書遺言であれば、公証役場で作成した写しを相続人に送ることで内容を周知できます。
③家庭裁判所との関係(検認が必要な場合など)
自筆証書遺言が見つかったとき
遺言者が残した自筆証書遺言は、基本的に「検認」という手続きを経て、その内容を確認します。
検認は家庭裁判所で行われ、相続人全員に検認日を通知したうえで開封するのが原則です。
選任手続きが必要となるケース
遺言執行者が指定されていない場合など、家庭裁判所に申し立てをして遺言執行者を選任してもらうことがあります。
この点は「4.遺言執行者が指定されていない場合」で詳述します。
3.遺言執行の流れと手順
STEP1:相続人の確定と遺言内容の確認
まず、相続人が誰なのかを戸籍調査によって確定します。
複数回の婚姻や離婚、養子縁組などがあると複雑になるため、遺言執行者は本籍地や過去の戸籍を辿り、全ての相続人を漏れなく把握しなければなりません。
そのうえで、遺言書に記載されている内容(財産の分け方や遺贈など)を再度確認し、実務に着手します。
STEP2:相続財産の調査・財産目録の作成
次に、被相続人(遺言者)の財産を調査し、財産目録を作成して相続人へ交付します。
財産には不動産や預貯金、株式・投資信託、生命保険、貸付金などが含まれる場合がありますし、負債や未払い税金なども含めて全体像を把握することが重要です。
相続財産目録には、不動産の所在地・評価額、預貯金の残高、株式銘柄・株数、負債残高などを記載し、相続人全員に示します。
STEP3:遺留分への配慮が必要なときの対応
遺言書で特定の受遺者に多くの財産を渡すよう書かれている場合、他の法定相続人の遺留分を侵害するケースがあります。
遺留分侵害額請求がなされる可能性もあるため、遺言執行者は遺留分請求が想定されるときは相続人間の調整や法律上の対応を検討することが大切です。
STEP4:遺贈・特定財産の引き渡し手続き
遺言書に「○○の不動産をAに遺贈する」や「預貯金の一部をBに与える」といった指定がある場合は、遺言執行者が財産の名義変更や引き渡し手続きを行います。
受遺者に実際の財産を交付することで、遺言の内容を実現します。
STEP5:預貯金や有価証券の名義変更
相続財産に預貯金や株式・投資信託などの有価証券が含まれている場合、銀行や証券会社で相続手続きを行い、相続人や受遺者の名義へ変更します。
必要書類としては、遺言書や執行者の就任証明書、相続人全員の戸籍などが一般的です。
STEP6:不動産の相続登記手続き
不動産を相続や遺贈で受け取る場合は、不動産の登記名義を相続人や受遺者の名義に変更する必要があります。
遺言執行者が中心となり、法務局へ相続登記の申請を行います。
固定資産税の課税情報や不動産取得税、相続税申告などとの兼ね合いもあるため、税理士など他の専門家と連携して手続きを進めるとスムーズです。
SYEP7:執行完了後の報告・書面交付
遺言執行者は、一連の手続きが完了した時点で、相続人や受遺者に対して経過や結果を報告する義務があります。
報告書の作成
どの財産を誰に引き渡したのか、各種名義変更をいつどのように行ったのか、といった内容をまとめます。
相続税申告の要否
相続財産が一定額を超える場合には相続税申告が必要となるため、期限内(被相続人死亡から10か月以内)に行いましょう。
4.遺言執行者が指定されていない場合
遺言執行者の選任手続き(家庭裁判所での選任など)
遺言書に「遺言執行者」として特定の人物が指定されていないケースでは、家庭裁判所に選任を申立てる方法があります。
家庭裁判所の選任
執行手続きが複雑な場合などは、家庭裁判所に申し立てて、適切な人を遺言執行者として選んでもらいます。
相続人が遺言執行者となるリスクとメリット
相続人の一人が執行者になる場合、専門家を頼まなくても費用が抑えられるメリットがあります。
一方で、名義変更や相続人間の調整などを素人が全て担うのは負担が大きく、トラブルに発展するリスクも高いです。
専門家を遺言執行者に選任するメリット
弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に選ぶことで、以下のようなメリットがあります。
■相続人間の紛争が起きにくい
■相続税申告や不動産登記、税対策を一括で行いやすい(税理士や司法書士と連携している専門家の場合)
5.遺言執行者の辞任・解任・後任選任
辞任を希望する場合の手続き
遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合には辞任することが認められます。
ただし、そのためには家庭裁判所の許可が必要とされるケースが多く、正当な理由なく辞めることは難しいとされています。
解任が認められる要件と手続き
遺言執行者がその義務を怠った、不正が発覚した場合などは、家庭裁判所に対して「解任の申立て」を行うことができます。
ただし、解任の要件は法律で定められており、実際に解任が認められるには一定の正当事由が必要です。
遺言執行者が亡くなったときの対応
遺言執行者が作業途中で亡くなった、または高齢や病気で続行できなくなった場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所へ後任の遺言執行者選任を申し立てることが一般的です。
6.遺言執行で生じやすいトラブルと対処法
遺言の無効主張や遺留分侵害を巡る紛争
遺言の有効性(書き方が不適切だった、意思能力がなかった等)を巡って相続人や受遺者同士が争うケースがあります。
また、遺留分を巡る紛争もよく起きるため、執行者は問題発生の早期段階で専門家(弁護士)に相談し、適切な対応を図る必要があります。
相続人同士の意見対立と遺産分割協議の紛糾
たとえ遺言があっても、財産目録の内容や評価、相続放棄などを巡って相続人間で意見対立が起こることは珍しくありません。
円滑に遺言内容を実現するためには、執行者が丁寧な説明と調整を行い、必要に応じて相続に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
執行者が義務を果たさない(あるいは能力不足)場合の対処
遺言執行者が業務を放置したり、誤った手続きにより他の相続人に損害を与えたりすると、解任申立てや損害賠償問題に発展することもあります。
弁護士に早めに相談して、適切な対策をとることが重要です。
7.専門家(弁護士・税理士・司法書士)に依頼するメリット
複雑な相続財産や多額資産への対応
被相続人が高額の金融資産や多数の不動産を保有している場合、財産の調査・評価・名義変更の手続きは非常に煩雑です。
また、相続税の計算・申告には税務の専門知識が求められます。
相続に強い専門家に依頼をすることで、スムーズに遺言執行手続きを完了できます。
トラブル防止と早期解決につながるサポート
専門家を介在させることで、相続人同士のコミュニケーションが円滑になり、紛争の火種を早期に把握して解決へ導きやすくなります。
特に、遺言執行者が中立的な立場にある弁護士であれば、感情的な対立を最小限に抑えることが可能です。
8.当事務所が提供する遺言執行サポートの強み
①多士業連携による総合的な相続対応
当事務所は弁護士のみならず、税理士や司法書士など幅広い専門家が在籍しています。
これにより、相続税申告や不動産の名義変更なども含めて一体的にサポートする体制が整っています。
②過去の実績と専門性
相続・遺言分野のご相談・案件対応を多数手がけ、複雑な相続財産や海外資産が絡むケースなど、難易度の高い事例にも対応実績があります。
豊富なノウハウを活かして、最適な解決策をご提案いたします。
③無料相談予約のご案内
当事務所では、初回の無料相談を実施しています。
「遺言執行者に指定されたがどう進めるかわからない」「遺言執行を進めているが遺留分を巡って相続人同士が対立している」など、お気軽にご相談ください。
9.まとめ
遺言執行を円滑に進めるために
遺言執行は、被相続人の遺言書に書かれた意思を正しく実現するための重要な手続きです。
相続人の確定、相続財産目録の作成、各種名義変更など、やるべきことは多岐にわたります。
特に、遺言執行者として指定された場合は、自ら進んで円滑に事を運ばないと、相続全体が停滞してしまう可能性がある点に注意が必要です。
専門家への早期相談の重要性
相続財産が多額になるほど、不動産や金融資産の評価、相続税の申告、相続人間の調整といった作業が煩雑になるため、専門家のサポートが大きな助けとなります。
当事務所のように弁護士・税理士・司法書士が連携して対応できるところであれば、手間や時間面でのメリットも期待できます。
ぜひ、早めに専門家へご相談いただき、円滑かつ確実な遺言執行を実現していただければ幸いです。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。