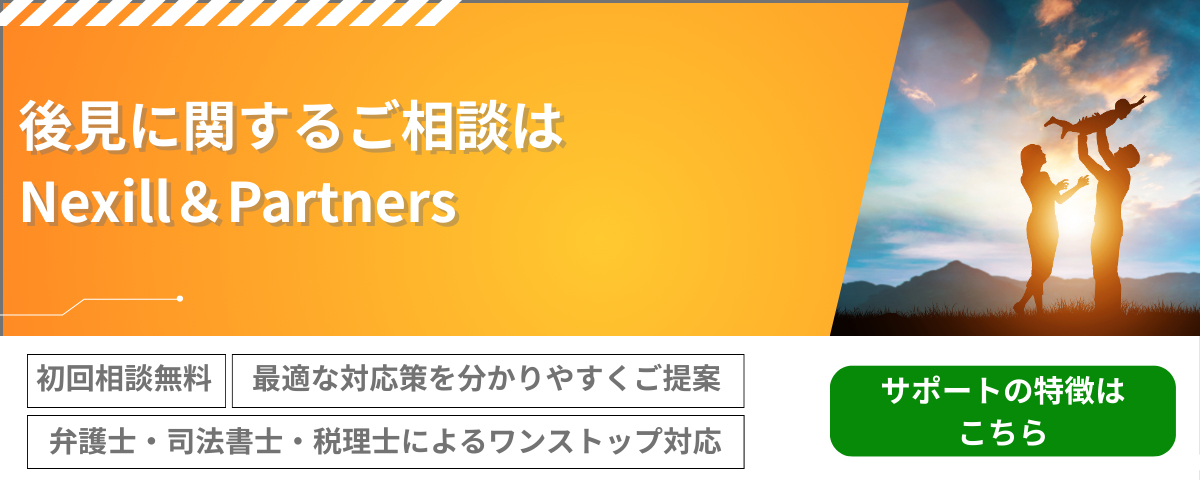認知症対策や介護費用の捻出などを検討する際、不動産の売却が重要な選択肢になることがあります。
ただ、所有者本人の判断能力がない場合は、本人に代わって「任意後見」を活用して売却できるのか分からず不安を抱える方も多いでしょう。
本記事では、任意後見制度を利用して不動産を売却するポイントや注意点を弁護士の視点から分かりやすく解説します。
任意後見人が不動産を処分するための条件や手続きを詳しく取り上げますので、今後の対策を検討されている方はぜひ参考にしてください。
1.任意後見とは? 不動産売却は本当に可能なのか
1-1.任意後見制度の概要と法定後見との違い
任意後見制度は、自分の判断能力が十分にあるうちに、将来の財産管理や契約行為を「どのように、誰に任せるのか」を契約によって定めておく仕組みです。
法定後見が「判断能力が衰えた後、家庭裁判所が後見人を選任する制度」であるのに対し、任意後見は「判断能力がある段階で、本人が自由に後見人(候補者)や業務範囲を決めておける点」が大きな違いです。
まだ判断能力がしっかりしていて、自分自身で後見業務の範囲について意思表示をしておきたいと思われる方には、任意後見の方がメリットを感じやすいでしょう。
1-2.任意後見人ができること・できないこと
任意後見契約では、契約書(公正証書)に「後見人に何をしてもらうか」を詳細に記載し、相続人や家族が望む形で財産管理を委任できます。
具体的には、金融機関の口座管理や施設入所の手続き、定期的な支払いなどがあります。
一方で、「死後事務処理」や「遺言書作成の代理」などは任意後見人の権限外です。
また、契約で定めていない行為については、後になって「後見人として勝手に行える」とは限りません。
そのため、不動産売却を想定しているのであれば、契約時に「不動産処分の権限」を明記しておく必要があります。
1-3.不動産売却が問題になるケース
高齢の親が実家を所有しており、介護費や施設入居費を工面するために売却したい場合、すでに認知能力が低下していると、法定後見(成年後見)を選ぶ方も少なくありません。
しかし、法定後見は本人や親族だけで後見人を自由に決められず、家庭裁判所が選任する仕組みです。
そこで「事前に任意後見契約を締結して、必要になった時点で後見人(=任意後見人)に財産管理を任せたい」と考える方もいるでしょう。
そうしたとき、「そもそも任意後見人に不動産を売却する権限があるのか?」が大きな疑問点となります。
2.任意後見人による不動産売却の法的根拠と必要な条件
2-1.「代理権目録」に不動産処分権限が含まれているか
任意後見契約では、公正証書で後見人の代理権を詳細に定めると同時に、契約内容を「代理権目録」として登記します。
この代理権目録に不動産売却(処分)権限が明記されていれば、任意後見人は被後見人に代わって不動産を売却することが可能です。
逆に、契約書に不動産処分の記載がない場合には売却手続きが難しくなります。
そのため「将来は自宅や所有地を売却するかもしれない」と考えているなら、契約締結時に不動産処分権限を盛り込んでおくことが必須です。
2-2.任意後見監督人は必要? 事前の同意や許可の有無
任意後見契約が正式に効力をもつと、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
監督人は任意後見人の業務をチェックする立場ですが、法定後見のように「不動産売却には家庭裁判所の許可が必要」というルールはありません。
ただし、売却の内容が被後見人の利益に反しないかどうかを監督人に説明し、十分に納得を得てから進めるのが望ましいでしょう。
任意後見監督人から明確に反対意見が出ているのに強行すると「善管注意義務」違反などで問題が生じる可能性もあります。
2-3.家庭裁判所への許可申立ては不要なのか
法定後見では、居住用不動産の処分などに際し、家庭裁判所の許可が必要とされています(民法859条の3)。
しかし、任意後見の場合、原則としてこうした裁判所の許可は不要です。
これが法定後見と比べたときの大きなメリットの一つといえます。
ただし、あくまで「代理権目録に適切な記載があり、売却が被後見人の利益を損なわない」と判断される場合に限られますので、ここを満たしている必要はあります。
3.居住用不動産の売却における注意点
3-1.本人の居住権をどう確保するか
売却しようとする不動産が被後見人(本人)の自宅である場合、もし本人がまだ居住しているなら、売却後の住まいをどうするかをあらかじめ考慮しなければなりません。
施設入居費用の捻出が目的であれば、同時に施設入所先との契約手続きも見通しを立てたうえで進める必要があります。
また、本人が「住み慣れた家を離れたくない」という意思を持っている場合には、意思を尊重する方向でほかの財源を検討するのが望ましいケースもあるでしょう。
3-2.「善管注意義務」の視点からみた売却価格の査定
任意後見人が不動産を処分する場合「より高い価格で売却するよう努力する義務」が課されます。
これを「善管注意義務」と呼び、もし相場より極端に安い価格で売却してしまうと、後で被後見人や相続人から不満が出たり、監督人との間で争いが起きたりするリスクが高いです。
不動産会社から複数の査定を取り、適正価格を確認しながら売却活動を進めるのがポイントとなります。
3-3.法定後見との比較:許可・手続き面での違い
法定後見だと、被後見人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要で、売却の手続は容易ではありません。
一方、任意後見では本人が事前に権限を付与しているため、裁判所の許可を要しない点が魅力です。
ただ、売却行為を任意後見人が主導しなければならないため、後々のトラブルを避けるためにも、実務上は監督人に相談しながら進める方が安全でしょう。
4.売却手続きの流れと必要書類
4-1.売主(被後見人)の意思確認
被後見人名義の不動産を売却するにあたっては、まず「被後見人自身の意思」をできる限り把握することが大切です。任意後見の場合でも、すでに認知能力が低下しているケースでは、直接的に「この不動産を売却してよいか?」と尋ねても十分な返答が得られないことが少なくありません。そのため、以下のポイントに留意して進めます。
1.可能な範囲で被後見人の意向を確認する
- まだ意思能力が部分的に残っているようであれば、簡単な言葉や図などを用いながら、売却の目的(例:施設入所費用を確保する)や代替の居住先などについて説明し、被後見人が納得しているかを確認します。
- すでに判断能力がほとんどなく、本人の意思表示が難しい場合は、任意後見契約を結んだ時点でどのような意図があったか、契約書や家族・親族への聞き取りなどによって被後見人の考えを推定することが必要です。
2.監督人・親族との協議による利益判断
- 本人の意向や不動産売却の必要性を客観的に検証するため、任意後見監督人や親族とも話し合い、売却が被後見人の利益を最大限に守る選択かどうかを検討します。
特に居住用不動産の場合は、被後見人の居場所・生活環境を確保する代替案との兼ね合いを考慮しなければなりません。
3.市場価格の把握と適正な売却条件の設定
- 不動産会社に査定を依頼し、相場より著しく低い価格での売却にならないよう留意します。
複数社の見積もりを比較し、売却時の手続き費用や税金、介護費用の見込みなどを合わせて検討しながら進めるのが望ましいです。 - 被後見人が高額の借金を抱えている場合や施設入所が迫っている場合でも、性急に売り急いで相場より大幅に安くしてしまうと「善管注意義務」に反する恐れがあります。
客観的な資料や専門家の助言をもとに、合理的な条件下で売却することが重要です。
4-2.売買契約・決済
任意後見人が被後見人の意思確認や市場調査を終えたら、実際の不動産売買手続きへと移ります。
大まかには以下の手順を想定してください。
1.不動産会社との媒介契約
- 売却を進めるにあたり、不動産会社と「媒介契約」を結んで仲介を依頼します。
- 媒介契約には一般・専任・専属専任といった種類があり、それぞれ広告展開やレインズ登録の義務、業者の活動範囲などが異なります。
被後見人の財産を守るためにも、複数社からの提案を比較検討し、適切な形態を選びましょう。 - 媒介契約書には、売り出し価格や仲介手数料、契約期間などが明記されます。
任意後見人は、代理権目録(後見人に不動産売却権限が付されていることの証明)を示しながら契約締結を行います。
2.買主との交渉と売買契約
- 不動産会社の広告や媒介活動によって買主が見つかったら、価格や引き渡し時期などの条件を交渉します。
- 重要事項説明(宅地建物取引業法上の説明義務)を受けたうえで、売買契約書を作成・締結します。
任意後見人が「売主」として署名押印し、印鑑証明書や本人確認資料など必要書類を準備しましょう。 - 売買契約時には手付金を受領することが多く、受領時点で契約が成立します。
ただし、後々のトラブルを防ぐため、契約書や重要事項説明書は事前に十分確認してください。
3.決済と引き渡し
- 契約後、買主の住宅ローン審査や決済の準備が整えば「決済日」を迎えます。
- 決済日には、買主から残代金を受け取り、同時に物件を引き渡すのが通例です。
不動産会社・金融機関・司法書士などが同席する場面もあり、登記申請(所有権移転・抵当権抹消など)がスムーズに行われるよう段取りを組みましょう。 - 任意後見人は、手続きに必要な書類(印鑑証明書・住民票・登記識別情報など)を的確に用意し、売却代金の入金を確認したうえで鍵や関係書類を買主に引き渡します。
4-3.決済後の手続
売買契約と決済が終わったからといって、任意後見人の業務がすべて終了するわけではありません。
被後見人の利益を最優先に考え、次のような手続きや管理を行う必要があります。
1.登記完了の確認
- 司法書士が決済当日に登記申請を行い、所有権移転登記などが完了するまで数日~数週間かかる場合があります。
- 申請が通った後に発行される登記事項証明書を取得し、売却処分が正式に完了したことを確認しましょう。
2.売却代金の管理と報告
- 受領した売却代金を、任意後見人が適切に管理することが大切です。
必要に応じて、被後見人の預金口座へ入金し、施設入所費用や医療費、日常生活の支払いに充てるなど、売却の目的に沿って活用します。 - 後日に備えて、売却代金の使途や収支記録を明確にし、任意後見監督人や親族へ定期的に報告することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
3.被後見人の居住環境などの調整
- 居住用不動産を売却した場合、被後見人が住む場所を確保する必要があります。
既に施設入所しているなら問題ありませんが、もし売却後に新たに転居するなら、引っ越し手続きや施設契約を任意後見人が代理で行わなければなりません。 - この過程でも、被後見人の体調や希望を踏まえつつ、家族・医療機関・施設職員と連携して進めることが望ましいです。
4.税務申告や関連手続き
- 売却に伴って譲渡所得税や住民税、あるいは相続税の絡みなど、税務上の対応が必要になるケースがあります。
金額の大小にかかわらず、早めに税理士へ相談し、納税や確定申告を漏れなく行いましょう。 - 相続税の有無や他の財産に関する手続きも含めて、専門家へ一括で相談しておくと安心です。
任意後見人による不動産売却の一般的な手順は上記のようなイメージとなり、これらを確実に実行することで、「任意後見人としての善管注意義務」に応じた不動産売却が完結します。
売却代金は被後見人の今後の生活費や医療・介護費用に充てることが多いため、管理・活用の方法についても適切な判断と報告が必要となります。
5.任意後見の不動産売却は専門家に相談を|当事務所が提供するサポートと専門家活用のメリット
5-1.弁護士・税理士・司法書士が在籍する当事務所の強み
不動産売却には売買契約や登記、場合によっては相続税の申告なども絡んできます。
当事務所では、弁護士だけでなく税理士・司法書士も在籍しており、ワンストップで手続きを進められる体制を整えております。
任意後見契約の締結段階から最終的な売買完了まで、一貫してサポートいたします。
「任意後見で不動産を売却したい」「親が施設入所を検討しており、自宅の売却が必要」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。