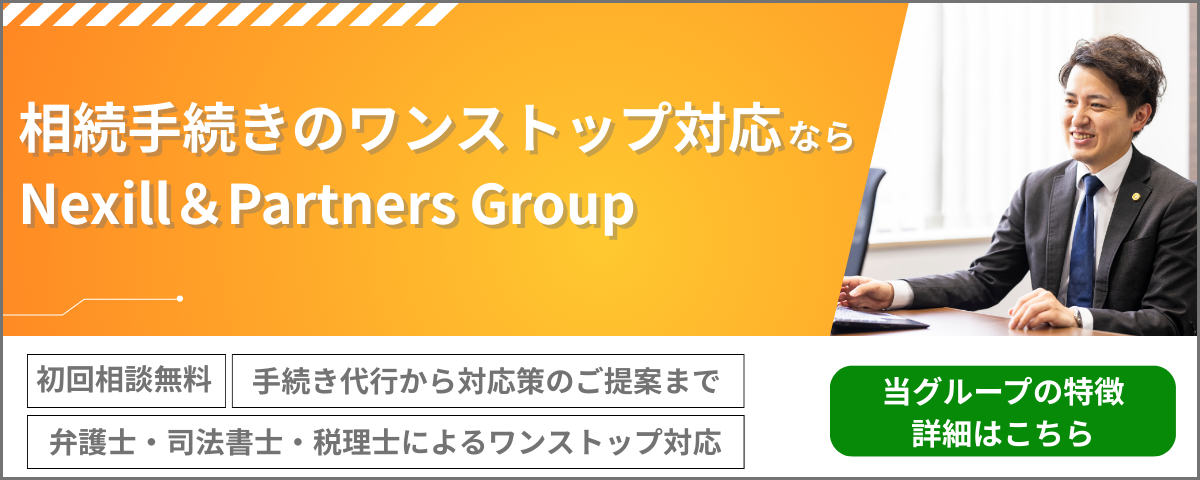相続が始まった際に、まず行わなければならないのが相続人調査です。
誰が法定相続人に当たるかを把握しないまま遺産分割協議や名義変更を進めてしまうと、後になって見落としていた相続人が現れるおそれがあります。
そして、この相続人調査の要となるのが「戸籍の読み解き方」です。
実は、古い戸籍のなかには改製原戸籍や除籍謄本があり、手書きで書かれている部分や旧字体が残っている場合も珍しくありません。
こうした戸籍を正確に読み解くには、少しコツを押さえることが大切です。
この記事では、戸籍の基本的な構成や読み間違えやすいポイントを中心に解説します。
スムーズに相続人調査を終わらせ、後々のトラブルを回避するための参考にしてください。
1.はじめに|戸籍の読み解きが重要な理由
相続手続きでは、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を確認することで、誰が相続人になり得るかを確定します。
しかし、戸籍は何度か改製が行われており、古い除籍謄本や改製原戸籍は筆書きや旧字体で書かれていることも珍しくありません。
このため、単に戸籍を「収集」するだけでは不十分で、「正しく読めているか」が大きなカギを握ります。
読み間違いで認知された子や離婚した配偶者との間の子を見落としてしまうと、後から相続人が追加で発覚し、協議や手続きがやり直しになるリスクが高まるのです。
2.戸籍調査の基本概要―相続人特定に必要な範囲は?
そもそも相続人調査とは
相続人調査とは、法定相続人に該当する人を正確に洗い出す作業です。
民法の規定で、相続人には配偶者や子ども、さらに子がいない場合は直系尊属や兄弟姉妹などが含まれます。
誰が相続人になれるかは、戸籍の記載内容によって判断されるため、戸籍を取得して細かくチェックすることが欠かせません。
どの段階で戸籍収集が必要になるのか
相続が開始すると、遺産分割協議や名義変更(相続登記)など、さまざまな手続きを進める必要がありますが、ほとんどの手続きで「相続人全員の同意」や「相続人全員の署名押印」などが要求されます。
その前提として「相続人が誰か」を明確にするため、戸籍調査で法定相続人を確定するのが最初のステップです。
3.戸籍の種類|読み方に影響する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い
①現行戸籍:最新の情報がまとまった戸籍
現行戸籍とは、現在使われている戸籍のことで、被相続人が死亡時点で在籍していたものを指します。
基本的にはこの現行戸籍を起点に、その前の本籍地や改製原戸籍などをさかのぼっていく流れとなります。
②除籍謄本:在籍者が全員除かれて「空」になった戸籍
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた全員が婚姻や死亡などで除籍され、最終的に「空」になった状態の戸籍のことです。
被相続人が転籍したり、死亡したりした戸籍もこの「除籍」に当たるため、相続人の存在を確認するために重要な情報が含まれています。
③改製原戸籍:旧様式の戸籍が改製されたときの元データ
明治や大正、昭和に作られた古い戸籍は、法改正などで新しい様式に切り替えられてきました。
切り替え前の状態が保管されているのが改製原戸籍です。
ここには婚姻や離婚、認知などの詳細が手書きで書かれている場合が多く、読み解きには慣れや注意力が必要です。
4.実際の戸籍謄本はどう読む?用語解説と記載事項のチェックポイント
日付・本籍・筆頭者:最初に確認すべき基本事項
まず戸籍謄本を手にしたら、交付日や本籍地、筆頭者の名前など、最初に目立つ位置に書かれている基本情報をチェックします。
筆頭者はその戸籍が編製された当時の「戸籍の代表」であり、実際に相続人になるとは限らない点に留意しましょう。
婚姻・離婚・養子縁組・認知などの記載を読み解く
戸籍には、婚姻・離婚・養子縁組・認知など、家族関係の変動が記載されます。
たとえば-「昭和◯◯年◯月◯日婚姻」-「平成◯◯年◯月◯日養子縁組」-「認知届受付」などのように書かれている場合、その日付にどのような事実があったのかを正しく読み取る必要があります。
誤って見落とすと、相続人の範囲を間違える危険があります。
改製原戸籍や除籍謄本でありがちな手書き表記の注意点
改製原戸籍や除籍謄本には、旧字体や難読漢字、カタカナ交じりの手書き表記が残っていることがあります。
筆記体のような書き方で「高」と「髙」が混在していたり、名前の読みが一見判断しづらい場合もあるので、複数枚を突き合わせて解釈することが必要となります。
5.具体的な読み解き手順|時系列で整理しながら相続人を洗い出す
STEP1:出生~死亡まで連続する戸籍を取得する
相続人調査では、被相続人が「生まれてから死亡するまで」の戸籍をすべて取得します。
最終本籍地の市区町村役場で請求し、不足があれば前の本籍地に追加で請求する流れです。
すべて揃ったら、まずは一通り目を通して「何枚の戸籍が存在するか」を把握します。
STEP2:婚姻・転籍の履歴を古い順に追っていく
次に、最も古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)から順番に読み進めます。
記載されている婚姻・離婚の事実や転籍日を軸に、被相続人がどのような家族関係を持っていたかを整理しましょう。
古い順に見ることで、誕生した子供の情報や認知の届出などを自然に時系列で追えるため、混乱を防ぎやすいです。
STEP3:兄弟姉妹・甥姪の有無は親の戸籍もチェック
被相続人に子がいない場合や、子が先に死亡して代襲相続が発生する可能性がある場合には、被相続人の父母の戸籍も確認する必要が生じます。
兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になるケースでは、被相続人の親の戸籍を読み解くことで、家族構成を正確に把握できるのです。
6.戸籍記載を読み誤りやすいケースと対策
旧字体・手書き表記で名前や続柄が判別しにくい
古い戸籍には、現在使われていない旧字体が混じっている場合があります。
名前の字が微妙に違って見えることがあるので、同一人物なのか別人なのか判別できず混乱するケースもあるでしょう。
離婚や再婚が多い場合の子どもの続柄に要注意
被相続人が離婚や再婚を繰り返していると、子どもが前婚の配偶者との間にいたり、養子縁組で親族関係が変わっていたりするケースがあります。
戸籍で確認せずに「子どもはいないと思っていた」という思い込みで進めると、後から相続人の存在が判明してトラブルになりがちです。
生前に養子縁組をしていた場合の注意点
実子以外に養子がいた場合や、逆に養子縁組を解消していた場合は、戸籍にその旨が記載されています。
養子縁組は法定相続人の範囲や相続分に直結するため、しっかりと読み取っておかないと計算を誤るおそれがあります。
ご自身のみでの作業が行き詰った場合は、弁護士、司法書士などの専門家に戸籍収集を代行してもらうのも一つの手です、
7.戸籍の読み解きが難しいと感じたら?弁護士に相談するメリット
明治・大正期など非常に古い形式の戸籍は、手書きの旧字体や罫線が入り混じっていて、慣れないと判読が困難です。
また、被相続人の転籍歴や家族状況によって、戸籍収集の枚数や難易度は大きく異なります。
複雑化しそうな場合ほど、早めに専門家へ相談することが失敗や二度手間を防ぐコツです。
弁護士法人Nexill&Partnersでは、初回無料相談を通じて状況をヒアリングし、戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議までワンストップで対応可能です。
誤った解釈で後々手続きをやり直すリスクを避けるためにも、専門知識を有する弁護士にサポートを依頼して、スムーズかつ確実な相続手続きを目指しましょう。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。