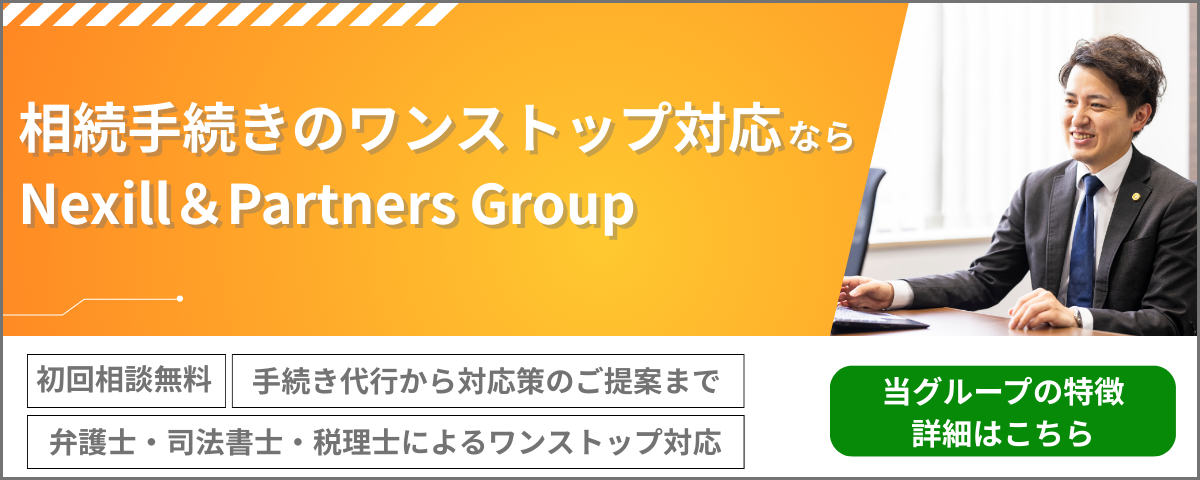相続が発生したとき、「そもそも誰が相続人になるのか分からない」「疎遠になっていた親族がいるけど、調べる方法が分からない」といった悩みを抱える方は少なくありません。相続手続きをスムーズに進めるためには、まず相続人を確定する「相続人調査」が欠かせませんが、その調査を誰に依頼するのがベストなのか分からずに戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、弁護士・司法書士・行政書士の士業ごとの特徴や対応範囲の違い、メリット・デメリットを分かりやすく整理していますので、相続人調査を依頼する際の判断材料にされてみてください。
1. 相続人調査とは?基本的な目的とタイミング
相続手続を進める上で、まず確認しなければならないのが「誰が相続人か」という点です。
この相続人の範囲を明確にするために行うのが「相続人調査」です。相続人が一人しかいないと思っていたが実は兄弟姉妹もいた、前妻との間に子どもがいた、など、戸籍を辿ることで初めて明らかになるケースも少なくありません。
相続人を正確に確定しないまま手続きを進めると、後から以下のような問題に発展する可能性があります。
・ 遺産分割協議が無効になる可能性
遺産分割協議は、法定相続人全員が関与している必要があります。1人でも相続人が抜けていた場合、その協議自体が無効と判断されることがあり、せっかく合意した内容も白紙に戻ることになります。
・ 手続のやり直しや相続人との関係悪化
後から「実は別の相続人がいた」と判明した場合、その人との間で新たに協議を行う必要があります。既に分割が終わっていたとしても、再協議を求められ、感情的な対立が生まれるケースも少なくありません。
・ 手続が進まなくなるリスク
相続登記や預貯金の名義変更、さらには相続税の申告など、あらゆる手続において相続人の確定は前提となるため、相続人が不明な状態では手続きを進めることができません。
このように、相続人調査は「いつか誰かがやればいい」というものではなく、早期に正確な調査を行う必要があります。
「誰が相続人なのか」がはっきりしない状態では、相続手続を進めることができないため、相続が発生したらまずは相続人の確定に着手しましょう。
2. なぜ相続人調査は「誰に頼むか」で迷ってしまうのか?
相続人調査をしようと思ったとき、多くの方が最初に直面するのが「誰に頼めばいいのか分からない」という問題です。これは決して珍しいことではなく、いくつかの理由によって、専門家の選択が難しくなっているのです。
まず、弁護士・司法書士・行政書士という3つの士業は、いずれも相続に関する業務を扱っており、「戸籍を集めてくれる」「書類を整えてくれる」など、やってくれる業務の内容が似ているため、その違いが非常に分かりづらくなっています。
加えて、「相続人調査の先にどんな手続きが必要になるのか(登記・税務・紛争対応など)」を具体的にイメージできていない状態だと、「とりあえず調査だけを安く済ませたい」という気持ちが先行しがちです。
しかし、調査後に登記や調停、申告が必要になった場合、「最初から一貫対応できるところに頼んでおけばよかった」と後悔するケースもあります。
ご自身の状況や調査の後に必要になる手続の種類によって、相続人調査を誰に依頼するのがよいかというのは変わってきますので、ここからは、代表的な3つの士業(弁護士・司法書士・行政書士)ごとに、対応できる範囲やメリット・デメリットを具体的に見ていきましょう。
3. 弁護士に相続人調査を依頼する場合
3-1. 対応できる範囲
弁護士は、調停・訴訟の代理人業務も含めて相続全体に関するあらゆる手続に対応できる士業です。相続人調査もその一環として行うことが可能であり、特に以下のようなケースで強みを発揮します。
- 家族関係が複雑な場合(婚外子や養子縁組があるなど)
- 相続人の一部が所在不明
- 相続人間で紛争が起こる可能性がある
相続人調査は戸籍の収集にとどまらず、法律的な判断が必要な場面(代襲相続の有無や認知の効力など)においても、正確な法的助言が可能です。
3-2. 弁護士に依頼するメリットとデメリット
・他の手続との一貫性がある
遺産分割協議がまとまらない、感情的な対立があるなどの場合でも、代理人として交渉や調停・訴訟への対応が可能です。調査結果をもとに、遺産分割協議書の作成や遺留分対応、相続放棄手続などをスムーズに引き継ぐことができます。
相続人同士に対立の可能性がある場合や、連絡が取れない相続人がいる場合も、後々の交渉や裁判手続きまで見据えて対応できる点は弁護士ならではの強みです。
・費用が比較的高額になりやすい
一方で、弁護士は費用が高額になることもあり、「戸籍の取り寄せだけをお願いしたい」といったシンプルな依頼には向かない場合もあります。基本的には、相続全体をトータルでサポートする中で相続人調査も担うというような場合が多いです。
相続の状況が複雑である、親族間で揉めそうでその後の交渉や裁判手続が必要になる可能性が見込まれるというような場合であれば、最初から弁護士に依頼することで、安心して手続を進められるでしょう。
4. 司法書士に相続人調査を依頼する場合
4-1. 対応できる範囲
司法書士は、不動産登記を専門とする士業であり、相続登記と一体的に相続人調査を含む戸籍の取得や相続関係説明図の作成に対応しています。
特に以下のようなケースでは、司法書士の関与が効果的です。
- 相続財産に不動産が含まれており、名義変更が必要な場合
- 相続人間で争いがなく、比較的シンプルな相続案件である場合
4-2. 司法書士に依頼するメリットとデメリット
・相続登記手続きと一体で依頼できる
司法書士に相続人調査を依頼する最大のメリットは、調査結果をそのまま使って登記申請まで一貫して任せられる点です。不動産の名義変更を行う場合、相続関係説明図の作成から相続登記までスムーズに対応できます。
・代理人業務は行えない
一方で、司法書士は代理人として交渉や調停・訴訟に関与することはできません。
相続調査を行い、いざ相続登記となった段階で相続人間で紛争トラブルが発生した場合でも、司法書士は間に立っての交渉などはできないため、弁護士に相談をする必要があります。
相続人同士の関係が円満で、主に不動産登記に関する手続きを進めたい場合には、司法書士への依頼が適しています。
5. 行政書士に相続人調査を依頼する場合
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や戸籍の収集代行、相続関係説明図の作成など相続人調査に必要な書類面のサポートを得意とする士業です。
対応できるのは主に以下のような場面です。
- 相続人が少なく、家族構成が単純なケース
- 書類収集と書面作成に特化した業務だけを依頼したい場合
- 相続手続の初期段階で、とりあえず戸籍収集を進めたい場合
5-2. 行政書士に依頼するメリットとデメリット
・費用を抑えて書類取得を依頼できる
行政書士に相続人調査を依頼する最大の利点は、費用が比較的安価であることと、戸籍の取り寄せなど定型的な作業を効率的に代行してもらえることです。
相続人間にトラブルの兆しがなく、相続登記や申告の見込みもない場合には、手軽に相談できる選択肢となります。
・対応範囲が限定的で、手続の分岐に弱い
一方で、行政書士は不動産登記の申請代理、さらには代理人として交渉や調停・訴訟を行うことはできません。
結果として、手続の途中で対応範囲を超える問題が発生した場合には、別の専門家を探す手間が発生し、二度手間になるリスクもあります。
6. 士業別まとめ:どの専門家に頼むべきかをケース別に比較
弁護士・司法書士・行政書士と、それぞれの士業には対応できる範囲と強み・弱みがあるため、「誰に頼むべきか」というのは相続の状況によって大きく異なります。
以下、よくあるケースごとに、誰に相談をするのが適しているのかを挙げていますので、ご自身の状況に近いものを参考にされてください。
6-1. 争いのないシンプルな相続→ 行政書士または司法書士
相続人が配偶者と子のみといった、法定相続人が明確なケースでは、行政書士や司法書士への依頼でも十分対応可能です。
書類の取得・整理・説明図の作成など、相続人調査を含めた事務作業が主な業務であれば、コストを抑えながらスムーズに進めることができます。
ただし、相続財産に不動産が含まれている場合は、登記手続を前提として司法書士に依頼しておくと、その後の手続きも一貫して任せられます。
6-2. 不動産が絡む → 司法書士または弁護士
不動産が遺産に含まれる場合、相続登記が必要です。
このとき相続人調査と登記申請をセットで対応してくれる司法書士は非常に頼りになります。
ただし、相続人間で不動産の評価や分割方法をめぐる争いが生じる可能性がある場合には、弁護士による法的アドバイスや代理交渉が必要になる場面も出てきます。
不動産の名義変更だけでなく、権利関係にトラブルの兆しがある場合は弁護士に依頼する方が安心です。
6-3. 相続人間に対立がある/音信不通の人がいる → 弁護士
相続人の中に連絡が取れない人がいる、あるいは感情的な対立があるといったケースでは、弁護士の出番です。
相続人調査だけでなく、遺産分割協議の代理交渉、調停・訴訟、不在者財産管理人の選任、失踪宣告などを一貫して対応可能なのは弁護士だけです。
単なる「調査」では終わらない可能性があると感じた場合は、最初から弁護士に相談しておくことが、後の手続全体の円滑化にもつながります。
6-4. 相続放棄の可能性がある場合 → 弁護士
相続人調査を進めていく中で、相続人の中に「相続放棄を検討している人」が出てくることがあります。この場合も、弁護士であれば相続人調査に続いて相続放棄の手続まで一貫して代理可能ですので、相続放棄の可能性が少しでも見込まれる場合は、調査から手続きまでをワンストップでカバーできる弁護士に最初から依頼しておく方が安全です。
6-5. 家族構成が複雑な場合 → 弁護士
前婚の子、養子、認知された非嫡出子など、家族構成が複雑な場合、相続人の範囲や相続分の確定には、単なる戸籍の収集にとどまらない法的判断が必要となります。
加えて、こうした家庭事情がある場合、その後の相続手続も遺産分割協議が難航したり、紛争に発展したりする可能性が比較的高いのが現実です。
たとえば、他の相続人が存在を知らなかった相続人が突然現れると、感情的な対立が生まれやすく、協議が進まなくなることも少なくありません。
このような状況では、最初に相続人調査を行う段階から、その後の交渉・調停・訴訟まで一気に対応できる弁護士に依頼しておく方が、スムーズかつリスクの少ない進行が可能です。
相続人調査の段階で「家族関係が複雑そう」「将来的に揉めそう」と感じたら、法的リスクを最小限に抑える意味でも、弁護士への相談を強くおすすめします。
6-6. 会社経営者や地主など事業承継・相続税を考慮すべきケース → 税理士と弁護士
相続人調査は、すべての相続手続きの出発点ですが、財産の規模や種類によっては、その先の対応がはるかに重要になります。
たとえば、会社経営者が亡くなった場合、誰が株式を承継するかによって、会社の経営権や安定性に直結する問題が生じます。
また、地主や資産家など不動産を多数所有している方の場合には、相続税の負担が大きくなりやすく、節税や納税対策まで含めた検討が不可欠です。
このようなケースでは、調査の正確さに加えて、税務知識や事業承継に関する法的視点が求められますので、弁護士に依頼の上で、並行して税理士にも相談をしながら進めることが重要です。
弁護士・税理士が連携している弁護士事務所も増えていますので、そういったワンストップ型の事務所に依頼すると、税務面を含めた相続手続が一か所で可能になるのでそこは大きなメリットといえます。
7. 当事務所のワンストップ体制による相続人調査の強み
7-1. 弁護士・司法書士・行政書士が連携することで全方位対応が可能
当事務所では、弁護士法人のほかに、司法書士法人・税理士法人が一体となって運営されており、相続人調査を起点に、相続全体を見据えた提案・対応が可能です。
「相続登記までそのまま実施したい」「相続財産の額が大きく相続税申告が必要だ」「不動産の共有状態を避けたい」といった派生的な課題にも、それぞれの専門家が連携して対応できるため、安心してお任せいただけます。
また、事業承継の際の相続方法や、相続税まで考慮した遺産分割方法の検討など、相続に付随する税務面まで同時にカバーができますので、法的な面だけでなく周辺領域まで見渡した最適な相続手続が可能です。
「どの士業に頼めばいいか分からない」「争いになるかもしれない」「そもそも何から始めていいか分からない」という方は、まずは一度ご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。