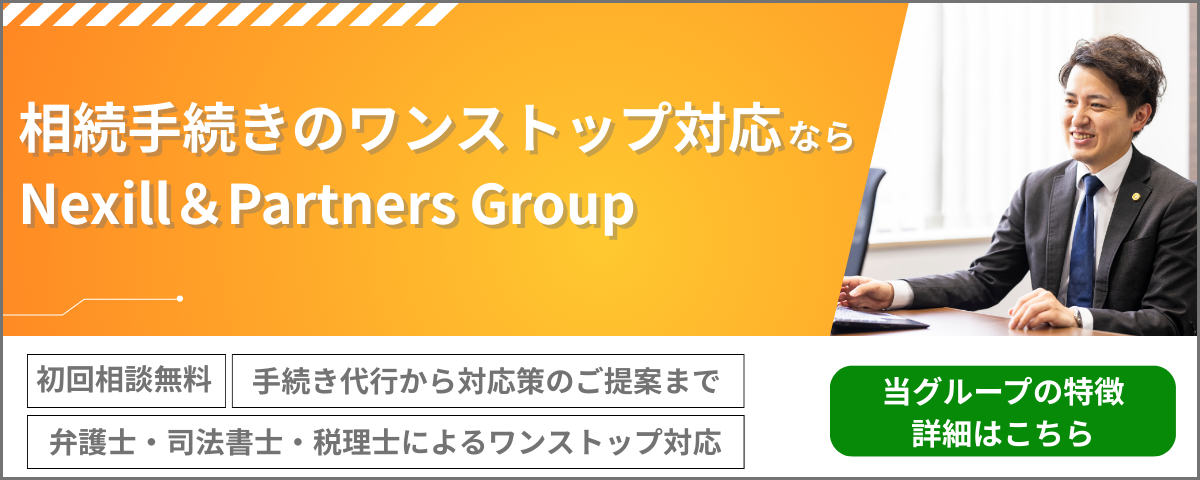2024年4月から相続登記が義務化されたことにより、相続を知った日から3年以内に登記をしなければ、最大10万円の過料が科される可能性があります。
これはすでに相続をしているものの現時点で相続登記ができていない不動産についても義務化の対象となりますので、注意が必要です。
本記事では、弁護士の視点から、相続登記と遺産分割の関係、放置していた場合に起こりうるリスク、不動産の状態に応じた注意点などを具体的に解説します。
1. 相続登記の基礎知識
まず、そもそも「相続登記」とは何でしょうか?簡単にいえば、不動産の名義を故人から相続人に移す手続きのことです。法律的には「所有権移転登記」と呼ばれます。
これまでは、相続登記に期限はなく、長年放置されることも珍しくありませんでした。しかしこの放置が原因で、以下のような問題が発生していました。
相続登記が放置されたことでの問題点
- 相続人が増えて話し合いが難航する
- 不動産の売却や担保設定ができない
- 遺産分割協議が複雑化する
このような背景を受けて、2024年4月からは法改正により、相続登記の申請が義務化されました。相続人は、「自己が相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を実施しなければならず、これに違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。
これにより、相続登記はいつかやればいいと放置することはできなくなりましたので、遺産分割が完了したら、速やかに登記手続を行いましょう。
2. 遺産分割協議と登記の関係
相続登記を行うには、「誰がどの不動産を相続するのか」が決まっていなければなりません。このため、登記を申請する前には、遺産分割協議が済んでいることが原則です。
遺産分割協議とは、相続人全員で集まり、不動産や預貯金、株式などの遺産をどのように分けるかを話し合い、合意する手続きです。合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて登記申請を行うことになります。
なお、遺産分割協議がまとまらず、登記申請の期限内に合意ができないような場合は、特定の相続人に名義を移すのではなく、相続人全員の法定相続分に応じて一時的に持分移転登記を行う(相続人全員の共有名義で登記を行う)という手段をとることもできますが、不動産を共有名義にすることでのリスクもあり、実務上はあまりお勧めできません。
暫定措置として法定相続分での登記を行った場合でも、遺産分割協議が完了し、特定の相続人が不動産を取得することで合意した場合は後に再度登記をやり直す必要がありますし、共有名義の状態で処分・売却をしなければならなくなった場合は手間や費用が増えるリスクもあります。
そのため、できる限り早期に協議を整えたうえで、誰がどの不動産を取得するかを正式に確定させて1回で登記を完了させることが望ましいといえます。
3. 相続登記をせずに放置している不動産がある場合はどうすべきか?
「親が亡くなって10年以上経つが、家の名義はそのまま」「誰が住んでいるかははっきりしているけれど、相続手続はしていない」——こうした状態の不動産は、決して珍しくありません。
しかし、相続登記を放置していると次のような問題が発生します。
相続登記をしないことでの問題点
- 不動産を共有している相続人が亡くなり、さらに新たな相続が発生する(数次相続が発生する)
- 相続人の数が増えて協議がまとまりにくくなる
- 売却・贈与・担保設定ができず、不動産を“動かせない”状態になる
- 相続登記義務違反として、過料が科される可能性がある(2024年以降)
仮に不動産を誰か一人が単独で使用していたとしても、それだけで「その人が単独で取得した」ことにはなりません。
登記簿の名義が被相続人(故人)のままでも、相続の開始と同時に、不動産の所有権は相続人に法定相続分に応じて承継されるため、登記をしていなくても、法律上は相続人が共有でその不動産を所有している状態になります。
ただし、登記がされていないため第三者に対抗することができず、法的手続きや不動産取引においては「名義が被相続人のまま」であることが大きな支障となります。
この共有状態を解消するには、相続人全員の合意の下で不動産を誰が取得するかを決める必要があります。
このように長期間放置されている不動産の登記については、
1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで集める
2. 相続人を全員確定する
3. 遺産分割協議を行い、登記に必要な書類を整える
というステップで手続を進めていきます。遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判などの法的手続きに進むことも検討されます。
早めに対応すれば相続人も比較的少なく、協議も成立しやすいですが、放置するほど関係者が増え、登記も困難になります。
4. 昔の相続を何もしていない場合(登記も遺産分割も未了)
「祖父の名義のままになっている土地がある」「相続人は誰かもはっきりしない」——このように、何十年も前の相続を手つかずで放置しているケースも非常に多く存在します。
このようなケースでは、すでに
- 相続人のうち何人かが亡くなっていて
- その子や孫が代襲相続人として登場して
- 関係者が20人、30人以上になる
といった状況に発展していることも珍しくありません。
こうなると、次のようなリスクや追加での手続きが発生します。
- 相続人の中に行方不明者がいると、不在者財産管理人の選任が必要
- 相続人の中に未成年者がいれば特別代理人の選任が必要
- 連絡の取れない相続人が一人でもいれば協議が進まない
- 合意形成に時間がかかり、その間の不動産の活用や処分ができない
また、こうしたケースでは「相続人同士が全く面識がない」という状況も多く、合意形成そのものが困難なこともあります。こうした状況では、弁護士が入って代理人として関係者間の調整を行うことで、初めて前に進められることも多々あります。
場合によっては、家庭裁判所の調停・審判手続きに持ち込むことが現実的な解決ルートになるケースもあります。長年放置してしまった相続は、専門家の関与なしには解決困難な局面に陥っている可能性が高いため、早期にご相談いただくことをおすすめします。
5. 不動産の状況に応じた登記上の注意点
相続する不動産の“状態”によっても、登記の進め方や注意点は大きく変わってきます。ここでは、弁護士として現場でよく遭遇する典型的な例をご紹介します。
5-1.未登記建物を相続したケース
被相続人が建てた家が法務局に建物として登記されておらず、「未登記建物」のまま相続が発生していることがあります。この場合、相続登記を行う前に、建物の表題登記(建物の存在を新規に登記する手続)を先に済ませる必要があります。これは土地家屋調査士も関与の上で進める手続となり、表題登記を行った後で名義変更を行うような流れとなります。
5-2. すでに存在しない建物の登記が残っていたケース
逆に、実際には取り壊されて現存しない建物の登記手続が放置されているケースもあります。これは、建物を解体した際に「滅失登記」がされていなかったことによるものです。この場合は、土地の相続登記に先立って、滅失登記を行っておくのが実務上は望ましい対応です。滅失登記の申請には、原則として登記名義人本人が行うか、名義人が死亡している場合は、相続人などの利害関係人が手続きを行うことができます。
なお、滅失登記をしなくても土地の相続登記自体は可能な場合がありますが、建物の存在に関する情報が誤って残ることは、将来的なトラブルの火種となる可能性がありますのでできるだけ現状に即した状態にしておくのが望ましいでしょう。
5-3. 地目と現況が異なる土地のケース
相続した土地の登記簿上の「地目(ちもく)」と、実際の使われ方が一致していないケースは、意外とよくあります。例えば、登記簿では「畑」となっていても、実際にはそこに住宅が建っており、長年「宅地」として使用されているような場合です。
このような場合、法律上はすぐに罰則があるわけではありませんが、登記簿の地目と現況が異なる状態を放置しておくと、実務上いくつかの問題が生じることがあります。
地目と現況が異なる場合の主な注意点
売却や相続の際に説明が必要になる
買主や相続人から「登記では畑になっているのに、本当に宅地として使えるのか?」といった懸念が出ることがあり、契約・分割の調整が難航する可能性があります。
不動産の評価にズレが出る可能性
土地の固定資産税評価や相続税評価において、地目が「畑」と「宅地」では評価基準が異なります。現況が宅地なのに評価が農地のままになっていると、特例適用の可否や評価額算出に支障が出ることもあります。
将来的な処分・開発時に行政手続が煩雑になる
自治体によっては、登記簿上の地目に基づいて許可・届出が必要となる場合があります。たとえば、農地であれば農地法の制限がかかることもあるため、転用ができないケースもあります。
このような事情から、地目と現況が異なる土地については、できるだけ早い段階で「地目変更登記」を行っておくことが望ましいといえます。特に相続後の名義変更を機に、地目についてもあわせて見直すことで、将来的な売却や節税対策、処分の選択肢が広がります。
6. 遺産分割協議が長引きそうなときの対応策
「不動産を誰が取得するかでもめている」「相続人の一人が話し合いに応じない」——このように、遺産分割協議が長引くことは珍しくありません。しかし、2024年の法改正以降は、相続登記が義務化され、3年以内に申請しなければならないことになりました。これにより、協議がまとまるまで「登記を保留する」という選択は、現実的ではなくなってきています。
そのため、分割協議が長期化しそうな場合には、以下のような対応が検討されます。
法定相続分による共有名義での登記
とりあえず相続人全員の法定持分で登記しておく方法です。これにより登記義務を果たすことはできますが、名義が共有状態になるため、後の処分・利用には不便が残ります。共有名義にすることでのリスクも大きいため、実務上は積極的には採用しない対応です。
「相続人申告登記」による義務履行
相続登記の義務化に伴い、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易的に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、新しく設けられた制度です。遺産分割協議が未了の状態でも、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内に法務局に申請することで、義務違反にはなりません。ただし、これは登記簿に「この人が相続人です」と記録を残すだけの制度であり、実際に相続登記を行うものではありません。そのため、第三者への権利対抗や不動産の処分等は正式な相続登記後にしか実施できません。あくまで、遺産分割が終わるまでの暫定的な対応にとどまる点に注意が必要です。
調停や審判への早期移行も視野に入れる
相続人の一部が協議に応じない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、協議が動く可能性もあります。最終的には法的に分割内容を確定させることができますので、当事者間での協議に限界がある場合は弁護士が代理人として裁判手続きへ移行することも視野に入れる必要があります。
どのような対応をすべきかは、個々の状況に応じて変わってきますので、まずは弁護士に相談の上で進め方を決めるのが望ましいでしょう。
7. 相続登記に関連するよくある質問(FAQ)
Q1:登記をしていない不動産にも固定資産税はかかりますか?
A:はい、登記がされていない場合でも、固定資産税は課税されます。課税対象は「登記名義人」ではなく、市町村が把握する現実の所有者情報(名寄帳)に基づいて課税されることが多いためです。そのため、「固定資産税を払っている=正式な所有者である」とは限りません。税金を払っていても、法的には名義変更されていなければ、不動産の処分や担保設定をする権限はありません。
Q2:遺産分割協議がまとまっていない間に、不動産を相続人の1人が単独で使用することは可能ですか?
A:可能ではありますが、注意が必要です。不動産は相続開始と同時に相続人全員の共有状態となるため、1人が単独で住み続けたり、使用収益を得たりしている場合には、他の相続人に対して使用料相当額の支払い義務が発生することがあります。無断使用が後から紛争の火種となることもあるため、共有状態であることを踏まえ、あらかじめ相続人間で合意書を交わしておくのが望ましいです。
Q3:相続登記が義務化されたのは、2024年4月1日以降の相続だけが対象ですか?
A:いいえ、それ以前に発生していた相続にも遡って適用されます。ただし、2024年4月1日時点で相続が発生していた場合は、そこから3年間の猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに登記申請を行えば義務違反にはなりません。なお、今後発生する相続については、相続を「知った日から3年以内」に登記を申請する必要があります。
当事務所では、弁護士だけでなく、司法書士・税理士が在籍のうえでの「ワンストップ対応」を行っており、次のような体制でサポートしております:
弁護士
遺産分割協議の設計、交渉、調停・審判対応
司法書士
相続登記の書類作成と申請手続全般
税理士
相続税申告や生前贈与、特例の活用などの税務設計
この体制により、お客様は「どこに何を頼めばいいか分からない」といったストレスなく、一元的にすべての相続手続きを進めることができます。
相続に関してお悩みのある方、相続登記や協議の進め方に不安がある方は、ぜひ早めにご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。