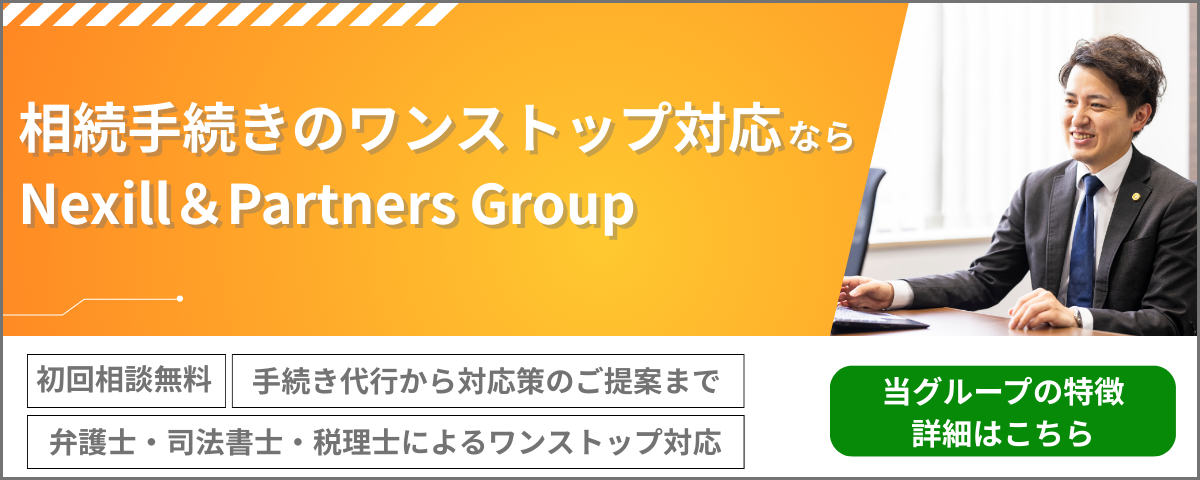「親が物忘れを訴え始めたが、遺言書を作っておきたい」「軽度認知症と診断されたが将来の相続争いを避けたい」――こうした相談が年々増えています。結論から言えば、認知症=遺言無効ではありません。遺言作成時に必要な遺言能力が維持されていれば有効と認められる余地は十分あります。本コラムでは、遺言能力の判断基準と認知機能に不安がある場合の遺言作成のポイントについて弁護士が解説します。
1.認知症と遺言能力の基礎知識
1-1 「認知症=遺言無効」とは限らない
遺言書を残せる人というのは民法で定義が決まっていて、以下両方に当てはまる人は遺言を残すことができるとされています。
- 15歳に達した者
- 遺言をする時に遺言能力を有すること
ここでいう能力とは、①自分の財産の種類と価値、②推定相続人・受遺者との関係、③遺贈・分配による結果を理解し、合理的に判断できることです。したがって「認知症と診断されている=直ちに遺言の能力がない」ということではありません。認知症の症状が極めて軽度で遺言書作成当日時点の判断能力および意思表示が明確であれば、その遺言の有効性は十分認められる余地があります。
一方で、遺言書作成時点で意思疎通が困難である、今日の日付や今いる場所が答えられない・聞かれた質問に一貫した回答ができないなど認知症が重度で判断能力がないような場合は、遺言書の作成ができない(作成しても無効になる可能性が高い)といえます。
1-2 遺言能力があるかどうかはどこで判断するのか?
遺言書を作成する際にご本人に遺言能力があるかどうかを判断するには、ご本人の状況や病院での検査結果などを含めて総合的に判断します。
以下、大まかな判断の基準について詳しく説明をします。
面談でのヒアリング(弁護士・公証人)
遺言書を作るにあたって、弁護士がご本人と対面し、
- ご自身の保有資産(種類・概算額)を説明できるか
- 相続人や受遺者を把握し、自分との関係性を理解できているか
- 遺言によって誰がどの財産を得るかを理解し、遺言作成の意思表示ができるか
という点をご本人とお話しながら確認します。ここで大きな齟齬がなければ遺言書作成に進むに足りる理解力があると判断することが多いです。
公正証書遺言で遺言書を作成する場合は、公証役場で実際に遺言書を作成する段階で、公証人が遺言書を作成するに足りる能力があるかどうかを判断します。
認知能力を示す書類(長谷川式スケール、医師の診断書など)
面談時に軽度の物忘れが疑われるような場合は、病院で認知能力を図るための検査を行い、ご本人の認知程度を調べます。
代表的なものとしては、長谷川式認知スケールがあげられます。
30点満点で、20点以上であれば認知症の疑いはほぼなく、遺言能力が認められる可能性が高いです。
20点以下の場合は点数に応じて軽度~重度の認知機能の低下が疑われ、10点以下であれば遺言能力はほぼ認められません。
なお、長谷川式スケールの点数のみですべての判断がされるというわけではなく、ご本人の状況や遺言の内容など総合的に見たうえで遺言能力の有無が決まります。
点数が20点以下の場合でも、遺言書の作成ができるケースもありますので、一度弁護士にご相談ください。
2. 認知機能に不安が残る際に遺言書を作成する際のポイント
・1日でも早く作成に着手する
認知機能の低下に不安がある場合は、症状が進んでしまう前にできるだけ早く遺言書を作成することが1つのポイントです。
認知症を原因とするものだけでなく、服薬などの副作用で一時的に判断能力が低下するような場合もありますので、ご本人の状態が安定している時期に作成を完了できると望ましいでしょう。
・公正証書遺言で作成をする
公正証書遺言は、公証役場で公証人の立会いのもとで遺言書を作成するため、「判断能力を第三者がチェックした」という客観証拠を残しやすいです。
認知機能に少しでも不安がある場合は、公正証書で遺言書を作っておくほうがリスク回避の観点からも安心です。(なお、公正証書遺言で作成しておけば、後に遺言の有効性を争われた際でも必ず遺言書が有効になるというわけではないという点には留意が必要です。)
FAQ:認知症リスク下で遺言書を作るときのよくある質問
Q.「軽度認知症」と診断されています。遺言書を作っても将来無効にされませんか?
A. 医療機関で“認知症”と診断されても直ちに遺言能力を失うわけではありません。重視されるのは、「遺言書作成時に自己の財産・相続人関係・分配結果を合理的に判断できる状態か」という実質的能力になるため、軽度の認知症と診断されていても、遺言能力が十分にあったという客観的な根拠資料(本人の受け答えの録音、弁護士や公証人との面談の記録など)を残しておくことで、遺言の無効リスクは一定程度防ぐことができます。
Q. 遺言書を作れるかどうかは長谷川式スケールの点数が基準になりますか?何点なら安全でしょうか?
A. 長谷川式スケールであれば20点が軽度認知症の目安とされており、その値を下回ると認知症を理由に遺言能力がないとされるリスクは高まりますが、点数はあくまで補助的指標で、裁判所は症状の質(見当識・短期記憶・理解力)を総合評価します。たとえば点数が18点であっても、弁護士や公証人の質問に適切に回答し、資産内容や遺言内容を自ら説明できる状況だったら有効と判断されることもあれば、逆に点数が正常域でも作成当日に適切な受け答えができない、認知機能に問題がある様子が見られたら無効と判断されることもあります。
ご本人の状況次第で遺言能力の有効無効は変わりますので、一概に点数だけで判断はできないというのが実情です。
Q. 公正証書遺言の立会人を家族に頼むと無効を主張されやすいと聞きました。本当ですか?
A. 推定相続人や受遺者は公正証書遺言の証人(立会人)になることができません。上記に当てはまらない親族であれば証人になることはできますが、後に遺言無効の争いになった際、「誘導・圧力」があったのではという主張をされることがごくまれにあります。
不安な場合は、弁護士等の第三者を証人として作成することを検討してもよいでしょう。
Q. 遺言作成後に認知症が進行したら、その遺言は取り消されるのでしょうか?
A. 遺言は「作成当時に有効」なら、その後に能力を失っても効力は維持されます。そのため、遺言作成後に認知症が進行してしまったとしても、作成済みの遺言が取り消されることはありません。
ただし、後で内容を変更・撤回するには改めて遺言能力が必要になるため、その場合は認知症の度合いによっては書き換えや撤回ができないという可能性はあります。
認知症=直ちに遺言が無効となるわけではありません。遺言書作成の前後の意思能力・判断能力が十分にあれば、有効な遺言書の作成は可能です。
ただし、認知症が進んでしまい完全に遺言能力を喪失してしまった後は作成ができなくなってしまうため、認知機能に不安がある場合はできるだけ早めに遺言書作成に着手されることをお勧めします。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。