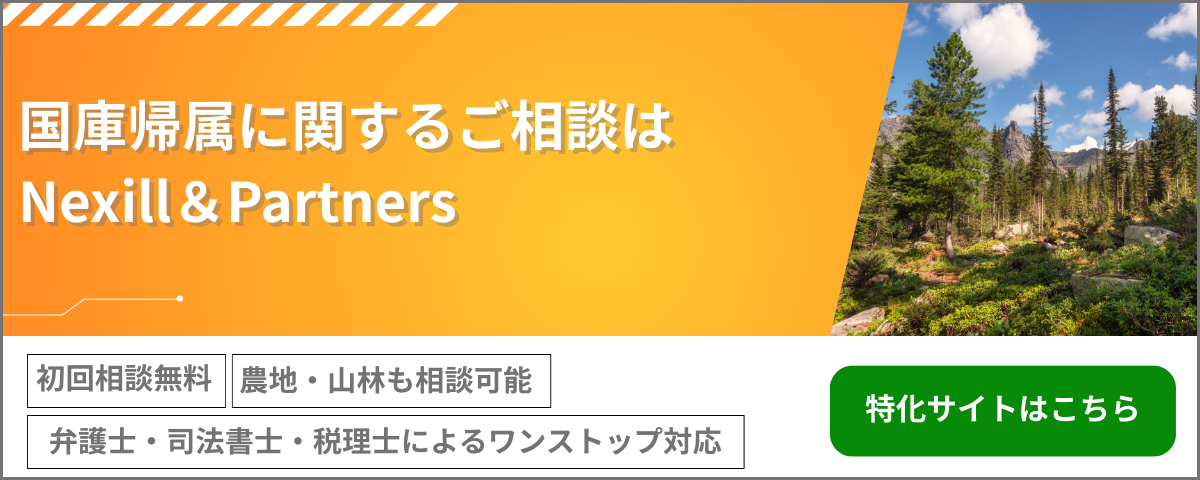相続した山林や農地を「使い道もないのに所有しているのは負担だ」と感じる方は、近年創設された相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみるとよいかもしれません。
山林や農地を相続して管理に困っている場合、この制度を活用して国庫へ帰属(引き取ってもらう)できるケースがあります。
ただし、境界や管理の状況など厳格な要件が定められているため、「自分の土地が本当に対象になるのかわからない」と悩む方も少なくありません。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の基本概要や申請手続きの流れ、承認申請が却下される場合の注意点、さらには農地・山林の処分や利用方法に関するポイントをわかりやすく解説します。
不要な土地を放置して固定資産税などの負担を抱え続ける前に、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身のケースで活用ができるのかを確認してみてください。
1.相続土地国庫帰属制度とは?山林・農地も対象になるのか
相続や遺贈によって取得した土地(山林や農地など)を国庫に帰属させることで、所有権を放棄できる仕組みが相続土地国庫帰属制度です。
令和5年4月以降に本格的にスタートし、「誰も使わない山林を持て余している」「農地を管理するのが大変だ」といった声を受けて注目されています。
ただし、利用できる土地には厳しい要件があり、申請をしても承認されないケースも少なくありません。
加えて、土壌汚染や崖地が含まれているなど、管理に負担がかかる状態だと却下される可能性が高いため、まずは制度の概要を正しく把握し、自分の土地が対象になるかどうかを検討しましょう。
2.承認申請ができる「所有者」と要件のポイント
2-1.対象となる相続人・遺贈を受けた人
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人または遺贈を受けた所有者です。
具体的には、以下のような方が該当します。
- 親が亡くなり、農地や山林を相続した人
- 遺言書により特定の土地を遺贈された人
所有権を持つ人が複数いる場合は、共有者全員の合意を得たうえで承認申請を行わなければなりません。
2-2.制度を利用できる土地の条件
承認申請が認められるには、法務局の審査で要件を満たしていることが明らかになる必要があります。
代表的な要件は以下のとおりです。
- 境界が確定しており、隣接する土地との争いがないこと
- 崖や段差など管理に多大な負担がかかる地形でないこと
- 担保権や所有権に係る争いが発生していないこと
これらに加え、法務局が「国庫に帰属させても問題ない」と判断できるだけの資料(地図や測量図等)を求められる場合があります。
費用や手間がかかるため、十分な事前調査が不可欠です。
2-3.農地・山林ならではの留意点
山林や農地は境界が不明瞭なケースが多く、実際に測量や地番の特定を行ってみると、隣接地との境が曖昧になっていることが少なくありません。
加えて、農地の場合は農地法の制限により転用許可が必要な場合もあるため、法務省だけでなく、地方自治体や農業委員会など複数の機関への確認が必要となるケースもあります。
3.相続土地国庫帰属制度が承認されないケース
3-1.却下事由と不承認事由の違い
制度上、「却下事由」と「不承認事由」は別個のものとして扱われます。
却下事由とは、申請を行う資格自体がない(相続人・遺贈人に該当しない等)場合などを指し、書類段階で審査を通過できないことが多いです。
一方、不承認事由は、要件を満たさない(境界が不明、管理上の負担が大きい等)場合を指し、法務局が審査の末に承認しないと判断するパターンです。
3-2.境界が明らかでない場合
山林や農地の多くは、昔から放置され、隣の土地との境がはっきりせず、境界トラブルが発生しやすいのが実情です。
もし境界確定ができず、隣接地との境界争いが起こる可能性があるとみなされると、審査の時点で承認を却下されるでしょう。
3-3.管理や利用に多大な負担がかかる場合
法務局は、土地が崖地や有害物質などの問題を抱えているかどうかもチェックします。
山林や農地でも、急斜面や土壌汚染がある場合には国による取得が難しく、許可されないケースが多いです。
不要だからといって放置していた土地の状態が悪化していると、実質的に制度の利用が不可能になることに注意しましょう。
4.審査の流れと必要な書類—法務局への申請方法
4-1.承認申請にかかる手数料と負担金
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料と負担金を納付する必要があります。
審査手数料は1筆あたりいくら、という形で算定され、土地の面積や状況によって金額が増減するケースも。
負担金については、管理費用の一部を所有者が負担するという考えに基づき、面積×一定額が設定されています。
具体的には以下の通りです。
【負担金算定の具体例】
| 宅地 | 面積にかかわらず20万円 ただし、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じ算定 |
|---|---|
| 田・畑 | 面積にかかわらず20万円 ただし、以下の田・畑については、面積に応じ算定 ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地 イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地 ウ 土地改良事業等(土地改良事業又はこれに準ずる事業であって帰属法施行規則第15条に規定する事業)の施行区域内の農地 |
| 森林 | 面積に応じ算定 |
| その他 | 面積にかかわらず20万円 |
【算定式】
⑴ 上記宅地の算定式
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 50㎡以下 | 国庫帰属地の面積×4,070(円/㎡)+208,000円 |
| 50㎡超100㎡以下 | 国庫帰属地の面積×2,720(円/㎡)+276,000円 |
| 100㎡超200㎡以下 | 国庫帰属地の面積×2,450(円/㎡)+303,000円 |
| 200㎡超400㎡以下 | 国庫帰属地の面積×2,250(円/㎡)+343,000円 |
| 400㎡超800㎡以下 | 国庫帰属地の面積×2,110(円/㎡)+399,000円 |
| 800㎡超 | 国庫帰属地の面積×2,010(円/㎡)+479,000円 |
⑵ 上記田・畑の算定式
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 250㎡以下 | 国庫帰属地の面積×1,210(円/㎡)+208,000円 |
| 250㎡超500㎡以下 | 国庫帰属地の面積×850(円/㎡)+298,000円 |
| 500㎡超1,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×810(円/㎡)+318,000円 |
| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×740(円/㎡)+388,000円 |
| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×650(円/㎡)+568,000円 |
| 4,000㎡超 | 国庫帰属地の面積×640(円/㎡)+608,000円 |
⑶ 上記森林の算定式
| 面積区分 | 負担金額 |
|---|---|
| 750㎡以下 | 国庫帰属地の面積×59(円/㎡)+210,000円 |
| 750㎡超1,500㎡以下 | 国庫帰属地の面積×24(円/㎡)+237,000円 |
| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×17(円/㎡)+248,000円 |
| 3,000㎡超6,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×12(円/㎡)+263,000円 |
| 6,000㎡超12,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積×8(円/㎡)+287,000円 |
| 12,000㎡超 | 国庫帰属地の面積×6(円/㎡)+311,000円 |
4-2.書類作成・調査のポイント
申請時には、境界が明らかであることを示す測量図や地図、所有権を証明する書類(登記簿謄本等)、相続人であることを示す戸籍関係書類など、多数の資料が必要となります。
不動産登記や土地調査の専門家と連携することでスムーズに進められますが、その分費用がかかる点は事前に把握しておきましょう。
4-3.地方(地方法務局)への提出と審査手順
書類が準備できたら、土地の所在地を管轄する地方法務局に申請書類を提出し、審査が行われます。
審査期間はケースによりますが、明らかに要件を満たしている場合でも数ヶ月以上かかることがあり、境界問題などがあればさらに長期化することもあり得ます。
5.農地・山林を手放すなら—相続土地国庫帰属制度以外の処分・利用方法
5-1.売却(不動産会社・森林組合など)
山林や農地は需要が低い場合が多く、売却が簡単ではありません。
それでも、立地や森林の資源価値、農地としての活用価値が見込まれる場合は、不動産会社や森林組合に相談してみる方法もあります。
国庫帰属制度を利用するよりも、不承認リスクがないメリットがありますが、買い手を見つけるのが難しいのが実情です。
5-2.第三者への譲渡・寄付
国や自治体以外の第三者に譲渡や寄付を検討する方法もあります。
ただし、農地の場合は農地法の許可、山林の場合でも活用計画がないと受け取ってもらえないケースが多いです。
寄付を検討する際は、受け入れ先の負担や条件を十分確認する必要があります。
5-3.相続放棄との比較検討
「どうしても管理が難しい」「制度の要件を満たせそうにない」という場合、相続放棄も一つの選択肢です。
ただし、相続放棄は土地だけでなく他の財産すべてを放棄することになるため、預貯金などのプラス資産まで手放してしまう点に注意しなければなりません。
相続税申告や遺贈との兼ね合いも踏まえ、総合的に判断することが重要です。
6.費用と負担金の内訳—実際どのくらいかかるのか
6-1.審査手数料の算定
相続土地国庫帰属制度の承認申請では、審査手数料を1筆あたりいくらで計算する仕組みがとられています。
土地が複数筆に分筆されている場合は、その筆数分の手数料がかかるため、知らずに分筆が多数あった山林などでは合計額が大きくなる可能性があります。
6-2.山林・農地の負担金が高くなるケース
傾斜のきつい山林、農地として利用価値の低い荒れ果てた土地など、管理に多大な労力や費用がかかると判断された場合には、負担金が高額になる傾向にあります。
国が所有することで発生し得るコストをある程度相続人に負担させる仕組みであるため、「思っていたより費用がかかる」ケースも少なくありません。
6-3.支払い時期と納付方法
審査を経て承認が下りた後、負担金を納付することではじめて国庫帰属が成立します。
納付が遅れると帰属手続きが進まず、期限内に支払わないと取り消し(不承認)になる場合もあるため注意が必要です。
7.相続土地国庫帰属制度を利用するメリット・デメリット
7-1.メリット—管理費の削減・将来の争い防止
固定資産税や維持管理費の負担を軽減できる
放置していた山林や農地が将来的に発生させる相続人間の争いを回避できる
他の相続人と共有の場合でも、全員の合意さえあれば一括して不要な土地を処分できる
7-2.デメリット—承認されなかった場合のリスク
手数料や測量費用などの調査・書類作成費がかかるが、不承認となれば全額ムダになり得る
境界問題など、専門家を交えても解決が難しい場合がある
審査に時間がかかるため、早急に土地を手放したい人には向かない可能性がある
7-3.農地・山林特有の注意点
農地や山林は、宅地に比べて境界があいまい・地形が複雑・法令上の許可が必要など、承認申請のハードルが高い傾向があります。
法務局の審査だけでなく、場合によっては自治体や農業委員会の判断を得る必要があるため、早めの準備・調査が肝心です。
8.【事例紹介】制度を検討したが却下されたケース
8-1.境界確定が困難で否認された
事例:Aさんは父の相続で山林を取得し、国庫へ帰属させるべく承認申請をしました。
しかし、隣接する土地との境界がどこなのか長年不明で、明確に示す測量資料もなし。
結果として法務局の審査で「境界が明らかでない」と判断され、不承認に。
Aさんは追加で測量を実施しましたが、実質的に再申請のハードルが高くなってしまいました。
8-2.農地が崖地化していたため費用が高額に
事例:Bさんは不要な農地を国庫帰属させようと考えましたが、斜面地が多く、管理に多大な費用がかかる状態でした。
法務局から「整地費用の問題がある」とされ、多額の負担金を提示されることに。
結局、Bさんは国庫帰属制度を断念し、第三者への売却を模索する道を選びました。
9.相続専門の弁護士法人Nexill&Partnersに相談するメリット
9-1.相続登記や相続放棄との併用検討が可能
不要な山林や農地を処分するには、名義変更(相続登記)や、場合によっては相続放棄も検討しなくてはならない場合があります。
当事務所は司法書士法人・税理士法人を併設しているので、これらの手続きや税務申告を含め、ワンストップで対応することが可能です。
9-2.税理士・司法書士も在籍しワンストップ対応
法務局への承認申請や書類作成には、境界確定や農地法の許可など、多方面の専門知識が必要となる場合があります。
当事務所は弁護士だけでなく、税理士・司法書士も在籍しているため、あらゆる角度から総合的にアドバイスができます。
複数の専門家を別々に探す手間やコストを大きく抑えられる点も大きな魅力です。
9-3.山林・農地の処分に関する専門的アドバイス
山林や農地は、宅地に比べて境界問題や地形的な課題が多く、国庫帰属制度を使う際には一層慎重な検討が求められます。
当事務所には、これまで数多くの不動産に関する紛争解決や相続手続きの経験がございますので、測量や境界確定の実務、農地法に関するご相談までトータルサポートが可能です。
9-4.当事務所の「相続土地国庫帰属申請サポート」サービス
当事務所では、相続土地国庫帰属制度を利用した申請サポートサービスをご提供しております。
具体的な費用の目安を掲載しておりますので、ぜひ下記のリンクよりご覧ください。
▶ [土地国庫帰属専門サイト](https://nexillpartners.jp/law/sozoku/tochi_kizoku/)
国庫帰属制度以外の選択肢との比較や、境界確定が難しいケースの対処法など、個別のご事情に応じたきめ細かなアドバイスが必要な方は、無料相談を活用して早めにご相談いただくことをおすすめします。
10.まとめ—不要な山林・農地を手放すなら早めの検討が鍵
相続土地国庫帰属制度は、使い道のない山林や農地を国へ帰属させる手段として近年注目を集めていますが、要件は非常に厳しく、境界問題や管理上の負担が発生する土地は承認申請が却下されやすいのが現実です。
実際に申請するとなれば、審査手数料や負担金など費用もかかるため、慎重な検討が必要となるでしょう。
「相続した不要な土地を放置している」「農地があっても使い道がない」といった状況を抱えているなら、まずは当事務所へご相談ください。
相続に関する専門性を生かし、法務局への承認申請や相続登記、ほかの処分方法との比較検討など、あらゆる角度からサポートいたします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。