相続税の申告は、「誰が」「どのように」行うのかを巡って、相続人間で混乱が生じやすい手続きのひとつです。
法的には各相続人がそれぞれ申告義務を負いますが、実務上は相続人のうち誰か1人が主導して進める場面も多いでしょう。
本記事では、相続税申告の主体に関する基本的な仕組みから、複数の相続人がいる場合の対応、トラブルを防ぐための方法までを税理士資格を持つ弁護士が解説します。
1. 相続税申告の基本:いつ、誰が、何をするのか
相続税申告は、相続が発生した際に「被相続人から財産を引き継いだ相続人」が行う手続きで、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税申告書を被相続人の住所地を所轄する税務署に提出し、あわせて納税も行わなければなりません。
期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生したり、特例(小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など)が適用できなくなったりするリスクがあるため、時間的な余裕は意外と少ないのが実情です。
1-1. 相続人とは誰か?法定相続人の範囲と確定方法
相続税を申告しなければならない人とは、相続人や包括受遺者(遺言で全財産を包括的に受け取るとされた人)です。
そのため、まずは法的に誰が相続人なのかを確定したうえで、相続税の申告義務者を明らかにする必要があります。
なお、遺言がある場合は、遺言に従って相続分が異なることがありますが、相続税の申告義務そのものは、財産を取得した人全員に発生します。
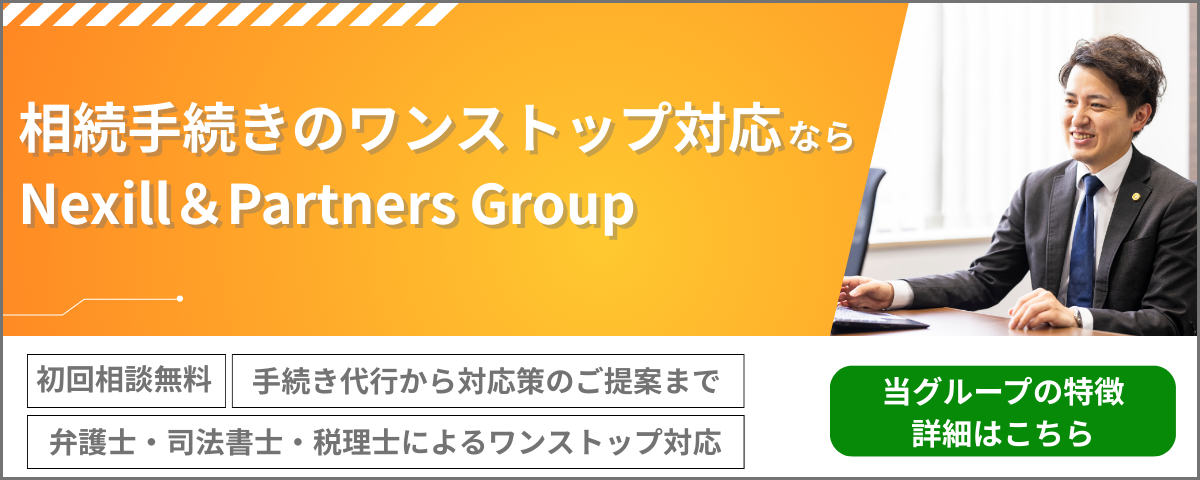
2. 相続人が複数いる場合の申告と納税の原則
相続税の申告は相続人がそれぞれ個別に行うというルールがありますが、実務上は「相続人が複数いる場合に、誰がどのように進めるべきか?」という点で悩まれる方が非常に多いです。
ここでは、複数の相続人がいる場合の申告と納税の原則的なルールと、代表者による取りまとめの可否、注意点について解説します。
2-1. 各相続人がそれぞれ申告義務と納税義務を負う仕組み
相続税の申告は、「被相続人から財産を取得した相続人ごと」に個別に行うことが法律で定められた義務です。
相続人が複数いる場合でも、「誰か1人が代表してまとめて申告すれば他の相続人の申告も済んだことになる」というわけではありません。
実務上は、税理士が関与して相続人全員分の申告書を1通にまとめて提出する(連名申告)ことが多くありますが、それはあくまで書類上の便宜であって、法的には各相続人が独立した申告義務者であるという前提に変わりはありません。
そのため、一部の相続人の申告内容に誤りがあった場合や、納税を怠った相続人がいた場合は、該当の相続人個人が税務署から是正通知や税務調査を受ける可能性があります。
申告は代表者に任せておけば自分は全く関係ないというわけではないことを理解しておきましょう。
2-2. 申告書の提出はまとめてでもOK?代表者による「取りまとめ提出」の可否
先ほどもお伝えした通り、相続人が複数いる場合、1人ひとりが別々に申告書を作成して税務署へ個別に提出する必要はありません。
実務上は、相続人の1人が他の相続人の同意を得たうえで、全員分の申告書をとりまとめて税務署に提出する「連名申告」という形式が広く採用されています。
この方法は、
- 書類の整合性がとりやすい
- 申告スケジュールを全体で管理しやすい
- 税理士と窓口が一本化される
といったメリットがあり、実務上も推奨されるケースが多くあります。
ただし、連名で提出する場合でも、各相続人が自らの取得財産・納税額・申告内容を確認・理解したうえで署名・捺印する必要があります。
あくまで書類提出の便宜が図られているだけで、法的な納税義務は相続人各自に分かれているという点に注意が必要です。
2-3. 他の相続人に無断で申告してもよいのか?
申告を急ぐあまり、他の相続人の同意を得ずに、代表者がまとめて申告書を提出してしまうというケースもありますが、これは極めてリスクの高い行為です。
相続税申告書には、
- 相続人全員の財産取得内容
- 特例適用の有無
- 遺産分割の内容(未分割/分割済など)
といった、各人の納税額に直結する情報が記載されるため、本人の意思確認がなければ法的に無効とされる可能性もあります。
また、無断で申告されていたことに後から気づいた相続人が、内容に納得していない、署名していない、税額の負担をめぐって争うといったトラブルに発展することもあり、税務署がその申告書の有効性を認めないケースも想定されます。
そのため、たとえ代表者が書類をまとめて提出する場合であっても、必ず全相続人の同意と確認を行ったうえで申告をしましょう。
2-4. 相続税納付の責任は「代表者」ではなく「各相続人」
相続税の納税義務は、申告義務と同様に、財産を取得した相続人ごとに個別に発生します。
実務上では申告を主導する相続人が立て替えて納税する場面もありますが、これはあくまで便宜的な「立替払い」であり、法的義務ではありません。
税務署から見ても、申告をした際に誰が代表者だったかではなく、「相続人各自がいくら納めるべきか」を基準に個別に納税状況を確認するため、未納があればその本人が延滞税や督促の対象となります。
3. 実務上は誰が申告をするべきか?
相続税申告は、法的には相続人全員が個別に行う義務を負っています。
しかし、実務上では主導的に相続税申告を進める人を相続人の中から一人立てるケースが多いです。
ここでは、誰がその役割を担うのが適切か、また担当者になった場合の注意点について解説します。
3-1. 代表相続人となるのは誰が良いのか?
相続税法上、代表申告人を誰にするのかという法的な決まりや制限はありませんので、相続人の中で誰が代表になっても問題はありません。
特に、次のような人がいる場合は、代表申告人になってもらうとスムーズです。
- 被相続人と生前に関わりが深く、財産状況をよく知っている人
- 書類収集等で比較的稼働がしやすい人
- 過去に相続税申告を行った経験がある人
3-2. トラブルを避けるための連絡・確認・合意のポイント
代表者が申告を進める際には、次のような配慮が重要です。
- すべての相続人に、作業の進捗と方針を共有する
- 各人が確認すべき書類(申告書、分割協議書など)には必ず目を通してもらう
- 署名・押印の前に、税額や分割内容の説明を丁寧に行う
- 誤解や疑念を生まないよう、透明性の高い運用を心がける
他の相続人の同意や確認を怠ると「勝手に進められた」と感じさせてしまいますので、後のトラブルを避けるためにもしっかりとコミュニケーションを取りながら進めるようにしましょう。
3-3. 遺言執行者がいる場合、その人に代表で相続税も申告してもらえる?
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が相続手続を主導で進めることとなりますが、遺言執行者は相続税申告そのものを代理する立場ではありません。
遺言執行者の権限は、あくまで、財産の名義変更や特定財産の引渡しなど、遺言内容の実現を目的とした範囲に限定されており、相続税申告の責任は財産を取得する各相続人にあります。
そのため、遺言執行者がいる場合でも、相続税申告は相続人自身が行うか、税理士に依頼の上で申告を代行してもらうかのいずれかで個別に対応する必要があります。
4. 「申告を誰がやるか」で起こりやすいトラブルと防止策
相続税申告において、相続人の1人が主導的に動くことは実務上よくあることです。
しかしその過程で、他の相続人に内容をきちんと共有しないまま、申告書を一方的に作成・提出してしまうという事態が起こると、後々「そんな内容で申告するとは聞いていない」「自分の意志ではない」といったトラブルにつながる可能性があります。
よくあるトラブルの原因
- 他の相続人の署名・押印を得ないまま申告書を提出していた
- 分割協議が完了していない段階で、法定相続分に基づく申告を勝手に行っていた
- 特例適用や税額の計算内容を知らせず、黙って申告した
加えて、税務署も申告書の整合性や全相続人の意思確認を重視しており、相続人ごとに事情聴取や税務調査を行う場合があります。
その際、申告内容について相続人間で説明が食い違えば、「本当に正しい申告がされたのか」という疑念を招きかねません。
相続税申告を相続人全員分をまとめて実施する場合は、以下のように情報共有・説明を確実に行い、共通理解を持ったうえで進めるようにしてください。
- 進捗状況や申告方針を全員に逐一共有する
- 税額や取得財産の内容について説明責任を果たす
- 申告書の署名・押印を確実に取り、文書で記録を残す
5. よくある質問(FAQ)
Q1:相続人の一人が申告や手続きを拒否した場合、その人の分の申告はどうすればよいですか?
A:その相続人の申告・納税義務を他の相続人が代行することはできません。
相続税は「各相続人が自分の取得分に応じて個別に申告・納税する制度」であり、他人の代理で勝手に申告を行うことは原則として認められていません。
そのため、申告への協力を拒否する相続人がいる場合は、
- まずは自分たち(協力的な相続人)の分だけでも期限内に申告・納付を行い、
- 拒否している相続人には、書面等で協力を促した記録を残しておくことが重要です。
その相続人が期限内に申告・納付しなければ、税務署からその人に対して無申告加算税や延滞税が課されることになります。
一方、全体の遺産分割が未了である場合は、協力している相続人のみで法定相続分に基づいた「未分割申告」を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、将来的に分割がまとまった際に特例を適用できる可能性が残せます。
相続人間での交渉が進まない場合には、調停や弁護士による法的サポートも視野に入れるべき状況といえるでしょう。
Q2:相続人がいない場合、相続税の申告は誰が行うのですか?
A:相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合、最終的にその財産は国庫に帰属します。ただし、その前段階として家庭裁判所により「相続財産管理人」が選任され、相続財産の管理・清算が行われます。相続税申告が必要な場合は、この相続財産管理人が申告・納付を行う立場となります。
まずは相続財産管理人の選任申立を行わなければなりませんので、弁護士にご相談ください。
Q3:申告期限が土日・祝日に当たる場合はどうなりますか?
A:相続税の申告期限が土曜・日曜・祝日と重なる場合、期限はその翌開庁日(通常は月曜日)に自動的に延長されます。例えば、期限日が日曜日であれば、翌月曜日が正式な申告期限です。
ただし、申告期限ギリギリでの提出は、書類の不備や記載ミスがあった場合に修正や再提出の時間的余裕がなくなってしまうため、できるだけ早めに準備・提出を進めることが望ましいです。
Q4:相続税の申告が必要かどうかをどのように判断すればよいですか?
A:相続税の申告が必要かどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが基準になります。ただし、配偶者の税額軽減や生命保険金・退職金の非課税枠などを考慮すると、申告義務の有無の判断は複雑になります。財産評価の知識が必要なため、迷った場合は早期に税理士に相談することが重要です。
なお、配偶者控除や各種特例を適用する場合は、相続税申告をしていることが条件となりますので、基礎控除額を下回っている場合でも相続税の申告が必要となりますので注意してください。
6. 当グループはワンストップで相続申告を支援しています
当事務所グループでは、税理士・弁護士・司法書士が在籍し、相続に関わるすべての手続きを一括でサポートしています。
相続税申告の代行だけでなく、その前段階の遺産分割協議や万が一の紛争対応、税申告以外の相続手続についても全てご対応が可能です。
まずは一度ご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。



