皆さんは、税金の申告をご自身でされたことはありますか。
事業をされている個人事業の方などは、所得税の確定申告をご自身でされたこともあると思います。
しかし、「相続税」の申告をしたことのある方はそれほどおられないのではないでしょうか。
一般的に相続税申告は税理士に依頼をする方がほとんどかと思いますが、今回は敢えてご自身で申告を行うことを念頭に、相続税申告の必要書類のうち、「相続税申告の際に取得する必要のある書類」について、一部ご紹介したいと思います。 すべての必要書類をご紹介するのは分量的に難しいのですが、今回の記事をきっかけに、相続税申告について少しでも興味を持って頂ければと思います。
1.相続税申告における基礎知識
相続税は、簡単にいうと、①どなたかが亡くなられた場合で、②一定の基準額(基礎控除額といいます。)を超えた遺産が存在する場合にのみ申告する必要が出てきます。そもそも、毎月入ってくる収入に課税される、比較的身近な所得税と違って、相続税は、①どなたかが亡くなった場合にのみ課税される点で、皆さんの周りでもそれほど頻繁に問題になることはないかもしれません。
それに加えて、②基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で計算されますので、それなりの遺産額でなければ相続税の納税は不要ということになります。
残された遺産の種類や数にもよりますが、率直に申し上げて、相続税申告はかなり複雑です。
何が複雑かをすぐにご説明するのは難しいのですが、例えば、どこまでの財産を相続税の課税対象となる「遺産」と考えるのか、遺産の中に不動産や株式がある場合、いったい「いくら」のものとして評価するのか、又は葬儀費用の扱いはどうなるのかなど、検討しなければならないことが多いうえに、1つ1つについて、専門的知識を要求されることも多いです。
本コラムでは保有資産別に相続税申告を行う際に準備すべき必要書類の一覧と、書類を集めるうえでのポイントについて、相続問題に関する対応実績が豊富な弁護士が解説しております。複数にまたがるケースも少なくありませんので、ぜひご参考にしてください。
相続税申告に関する基礎知識の詳細はこちらの記事でも解説しておりますので、ぜひご覧ください。
2.【家庭用財産】の場合の相続税申告の必要書類
(1)書類一覧
| 書類名等 | 取得できる場所・取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 時価が5万円を超える 家庭用財産のリスト |
相続人等が自宅を調査し、 作成する。 |
5万円を超えているかどうかは、1個または1組ごとに判定する。 |
| 時価が5万円を超える 家庭用財産の購入時の資料 |
自宅等に保管がある場合。 | 買った時期や金額、店舗名の分かる領収書等。 |
| 自動車検査証(車検証) | 車種、初度登録年月日、型式の確認のため。 | |
| 美術品が入っていた箱や保証書 等 | 落款(印)や署名等真贋確認のため。 | |
| 美術品相続評価書 | 画商や骨董商、各地の美術倶楽部等。 鑑定評価料数万円~、 評価書発行量数万円 |
画像だけで簡易に査定してくれる場合もある |
| 船舶検査証書、 購入時の契約書や領収書 等 |
船種、船名、登録番号等の確認のため。 |
(2)書類を集める上でのポイント
①家庭用財産は5万円を超えているかどうかで判定する
相続開始日現在における1個または1組の価額(時価)が5万円以下の家庭用財産は、世帯ごとにまとめて大まかに価値を見積もり、一括で評価してよいことになっています。そのために、まずは、5万円を超えそうな新品やアンティークの物等がないかどうか確認してください。
②趣味の道具や美術品に注意
亡くなった方に、カメラ、ゴルフ、マリンスポーツ、ワイン、音楽、茶道等のような趣味があり、それらに関する道具が多くある場合や、美術年鑑に記載されている作家の美術品がある場合、念のため価値の判断できる専門家に確認してもらいましょう。亡くなった方の通帳や生前の振込や引き落としの記録から、購入金額が分かるようなら確認してみてください。
3.【生命保険・損害保険・火災保険】の場合の相続税申告の必要書類

(1)書類一覧
| 書類名等 | 取得できる場所・取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 保険証券のコピー | 自宅(保険会社への提出前にコピーしていた場合)。 | 契約書・被保険者・受取人の確認のため |
| 保険金の支払明細 支払通知書 支払計算書 支払手続き完了のお知らせ 等 |
保険金請求後、保険会社から保険金の支払前に受取人に郵送される。 保険金の支払日や金額、送金先等が記載されている。 |
故人が被保険者だった保険がある場合。 書類名は保険会社により異なる。 |
| 解約返戻金相当額等証明書 生命保険権利評価額証明書 等 | 契約していた保険会社。 | 故人が契約者(保険料負担者)で、今回保険金が支払われない保険がある場合。 |
| 建物更生共済の解約返戻金証明書 | 共済契約を結んでいる農協等。 | 契約返戻金のある共済契約がある場合。 |
| 受取人の通帳 | 入金確認のため。 | |
| 保険料負担者の通帳 | 保険料を支払った事実を確認するため。 |
(2)書類を集める上でのポイント
保険が、相続税の対象になるかならないかの判断は難しいです。
保険金が支払われない保険契約、も相続税の対象になることがあります。家にある保険証券について、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人を確認してください。
①契約者・被保険者・受取人・保険料・保険金について
亡くなった方が被保険者だった生命保険は、相続で保険金が支払われ、相続税の対象になります。以下で保険の用語について説明します。
「契約者」…契約の当事者となり保険料を払う人
「被保険者」…保険の対象になっている人
「受取人」…保険金をもらう人
「保険料」…契約者が保険会社に払い込むお金
「保険金」…もしものときに受取人がもらえるお金
②保険証券
上記は、保険加入時に保険会社から契約者に交付される保険証券に記載されています。しかし、保険金の請求手続きをするときには保険証券を提出する必要があり、一度提出してしまうと、その後は返還されないので、注意が必要です。通常、保険金の請求手続きを行った後に相続税申告を行うことが多いので、保険会社へ提出する前にコピーを取っておいてください。
保険証券が見当たらない等保険契約の有無が不明な場合は、亡くなった方の所得税の確定申告書に生命保険料控除証明書が添付されていないか、または、給与所得の源泉徴収票に生命保険料の控除額の記載がないか、または、預金口座から保険料が引き落とされていないか等、見てみてください。
③解約返戻金相当額等証明書
解約返戻金相当額とは、保険を解約したときに保険会社から戻るお金のことです。終身保険や養老保険等、保険期間が長い保険や掛け捨てではない貯蓄性のある保険には、解約返戻金があることが多いです。
相続で保険金が支払われなくても、亡くなった方が契約者(保険料負担者)である生命保険は、解約返戻金相当額が相続税の対象になります。
亡くなった方が家族にかけた(被保険者が家族の)生命保険の中にこのようなものがないか、保険証券を持ち寄り確認してみましょう。
該当する保険があった場合は、保険会社に相続開始時点での解約返戻金相当額を証明する「解約返戻金相当額等証明書」の発行を依頼してください。証明書を発行してもらえない保険会社もありますが、相続人に対しては、口頭や簡易な書面で金額を教えてもらえることが多いです。
④契約者と保険料負担者が異なる場合
原則、保険料は、契約者が負担すべきものです。しかし、家族が契約者になっている保険の保険料を、家族が代わりに亡くなった方が現金や口座振替で支払っていることがあります。
その場合は、「名義保険」(契約者が単に名ばかりにすぎない場合)として扱われ、実際に保険料を負担していた人が誰かということで税務上の取扱いを判断します。
⑤会社員の場合
保険料を給料から天引きする団体扱いの生命保険に加入していないか、勤務先に確認してください。
⑥損害保険が相続税の対象になる場合
亡くなった方が建物更生共済(積立型の共済契約)の契約者だった場合、解約返戻金の額が相続税の対象になります。加えて、掛け捨ての火災保険や自動車保険等契約返戻金のない損害保険も,生前に保険料を一時払いしていた場合は、前納保険料の額が相続税の対象になります。
4.【有価証券】の場合の相続税申告の必要書類
(1)書類一覧
| 書類名 | 取得できる場所 | 取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 残高証明書 | ①証券会社や銀行で取引していた場合、その証券会社や銀行等で取得できる。 | 手数料は金融機関により異なる。 | 相続開始日現在の残高を依頼する。 |
| ②株券を現物で保有していた場合等は、株式名義書換代行機関になっている信託銀行等(株主名簿管理人)で取得できる。 | 手数料は金融機関により異なる。 | ||
| 配当金計算書、支払通知書、株主総会招集通知 | 自宅に保管があれば取得できる。 | 1単元に満たない株式がないかどうかを確認する。 | |
| 取引残高報告書 | 郵送または電子(インターネット)で金融機関から交付される。 | 基準日現在の預かり資産の一覧が記載されている。 |
(2)書類を集める上でのポイント
有価証券とは、株式、債券(公債や社債)、投資信託等のことです。
①残高証明書
通常は、取引していた証券会社や銀行に発行を依頼してください。一般的に、取引店や相続専用のセンターで手続きをします。「相続税の申告に使います」と伝えると、所有していた株式数や口数、相続税申告に必要な評価額や利率等を記載してもらえることが多いです。
株券を現物で保有していた場合等は、株式名義書換代行機関になっている信託銀行等(株主名簿管理人)に残高証明書の発行を依頼してください。株主名簿管理人は、株主になっている会社のホームページや、配当の時期に郵送される「配当金計算書」で確認することができます。
②単元未満株式
単元未満株式とは、1単元(100株や1,000株など、銘柄ごとに決められている最低売買単位の株式)に満たない株式のことです。長年同じ銘柄を保有していた場合に生じることが多いです。これは、証券会社や銀行の残高証明書に記載されないために確認を忘れがちですが、相続税の対象になります。
「配当金計算書」や「配当金支払通知書」、「株主総会招集通知に同封されている議決権行使書」には、単元未満株式も含めた所有株数が記載されているので、亡くなった方がこれらを保管していないか探してみてください。見つからない場合は、株主名簿管理人に単元未満株式の有無を問い合わせてください。
③取引していた証券会社等が分からない場合
証券会社等からは、期間中に取引があれば3か月に1度、取引がなくても1年に1度は「取引残高報告書」が郵送または電子で交付されます。これには、預り資産の詳細な内容が記載されていますので、まずは探してみてください。見当たらない場合は、インターネットで取引を行っていた可能性があるので、亡くなった方のパソコンやスマートフォンを調べ、インターネット上のお気に入りに証券会社のホームページが登録されていないか確認してください。パソコンのメールを確認するのも方法の一つです。
それでも見つけることができなければ、証券保管振替機構(通称ほふり)に、「登録済加入者情報の開示請求」という手続きを行えば、どの証券会社に口座を開設していたのかだけは、確認することができます。ただし、保有銘柄や株数等の情報は、別途証券会社への問い合わせが必要です。
5.【非上場株式】の場合の相続税申告の必要書類
(1)書類一覧
| 書類名 | 取得できる場所 | 取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 法人税申告書 | 通常は、税務署に提出したものの控えが会社に保管されている。 株式を発行している非上場会社に問い合わせること。 |
直近3事業年度分。 修正申告書、県民税申告書、市民税申告書、消費税申告書も必要。 |
|
| 決算報告書(賃借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表) | |||
| 勘定科目内訳明細書 | |||
| 法人事業概況説明書 | |||
| 定款 | 株式を発行している非上場会社。 | 現行のもの。 | |
| 株主名簿 | |||
| 従業員数のわかる資料 | 役員は除く。 | ||
| 登記事項証明書又は登記情報 | 登記事項証明書は法務局(郵送も可)。 登記情報は、インターネットの登記情報提供サービス。 |
法務局の場合、600円。登記情報提供サービスの場合、335円。 | |
| 日本標準産業分類 | 総務省ホームページ | 原則的評価方式(類似業種比準価額)で評価する場合に必要。 | |
| 日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表 | 国税庁ホームページ | ||
| 類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 | 国税庁ホームページ | 原則的評価方式(類似業種比準価額)で評価する場合に亡くなった年分のものが必要。 |
(2)書類を集める上でのポイント
非上場株式は、株式の保有目的は会社の規模、資産や利益の状況などをもとに評価するために必要です。
亡くなった方が会社を経営していた場合など、遺産の中に非上場株式(取引相場のない株式)が含まれていることがあります。
非上場株式の評価方法は非常に複雑です。また、相続後にその株式をどうするか等、相続税申告以外の面から検討しなければならないことが多く、専門的な知識が必要です。そのため、まずは、顧問税理士がいればその方に、いなければ相続税に強い税理士などの専門家に相談し、自分で相続税申告ができるかできないかも含めて、アドバイスをもらうことをお勧めします。
6.【預貯金】の場合の相続税申告の必要書類

(1)書類一覧
| 書類名 | 取得できる人 | 取得できる場所 | 取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 残高証明書 | 相続人や遺言執行者 | 口座のある金融機関の窓口 | 手数料は金融機関により異なる。 | 相続開始日現在の残高を依頼する。 |
| 亡くなった方名義の通帳 | 自宅に保管してある場合。 | 相続開始日前後の記帳がされているもの。 | ||
| または取引履歴 | 相続人 | 口座のある金融機関の窓口 | 手数料は金融機関により異なる。 | 通帳がない場合に依頼する。 |
| 亡くなった方の家族名義の通帳 | 各家庭に保管がある場合。 | 通帳にあるお金の出どころが家族出身の収入の場合は不要。 | ||
| 定期預金証書 | 自宅に保管がある場合。家族名義のものも確認する。 | 通帳式と証書式があり、証書式の場合に必要である。 | ||
| 利息計算書 | 相続人や遺言執行者 | 口座のある金融機関の窓口 | 手数料は金融機関により異なる | 定期預金があれば必要。普通預金は不要。 |
(2)書類を集める上でのポイント
①取引していた金融機関がわからない場合
通帳やキャッシュカード、証書等が自宅にないか確認してみてください。
②ネット銀行
亡くなった方のパソコンやスマートフォンを調べ、インターネット上のお気に入りにネット銀行のホームページが登録されていないか確認してください。IDやパスワードが不明でログインできない場合も、電話や郵送などで口座保有の有無を問い合わせてみてください。
③残高証明書
相続開始日(亡くなった日)現在の残高証明書を発行してもらう必要があります。外貨預金の場合、円に換算する必要があるため、対顧客直物電信買相場(TTB)に記載してもらいましょう。取引店以外で手続することもできますが、一般的には証明書の発行には日数がかかります。
④亡くなった方名義の通帳
税務調査では税務署が一番細かく調べる点なので、過去6年分程度は必ず入手してください。
⑤取引履歴
過去の通帳が見つからない場合に、通帳と同じ情報が記載されている取引履歴の発行を金融機関に依頼してください。発行には日数や費用がかかりますが、亡くなった方の相続人であれば単独で発行を依頼することができます。
⑥定期預金・定期貯金
定期預金・定期貯金は、亡くなった日に解約したと仮定した場合の利息も相続税の対象になるので、利息計算書を発行しなければなりません。残高証明書に既経過利息を記載してもらう形でも構いません。ただし、普通預金や通常貯金の場合は不要です。
⑦相続人が複数いても単独(1人だけ)で行える手続き
・口座の有無の調査
・残高証明書・取引履歴・利息計算書の発行依頼
は、相続人のうちの1人が単独でできます。なお、相続人全員の署名や印鑑なども必要ありません。
⑧亡くなった方の家族名義の通帳
家族名義の通帳にあるお金が、亡くなった方の収入によるもので、かつ、家族へ生前に贈与されたものでない場合、そのお金は亡くなった方の相続財産として相続税の対象になります。それを確認するために、家族名義の通帳が必要になることがあります。
相続税の申告上、預貯金や株式などの金融資産は、もともとのお金の出どころ(原資)は誰かという観点から、実質的な所有者を判断します。「誰の名義になっているか」ということは重視されません。そのため、亡くなった方の家族名義の金融資産についても、その資産が家族自身が外で働いて稼いだお金、実家から相続したお金、亡くなった方から生前に贈与されたお金などではない場合、実質的な所有者が亡くなった方である「名義預金・名義株」ではないか、検討しなければなりません。
7.【現金】の場合の相続税申告の必要書類
(1)書類一覧
| 書類名 | 取得できる人 | 取得できる場所 | 取得費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 亡くなった方名義の通帳 | 自宅に保管してある場合。 | 相続開始日前後の記帳がされているもの。 | ||
| または取引履歴 | 相続人 | 口座のある金融機関の窓口 | 手数料は金融機関により異なる。 | 通帳がない場合に依頼する。 |
| 手許現金の金額を記したメモ | 相続開始日に自宅や財布、金庫等にあったと思われる金額を、保管場所ごとの一覧表にする。 | 通帳からの出金記録と照らし合わせる。 | ||
| 医療費の領収書 | 病院等 | 無料。ただし、再発行には手数料がかかることがある。 | 支払日を確認する。 | |
| 葬式費用の領収書または金額を書いたメモ | 領収書のもらえないお布施や心づけはメモでよい。 | |||
| 貸金庫内の保管物のリスト | 相続人等が金庫内の写真を撮り、リストを作る。 | 現金その他の相続財産が保管されていないかも確認する。 |
貸金庫内の保管物のリスト 相続人等が金庫内の写真を撮り、リストを作る。 現金その他の相続財産が保管されていないかも確認する。
(2)書類を集める上でのポイント
①現金について(資産を通帳等で保管している場合)
一般的な家庭では、自宅に多額の現金を保管することは少ないと思います。相続開始日に、自宅や財布にあったと思われる金額を概算で相続税申告に含めれば、それで問題はありません。
ただし、例えば、容体が悪化してから亡くなるまでの間に、亡くなった方ではなくその家族が、通帳から多額の現金を引き出しているケースは少なくないと思います。引き出した現金を亡くなった方の生活費や医療費として、生前に使い切った場合には問題はありません。しかし、死後に必要となる葬式費用や家族の生活費として引き出していた場合、そのお金は相続開始日の時点では現金として手元にあったはずなので、現金残高に含まなければいけません。
②現金ついて(多額の現金を保管している家庭の場合)
通帳から引き出したお金は、その後、①使う、②別の財産を買う、③現金のまま取っておく、のいずれかになると思います。税務署は、亡くなった方の通帳の生前の出勤記録をチェックし、通帳から出たお金がどのように使われたかを確認します。②や③の場合、別の財産や現金として相続税申告に含めてください。①の場合は、引き出したお金の使い道を税務署に説明できるよう、わかる範囲でまとめておいたほうがよいでしょう。亡くなった方の通帳の生前の入出金記録を、過去6年分必ず入手してください。
③貸金庫
貸金庫には、遺言や不動産の権利証などの遺産を探すための手がかりや、現金や金の地金、宝飾品等、遺産そのものが保管されている場合があります。貸金庫の利用料が口座引き落としの場合が多いので、通帳の引き落とし記録を確認して、契約や利用の有無を調べてみてください。
8.【家屋(建物)】の場合の相続税申告の必要書類
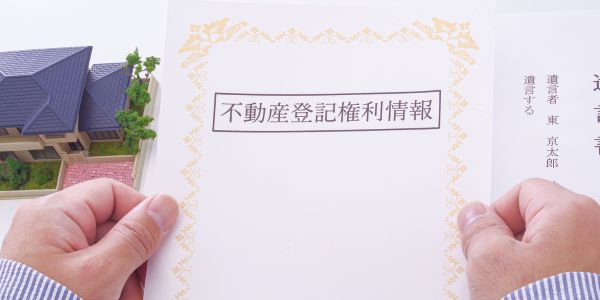
(1)書類一覧
家屋の中には未登記のものもありますが、それらも相続税申告の対象になりますので、以下の表を参考にしながら、注意して取得しましょう。
また、家屋(建物)に関する書類は、土地に関する書類と重複するものが多いので、一緒に取得することをおすすめします。
| 書類名 | 取得できる場所 | 費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税課税明細書 | 毎年、土地所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)から郵送される。 | ||
| 登記事項証明書 | 法務局(郵送可)。 | 600円 | 全部事項証明書を取得すること。 |
| または登記情報 | インターネットの登記情報提供サービス。 | 335円 | |
| 固定資産評価証明書 | 建物のある市区町村役場。東京23区は都税事務所(郵送可)。 | 手数料は市区町村により異なる。 | 亡くなった年のものが必要。 |
| 名寄帳(土地家屋課税台帳・固定資産課税台帳) | 建物のある市区町村役場。東京23区は都税事務所(郵送可)。 | 手数料は市区町村により異なる。 | 亡くなった年のものが必要。 |
| 建物図面/各階平面図 | 法務局(郵送可)。 インターネットの登記情報提供サービス。 |
法務局の場合、450円。登記情報提供サービスの場合、365円。 | 古い建物や未登記の建物にはないこともある。 |
| 建築計画概要書 | 建築確認申請時の書類。自宅に保管があるか確認。 | 増築の有無や建物の配置が確認できる。 | |
| 建築工事請負契約書 | 自宅に保管があれば必要。 | 設計図面などで建物の概要が確認できる。 | |
| 現地の写真 | 現地で撮影する。 | Googleマップのストリートビューなども参考になる。 | |
| 建物の賃貸借契約書 | 貸している・借りている土地がある場合に必要。なければ不動産会社に尋ねなければならない。 | 所有者と利用者が違う場合に必要。 | |
| 管理委託契約書 | 貸している・借りている土地がある場合に必要。なければ不動産会社に尋ねなければならない。 | 所有者と利用者が違う場合に必要。 |
(2)書類を集める上でのポイント
①分譲マンションの登記事項証明書
分譲マンションのように、1棟の建物の中に複数の独立した専有部分があり、その専有部分ごとに登記されている建物を「区分建物」といいます。
区分建物は、土地と建物が一体で登記されていることが多いので、建物の登記事項証明書を取得すれば、土地と建物の両方の登記状況が確認できます。ただし、比較的古いマンションは、土地と建物が別々に登記されていることがあり、その場合は土地と建物、それぞれの登記事項証明書を取得しなければなりません。
②建物図面/各階平面図
建物の位置を表した図面(建物図面)と建物の各階ごとの形状を表した図面(各階平面図)が一緒になっていることが多いです。
③建築計画概要書・建築工事請負契約書
建物の概要や配置が確認でき、宅地を評価する際に役に立ちます。建物の建築時に建築会社から受け取った書類一式に含まれていることが多いです。建築計画概要書は市区町村役場で閲覧することもできますが、写しを取得するには有料ですので、亡くなった方が保管していないか確認するとよいでしょう。
9.【事業用財産】の場合の相続税申告の必要書類
(1)書類一覧
亡くなった方が事業を営んでおり、個人事業主だった場合、事業用財産も相続税申告の対象です。
| 書類名 | 取得できる場所 | 費用 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 所得税の青色申告決済書または収支内訳書 | 控えの保管がなくても税務署で閲覧できるサービスがある。コピーは不可。 | 無料 | 確定申告を税理士に頼んでいた場合は税理士に確認すること。 |
| 帳簿(総勘定元帳、固定資産台帳など) | 個人事業者が事業や決済のために作成する。一定年数の保管が義務付けられている。 | ||
| 書類(棚卸表、通帳など) |
(2)書類を集める上でのポイント
①事業用財産とは
事業用財産とは、商品・製品・原材料などの棚卸財産、機械装置・器具・自動車などの減価償却資産、売掛金、未収入金などが該当します。屋号名の預金口座や事業用の手許現金も、相続税申告の対象です。
②書類の集め方
所得税の確定申告書には、青色申告の方の場合は「青色申告決算書」、白色申告の方の場合は「収支内訳書」という書類が添付されています。青色申告決済書には賃借対照表というすべての事業用財産のリストや減価償却資産の明細が、また、収支内訳書には減価償却資産の明細が載っているため、事業用財産を把握することができます。亡くなった方の確定申告書類の控えを確認しましょう。
③申告書等閲覧サービスの活用
書類が見つからない場合は、「申告書等閲覧サービス」を利用することもできます。これは、相続人などが税務署へ事前連絡をした上で、必要書類をそろえて窓口に行くと、税務職員の立ち会いのもと、亡くなった方が過去に提出した申告書などを閲覧できるというものです。手数料は無料です。閲覧できるのは、亡くなった方の相続人または一定の代理人です。ただし、閲覧をするには、相続人全員の委任状と印鑑証明書が必要です。また、閲覧内容を持参した紙に書き写すことはできますが、コピーはできません。
10.まとめ
今回は相続税申告の際に必要となる書類と収集の際のポイントをご説明しました。
相続税申告を自分で行うべきかどうか迷っている方も多いかもしれませんが、実際には多岐にわたる書類の準備や、資産ごとの評価方法、法的な取り扱いの理解が必要で、思わぬ時間や労力を費やすことが少なくありません。また、些細なミスが後のトラブルや申告漏れによる追徴課税につながることもあり、自分で対応するリスクは決して小さくないのです。
「書類を集めているうちに混乱してきた」「そもそも評価の方法が分からない」と感じる前に、専門家に相談することで、スムーズで正確な申告が可能になります。相続税申告に関するご相談はNexill&Partnersグループにご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。


