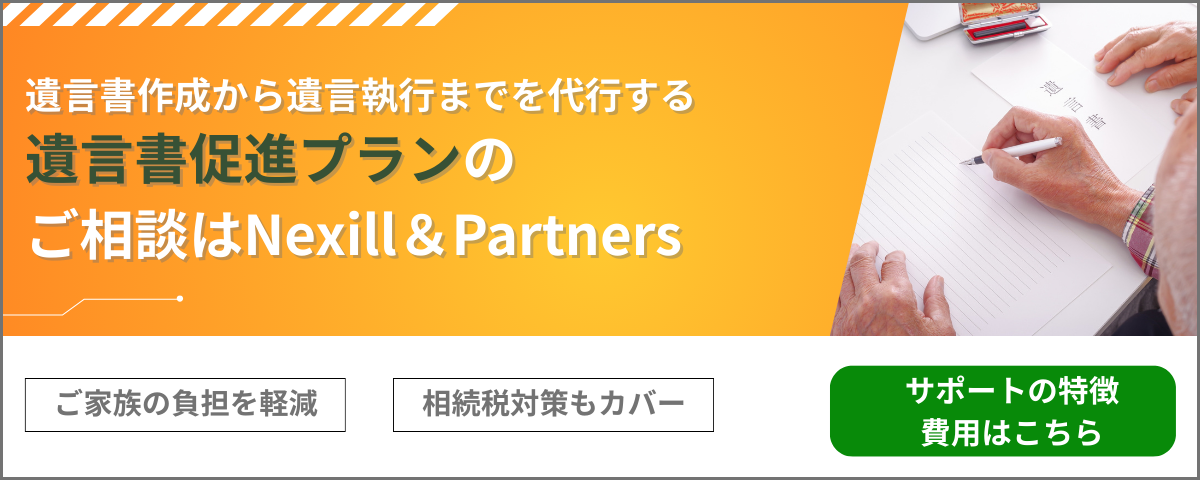「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続手続をスムーズにしたい」──そんな想いから遺言信託を検討される方が増えています。
とくに、銀行や信託銀行が提供する遺言信託サービスでは、公正証書遺言の作成から保管、死亡後の遺言執行までを一括で任せられる点が魅力ですが、ご自身やご家族の状況によってはうまく活用できなかったというようなケースもあります。
本記事では、遺言信託を使う上で実際に起きやすいトラブルやその背景、遺言信託は弁護士に依頼することもできるのか?という点までを詳しく解説します。
1. 「遺言信託」の基本理解
1-1. 遺言信託は「遺言による信託」とは異なる
一般的に遺言信託という言葉には、①信託法に基づく「遺言による信託」と、②金融機関や信託銀行が提供する商品サービスとしての「遺言信託」があります。
本コラムで解説する後者の金融機関等が提供する遺言信託というのは、主に次の業務で構成されています。
金融機関が提供する遺言信託業務の主な内容
- 遺言書の作成支援(公正証書での作成をサポート)
- 遺言書の保管(契約に基づき信託銀行等が管理)
- 死亡後の遺言執行(名義変更・払い戻し・分配などの手続代行)
こちらを見ていただくとわかる通り、「遺言信託」と呼ばれているものは、信託法上の「受益者・受託者」などの構造をとる信託契約とは異なり、遺言書の実行支援をパッケージ化した委任型のサービスと捉えるのが実態に近いものです。
1-2. どこまで対応してくれる?実際の業務範囲
一般的に、金融機関の遺言信託サービスでは「標準的な相続手続」に絞ったサポートが行われることが多く、以下のような手続きが代表的です。
遺言信託サービスの主な業務範囲
- 相続人への通知・連絡
- 預金口座の解約、払い戻し
- 株式・有価証券の名義変更
- 公正証書遺言の内容に基づく財産分配
ただし、税務申告、不動産登記、相続人調査、紛争時の代理対応などは範囲外であることが多く、それぞれ別途専門家に依頼しなければならない点に注意が必要です。
1-3. こういう人に向いている、という一般的な設計前提
金融機関の遺言信託サービスは、次のような方を主な利用者像として設計されているのが一般的です。
- 相続人間に特に揉める要素がない(配偶者+子どもなど)
- 財産が主に預金・有価証券などで構成されている
- 生前に一括で準備し、死後は任せてしまいたい
- 法律相談や家族内での協議や調整までは特に必要としていない
このように、“手続代行”として割り切って使うには適している反面、複雑な遺言書内容の設計や親族間の協議等のサポート面までを求める方には合わないケースもあります。
2. 遺言信託で実際に起こりうる代表的なトラブル事例
2-1. 銀行が遺言執行を辞退した/対応できないと言われた
金融機関はすべての遺言信託案件に対応してくれるわけではありません。 たとえば、以下のようなケースでは、銀行が遺言執行を断る、もしくは途中で辞退することがあります。
- 相続人間で紛争が発生している
- 相続財産に評価困難な資産(自社株・借地権など)が含まれている
- 一部の相続人の行方が不明で連絡が取れない
こうした事例では、契約時には「対応可能」と説明されていても、実際には想定通りに動かないこともあるため注意が必要です。
2-2. 遺言書の内容により、紛争トラブルに発展
遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記載していた結果、他の子どもから遺留分侵害額請求が行われてしまい、結果として金融機関では対応できず弁護士に相談が持ち込まれるといったようなケースです。遺留分以外でも、そもそもの遺言書の作成自体の効力を争われる(遺言無効)など、相続手続の過程において紛争化してしまった場合は弁護士以外での対応ができないため、注意が必要です。
3. なぜトラブルが起こるのか?背景にある3つの盲点
3-1. 「銀行=全部やってくれる」という誤解
多くの方が、金融機関の「遺言信託」という言葉から、「自分の死後、相続に関するすべてを銀行が一括してやってくれる」と想像します。 しかし、実際には銀行が担うのはあくまで遺言書の保管と、死亡後の定型的な執行業務に限られています。 相続人の調査や確認、紛争が発生した場合の対応、さらには不動産登記や税務申告などは、サービス対象外であるケースが大半です。
このように、「任せておけば大丈夫」という過信が、実務上の落とし穴に気づくタイミングを遅らせてしまうのです。
3-2. サービスの限界を理解せずに契約している
遺言信託の契約時、パンフレットや担当者の説明だけでは業務範囲や除外項目が十分に把握できていないことがあります。 例えば、以下のような要素は、契約書に小さく記載されているような場合も多く、重要性が理解されていないことが多く見受けられます。
- 相続人に連絡が取れない場合は執行停止
- 認知症や後見対象の相続人がいると追加手続が必要
- 相続税や不動産登記は別契約、別途費用
- 遺言内容によっては銀行が執行を辞退する可能性あり
これらを契約時に十分理解しないまま署名してしまうことで、「想定と違う」というトラブルの温床となってしまいます。
3-3. 遺言内容が曖昧なまま、形式だけ整えられている
金融機関の遺言信託サービスは、一定の標準フォーマットに沿った文案で作成されることが多く、個別事情に応じた柔軟な内容の設計は行われないのが一般的です。 そのため、「長男に相続させる」と書いてあっても、どの財産を?どのような条件で?といった点が曖昧なまま執行段階に進んでしまうことがあります。
また、家族に障害を持っている方がいる、相続人間の仲が悪い――などといった各御家庭の個別具体的な背景が反映されないことで、遺言としては形式的に有効でも、遺言内容の実行段階で摩擦や停止が起きるという構造的リスクをはらんでいます。
4. 事前に防げるトラブル、実は多いです。
4-1. 紛争リスクを踏まえた内容調整と情報共有
遺言内容は、被相続人の自由意思が尊重されるべきものですが、残された家族に争いを残す内容になっていないかを客観的に確認する作業も重要です。 たとえば、特定の相続人にだけ財産を多く残す場合は、遺留分侵害リスクの存在を前提に調整案(代償分割・現金配分など)を検討する余地があります。
また、完全に内容を秘密にするのではなく、信頼できる家族にはある程度方針を伝えておくことで、遺言執行時の混乱や反発を避けることができます。
4-2. 「誰が受け取るか」だけでなく「どう実行されるか」を考える
遺言を作成する際、多くの方が「誰に何を渡すか」に意識が向きがちです。 しかし、重要なのはその内容が現実に問題なく実行されるかどうかです。先ほどの遺留分の問題もそうですし、遺言執行者を誰に指定するかという点でも適切な人選ができるかどうかでスムーズな遺言執行ができるかどうかが変わってきます。
単に遺言書の内容を作るだけでなく、「遺言が執行される状況まで想定しておくこと」が、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
5. 弁護士に「遺言信託」を頼む場合はどうなる?委任の仕組みを解説
5-1. 弁護士による「遺言信託」= “遺言書作成+遺言執行の委任”
金融機関でいう「遺言信託サービス」は、実務的には「遺言書作成+保管+遺言執行」の3点セットを指します。 弁護士にこれと同等の業務を依頼したい場合、法的には以下の2つの委任を組み合わせて行うことになります。
② 遺言執行者への就任と、死後の執行事務に関する委任(遺言による遺言執行者指定+任意契約)
つまり、金融機関のように“包括的パッケージ商品”として契約するのではなく、弁護士と個別の業務委任契約を結ぶ形で遺言信託と同じ業務範囲を依頼することになります。
5-2. 死後に効力を発する「遺言執行者指定」が実務の鍵
弁護士が遺言信託的業務を担う場合、最も重要になるのが、遺言書内で「遺言執行者」に弁護士を指定しておくことです。 この指定があることで、弁護士は被相続人の死亡後、遺言の内容を実現するための一切の行為(預金の払戻し、不動産の名義変更、遺贈の履行など)を正当に行える権限を持ちます。
民法上、遺言執行者には「相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」が認められており(民法1012条)、相続人の代理権限を代替するかたちで実務を進めることができます。
5-3. 遺言書の中に“執行者への報酬条項”を記載しておくのが一般的
弁護士が遺言執行者として職務を担う場合、原則として「遺言に報酬の定めがあればそれに従う」ことになります。 したがって、遺言書の文末に「遺言執行者には、相当額の報酬を支払うものとする」といった条項を設けておくことで、業務範囲に応じた適正な報酬の支払いが可能になります。 なお、報酬金額は事前に見積り・契約書で明示しておくことがほとんどです。
5-4. 金融機関との違い:自由度と実行力の高さが弁護士の強み
弁護士への委任による遺言信託的業務の最大の特徴は、依頼者の事情に応じて設計の自由度が高いこと、そして実行時にも柔軟な対応が可能であることです。 金融機関では対応できない以下のような業務も、弁護士であれば一貫して引き受けることが可能です。(別途報酬は発生します。)
- 複雑な家族関係への調整支援(遺留分対応・面談など)
- 認知症や行方不明の相続人への対応(後見・不在者財産管理)
- 財産目録作成、不動産の現地調査、遺言内容の補足契約
- 調停・訴訟への代理対応(相続紛争発生時)
金融機関が提供する遺言信託サービスは、手続の簡便さや信頼感といった面で大きな魅力がありますが、対応範囲や遺言設計の柔軟性には一定の限界があります。「家族構成が複雑」「遺言の内容に個別の配慮が必要」「将来的に争いが起きそう」――そんなケースでは、弁護士に遺言作成や執行を委任することも、現実的な選択肢のひとつです。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言信託を使うか、普通の遺言で済ませるか迷っています。
A. 遺言信託は、相続手続の一部を専門機関に任せたいという方に向いていますが、必ずしもすべての方に必要なわけではありません。 たとえば、相続人が1〜2人で争いの見込みがない場合は、公正証書遺言+遺言執行者の指定だけで十分なケースもあります。相続財産が多岐にわたる、家族構成が複雑、相続人の中に障がいをお持ちの方がいるなど、特別な事情がある場合には、遺言信託と他制度を組み合わせた設計を検討することもありますので、弁護士にご相談のうえで進められるのが望ましいでしょう。
Q2. 生前に家族に遺言の内容を伝えておいた方がいいですか?
A. はい、できるだけ伝えておいた方がよいです。相続トラブルの多くは「内容に納得できなかった」ということに加えて「知らされていなかった」ことによる感情面が原因の一つとなっています。法的には遺言の内容を親族に公開する義務はありませんが、信頼できる相続人に方向性を伝えておくことで、遺言執行時の相続人同士での摩擦や相続手続の遅延を防ぐことができます。
Q3. 金融機関で遺言信託を契約したあとですが、今からでも弁護士に相談できますか?
A. もちろん可能です。「すでに契約をしてしまったけれど、この内容で大丈夫か不安」という方からのご相談も多数お受けしています。弁護士がセカンドオピニオンとして法的な問題点を確認し、必要に応じて補完的な手段(遺言内容の作成、家族信託など)のご提案を行います。銀行や信託銀行での遺言信託内容に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺言信託は便利な制度である一方で、「すべて任せられる」と思い込んだまま契約してしまうと、かえってトラブルのもとになることがあります。制度の仕組みを正確に理解しないまま契約してしまうことがないよう、本記事で紹介した事例のように、金融機関のサービス範囲や契約上の限界をきちんと理解したうえで「ご自身と家族にとって本当に安心できる方法」を選択していただくことが大切です。
遺言信託について弁護士へのご依頼も視野に入れておられる方は、まずはお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。