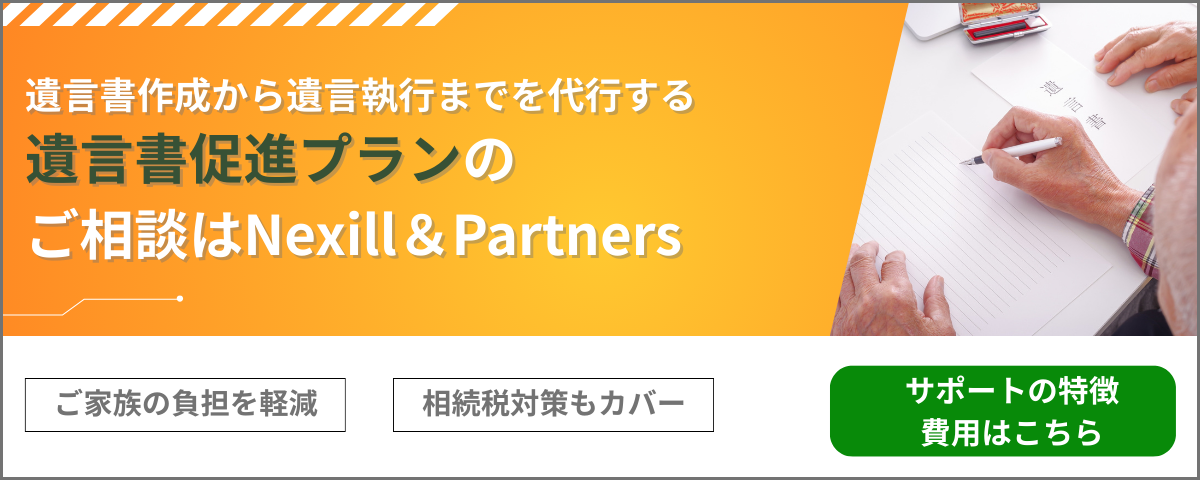相続が発生し、遺言書に「不動産は長男に相続させる」と書かれていて、さらに遺言執行者も指名されていた場合──「遺言執行者がいれば、自分たちは何もせずに登記も全て進めてもらえるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
確かに、遺言執行者には一定の法的権限がありますが、相続登記を“完全に一人で”進められるかどうかはケースによって異なります。
本記事では、遺言執行者が相続登記に関与できる範囲・できないこと・相続人側に必要な手続、さらには遺言執行者が自身での対応が難しい際の対応策まで、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。
1. そもそも遺言執行者とは何か?遺言執行者がいることで何が変わるのか?
遺言執行者とは、被相続人の遺言内容を実現するために選任された人物であり、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、遺言の内容によっては、相続人の協力を得ずに執行者単独で手続ができるケースがあります。
たとえば、「長男に財産を遺贈する」という内容であれば、執行者は長男の委任や印鑑証明なしに不動産の登記申請を進めることが可能です。
しかし、相続内容によっては、遺言執行者だけでは完結できない手続も存在します。
特に「相続させる」と明記されている場合には注意が必要です(この点は後述します)。
2. 遺言執行者が単独で相続登記を行うことはできるのか?
遺言執行者が相続登記を進めるにあたって、常に「遺言執行者だけで登記申請ができる」とは限りません。
実際の運用では、登記申請の主体や添付書類の性質によって、相続人の協力や委任が必要となる場面も多く存在します。
2-1. 遺言執行者が単独で登記申請できる代表的ケース
以下のようなケースでは、原則として遺言執行者が単独で所有権移転登記を申請することができます。
遺言執行者が単独で登記申請ができる代表例
- 遺言の内容が「遺贈」であることが明確に書かれている
- 遺言執行者が有効に就任している(辞任・欠格でない)
- 登記原因証明情報に遺言書と執行者の署名で足りる
- 相続人に異議がなく、他に利害関係人も存在しない
遺言書の文言としては、「遺言者は、下記不動産を次男〇〇に遺贈する。遺言執行者として〇〇〇〇を指定する。」というような記載であれば、遺言執行者は相続人や受遺者の委任状・印鑑証明なしで、単独で登記を行うことが可能です。
2-2. 相続人の協力が必要なケース(単独での登記不可)
以下のような事情がある場合には、遺言執行者のみでの登記申請は困難です。
ケース1:「相続させる」旨の文言がある場合
たとえば、
「本件不動産は長男に相続させる」という遺言は、法律上「遺贈」ではなく「指定相続」とみなされます。
この場合、相続人本人が登記申請人となる必要があり、遺言執行者は登記を代理できません。
ケース2:共有で相続させる内容の遺言
「土地は長男と次男が2分の1ずつ相続する」
このような場合、共有者それぞれが登記申請人となる必要があるため、遺言執行者が一方的に登記することはできません。
ケース3:登記官が受遺者の同意や補足書類を求める場合
たとえ遺贈であっても、登記官の判断により、
- 受遺者の印鑑証明書や意思確認書
- 遺産目録の補足説明
- 執行者の登記権限確認書類
などを追加で求められるケースもあります。
このような場合には、受遺者(相続人を含む)の協力が不可欠です。
3. 遺言執行者が登記申請を行う際の実務上のポイント
3-1. 登記原因証明情報には遺言執行者が署名する
登記申請には「登記原因証明情報」と呼ばれる書類が必要です。
これは、「この名義変更が何に基づいて行われるのか」を証明するもので、通常は遺言書の写し+執行者の署名(+受遺者の同意書など)が必要になります。
遺贈による登記申請の場合、次の3点が登記原因証明情報として求められ、これらが適切に整っていれば、法務局で登記申請が受理されるのが一般的です。
- 遺言書の写し(自筆証書または公正証書)
- 執行者の署名・押印
- 名義変更の根拠が遺贈であることと、その発生日を示す記載
3-2. 相続関係説明図・評価証明書などの添付書類の用意も遺言執行者が行う
遺言執行者が登記申請を行う場合でも、相続人自身が登記申請を行う際に必要となる書類は提出が必須となるため、登記を行う責任を担う遺言執行者は、これらの資料も自ら準備・収集することが原則とされています。
ただし、執行者単独での収集が難しい場合には相続人に協力を依頼したうえで必要書類の取り付けを進めることとなります。
4. 遺言執行者が複数指定されている場合の注意点
遺言執行者は1名とは限らず、複数人を共同で指定することも可能です。
実際、公正証書遺言の作成時などに「〇〇と△△を遺言執行者に指定する」と記載されていることがあります。
複数の執行者が存在する場合、その役割分担や手続の進め方には特有の注意点があります。
4-1. 登記実務における共同執行者の取扱い
不動産登記申請において遺言執行者が複数いる場合、原則として共同して手続を行う必要があります。
つまり、
- 登記原因証明情報への共同署名
- 登記申請書への連名
- 司法書士への委任が必要な場合も、複数執行者の連名委任が必要
といった手続になります。
また、法務局によっては「共同執行者の一部のみが申請した場合、他の執行者からの委任状を求める」など、形式面で厳格な対応を取ることもあるため、事前に確認が必要です。
4-2. 遺言執行者の間で意見が分かれたときの処理は?
共同遺言執行者間で判断が分かれた場合、誰が優先して意思決定できるかは法律上明確に定まっていません。
このため、
- 遺言書に「〇〇が主たる執行者とする」と明示されている場合はその指示に従う
- 明確な指示がなければ、相互協議によって意思統一を図る
- 意見が一致せず執行が停滞する場合には、家庭裁判所に対処を求める(職務執行の許可・変更・解任など)
といった対応が求められます。
執行者間でのトラブルや意思疎通の齟齬は、相続人全体の混乱につながりやすいため、初期段階での役割分担や協力体制を整えることが重要です。
5. 自分が遺言執行者として指定されているが対応できない場合はどうしたらよいか?
5-1. 遺言執行者を辞任する
まず前提として、遺言執行者に選ばれたとしても、必ずしもその職務を受け入れなければならないわけではありません。
ご自身が遺言執行者に指名されていた場合でも、「相続のことはわからない」「専門的なやり取りが不安」と感じる方は少なくありません。
民法上、遺言執行者は就任を拒否する自由があり、就任後もやむを得ない理由があれば辞任が可能です。
辞任を希望する場合は、
2. 家庭裁判所に「辞任の許可」を申し立てる
などの方法が取れます。
特に、利害対立が懸念される相続人の一人が遺言執行者に指名されているケースでは、中立性を確保する観点からも辞任が検討されることがあります。
補足:執行者が辞任し、後任も選任されなかった場合はどうなる?
遺言執行者が辞任し、かつ新たな執行者も選任しなかった場合は、遺言内容の実現に必要な手続を、相続人全員が協力して行うことになります。
ただし、この方法が可能かどうかは、遺言の内容や実行すべき手続の性質によって異なります。
相続人で進められるケース
- 遺言が「相続人に相続させる」内容であれば、登記や銀行手続は相続人自身で行うことが可能です。
- 遺言執行者が不要な類型の遺言であれば、相続人による実行でも問題は生じません。
相続人では実行が難しいケース
- 遺贈(特に第三者への遺贈)が含まれている場合は、遺言執行者の存在が法的に必要とされる場面が多く、相続人だけでは登記などの手続が進められないこともあります。
- 遺留分への配慮、寄付、信託設定など、法律解釈や中立的対応が必要な内容が含まれている場合には、専門家による執行が望ましいとされます。
また、相続人間に意見の不一致や利害対立がある場合、執行者不在のまま進めると、かえって紛争が激化するリスクも否定できません。
そのため、執行者の辞任後も遺言の内容が未了である場合には、必要に応じて家庭裁判所に後任の執行者選任を申し立てることが望ましいといえます。
5-2. 弁護士を遺言執行者に選任し直す
自分だと遺言執行が難しい場合は、ご自身の代わりに弁護士などの専門家を遺言執行者として選任し直すという選択肢もあります。
遺言執行者の選任の申立ては相続人のうち1人からの申立てで可能で、家庭裁判所に申立てを行うことで弁護士などの専門職を新しく遺言執行者として就けることができます。
弁護士を遺言執行者につけるメリット
弁護士が遺言執行者になることで、以下のようなメリットもあるほか、ご自身の負担も減らすことが可能です。
- 法律的な問題を適切に処理できる
- 相続人同士の感情的対立に巻き込まれず、中立的に進行できる
- 書類整備や通知業務を代理で対応でき、負担軽減につながる
注意点:遺言の文言や相続人の同意によっては再選任が難しいことも
遺言書の中で「特定の人物のみを執行者とする」などの限定的記載がある場合や、相続人間に深刻な対立がある場合には、新たな執行者の選任がスムーズにいかないこともあります。
また、弁護士を遺言執行者につけることで、弁護士報酬が発生する点には留意が必要です(報酬の金額や支払方法は、必ず事前に確認をされてください)。
6. 関連:不動産以外の相続財産に対する執行者の権限とは?
ここまで主に「不動産の相続登記」に焦点を当ててきましたが、実際の相続手続では、預貯金、株式、保険金、動産、賃貸借契約など、多様な財産についての執行手続が求められます。
不動産の相続登記以外の相続手続について、遺言執行者の方で何がどこまでできるのかについても少しだけご説明します。
6-1. 遺言執行者単独で預貯金・株式・保険などの名義変更は可能か?
遺言で「遺贈する」と指定された財産であれば、遺言執行者はその名義変更手続を単独で行う権限を有します。
たとえば、
- 銀行口座の名義変更または解約
- 証券口座の名義移転・売却
- 保険金の請求(受取人が被相続人名義の場合)
などは、遺言執行者の職務範囲に含まれます。
実務上は金融機関・証券会社ごとに必要書類や様式が異なり、執行者の本人確認・印鑑証明・遺言書の原本提出などが求められるため、事前に必要書類の確認が不可欠です。
6-2. 執行者が金融機関とやり取りする際の注意点
先ほどもお伝えしたように、銀行や証券会社では、執行者が単独で手続を行うためには、執行者としての資格確認書類の提出が必要となるのが通常です。
一般的に求められる書類としては、以下のようなものがあります。
- 遺言書(公正証書または検認済の自筆証書)
- 執行者の就任を証明する書面(家庭裁判所の選任通知書など)
- 執行者の印鑑証明書・本人確認書類
- 相続関係説明図や戸籍謄本一式
加えて、財産の種類や処分方法によっては相続人全員の同意書を求められることもあるため、必要に応じて相続人に協力を依頼の上で相続手続を進めることとなります。
6-3. 税務署・市役所での手続は遺言執行者でできるのか?
税務署(相続税申告)の場合
相続税の申告は、各相続人が個別に行う義務があるものであり、遺言執行者が代理して行うことはできません。
申告書の署名・提出は、あくまで財産を取得した相続人自身、または正式に委任された税理士が行う必要があります。
そのため、遺言執行者の立場では、次のような「補助的業務」に限られます。
- 相続財産の目録作成・資料整理
- 税理士との橋渡し(委任状の収集、相続人への連絡)
- 財産内容・取得者の確認と税理士への共有
- 相続人が申告を怠らないよう事前の周知
つまり、申告そのものを代理することはできませんが、実務を円滑に進めるための支援的役割を担うことは可能です。
市役所(名義変更・行政通知等)の場合
不動産以外にも、軽自動車や家屋課税台帳の所有者変更、国民健康保険・介護保険の手続などが発生することがあります。
これらは被相続人死亡後の届出義務として相続人に課せられるものですが、執行者が代理人として関与できるケースもあります。
ただし、相続人本人の個人情報に関わる手続については、原則として相続人本人またはその法定代理人(成年後見人など)でなければ申請できない場合がありますので、その点には留意が必要です。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言執行者が相続人本人の場合、自分のための登記も単独で進められますか?
はい、可能です。 自分が遺言執行者に指定されており、かつ遺言で「自分に遺贈する」旨が明記されている場合には、遺言執行者として自己に対して登記申請を行うことが認められます。なお、遺言書の文言に「相続させる」と書かれている場合は、登記実務上は「相続人本人として登記する」扱いとなるため、遺言執行者という立場は登記の可否に影響しません。
Q2. 遺言書が2通見つかりました。遺言執行者としてどう対応すればいいですか?
まず、2通の遺言書が両方とも有効な形式で作成されていた場合(例:いずれも自筆証書遺言/公正証書遺言)、遺言の効力は「日付が新しいもの」が優先されます。 ただし、旧い遺言書の中に新しいものと矛盾しない内容があれば、その部分が引き継がれる可能性もあります。 執行者としては、遺言書の内容・形式・日付のすべてを確認したうえで、どちらが優先されるかを法的に判断する必要があります。ご自身のみでの判断に自信がない場合は、弁護士に相談をされてください。
なお、ご自宅で保管されていた自筆証書遺言の場合は開封の前に検認手続を忘れずに実施するように注意が必要です。
Q3. 遺言執行者が財産目録を作成しない・見せてくれない場合、どうすればいいですか?
民法上、遺言執行者は就任後「遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付または閲覧させる義務」があります。 そのため、執行者が説明責任を果たしていない場合、相続人は内容証明郵便などで正式に開示請求を行うことができます。 それでも対応しない場合は、家庭裁判所に対して「遺言執行者の解任」を申し立てることも検討されますので、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、弁護士・司法書士・税理士が在籍のうえで社内連携し、遺言執行から登記・税務・交渉対応までを一括で支援する体制を整えています。
遺言執行についてご不安な点やお困りごとがございましたら、まずは一度ご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。