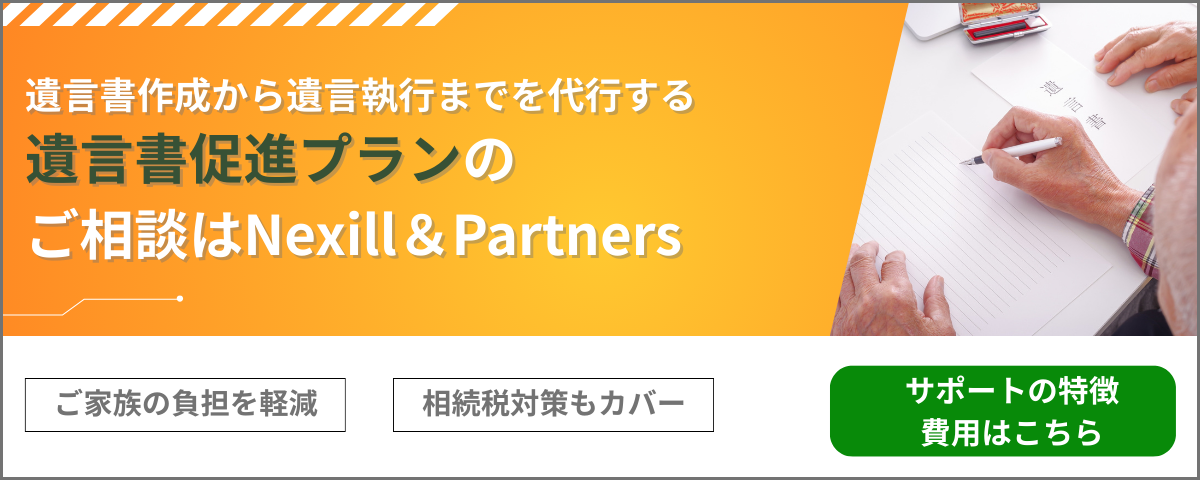相続手続の現場では「遺言書はあるけれど、遺言執行者が指定されていない」という状況が少なくありません。では、遺言執行者がいない場合、誰が相続手続を進めるのでしょうか。この記事では、遺言執行者がいない場合の相続の進め方、実務上の注意点など、弁護士の立場から分かりやすく解説します。
1. 遺言執行者がいないと相続手続はできないのか?
遺言書が存在していても、「遺言執行者」が明示されていないケースは珍しくありません。
まず結論からお伝えすると、遺言執行者がいない場合でも、遺言書の内容は有効です。ただし、実際の相続手続においては、関係者の協力が必要不可欠であり、場合によっては家庭裁判所を利用して遺言執行者を選任したほうがスムーズに進むこともあります。
2. そもそも遺言執行者ってどんな役割?いないと困る理由
遺言執行者とは、遺言書の内容を法的・実務的に実現(執行)するために選ばれる人のことです。民法でその法的地位や権限が定められており、
遺言執行者として選ばれた人には、次のような役割や権限が認められています。
遺言執行者の役割・権限の例
- 相続財産を把握・管理し、必要に応じて保全する
- 各種名義変更や登記、預金の払戻しなどの手続を代理して進める
- 相続人の廃除や認知など、遺言による身分行為を申立てる
- 不動産登記や金融機関の相続手続に必要な書類を作成・提出する
上記を見てもらうと気づくかもしれませんが、遺言執行者がいることで、相続人全員の署名・押印が不要な場面が増えるのです。
たとえば、ある遺言書に「自宅不動産を長男Aに相続させる」と書かれていたとします。この場合、遺言執行者がいる場合といない場合では以下のように相続の手順が変わります。
- 遺言執行者が指定されていれば、執行者が単独で相続登記を申請できます。
- いなければ、法務局は「相続人全員の同意書・印鑑証明書」を求めてきます。
また、銀行などの金融機関でも、遺言執行者がいるかどうかで必要書類が大きく変わります。こちらも、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者のみで払戻し手続が可能ですが、いない場合は相続人全員の押印・書類提出が必要となることが一般的です。
つまり、遺言執行者がいないと、
- 相続人間の協力が不可欠になる
- 1人でも非協力な相続人がいると手続が止まる
- 受遺者(相続人以外に遺産を受け取る人)が自力で手続を進められない
といった事態に直面しやすくなります。
特に、相続人が複数いて疎遠・不仲であるケースや、遠方・海外に住んでいるケースでは、遺言執行者がいないことで実務が立ち行かなくなるリスクが飛躍的に高まります。
3. 遺言執行者がいない場合の3つの進め方
では、実際に「遺言執行者がいない遺言書」に直面した場合、どうすればよいのでしょうか?
ここでは、現実的な3つの進め方をご紹介します。
3-1. パターン①:相続人全員で協力して進める
最もオーソドックスな方法は、相続人全員が協力し合って手続きを進めるというものです。
この場合は、不動産登記や預貯金の解約、証券の移管などすべての相続手続を行う際に、相続人全員の印鑑証明書などの必要書類を提出しなければなりません。
なお、不動産登記においては、状況によって簡易な遺産分割協議書を提出するよう法務局から求められる場合もあります。その場合は、遺産分割協議書を作成の上で相続人全員の署名押印が必要となってきます。
この方法は、相続人全員の関係が良好で、速やかに必要書類を揃えることができる場合に有効です。
ただし、1人でも押印を拒否したり、連絡が取れなかったりすると相続手続全体が止まってしまうため、注意が必要です。
3-2. パターン②:家庭裁判所で遺言執行者の選任を申し立てる
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に申し立てることで、後から遺言執行者を選任してもらうことができます。
この制度は、民法に基づき、遺言の内容を実現するために必要と判断されるときに、相続人や受遺者などの利害関係人が申し立てを行い、裁判所が適切な人物を選任するものです。
相続人の“単独”申立てが可能
実務上よく誤解されがちですが、この遺言執行者の選任申立ては、相続人全員の同意が必要ではありません。
相続人のうち誰か一人でも単独で申し立てることが可能です。
たとえば、
- 「他の相続人と連絡が取れない」
- 「一部の相続人が手続に非協力的」
- 「自分(申立人)が受遺者で、相続人とは関係が薄い」
といったケースでも、申立てを妨げることはありません。
この“単独で進められる”という点は、相続実務において非常に重要です。
相続人の関係性が希薄だったり、対立していたりするケースでは、全員の合意形成が困難なことが多くなりますが、遺言執行者を選任することで、たとえ相続人の一部が非協力的な場合でも、相続手続を単独で実行できるようになるため、現実的な解決手段となります。
ただし注意:相続人に「意思能力がない人」「行方不明者」がいる場合
先ほどお伝えした通り、遺言執行者の選任申立て自体は特定の相続人が単独で行うことが可能ですが、相続人の中に以下のようなケースがある場合には、申立て後の審理段階で追加対応が必要になることがあります。
相続人に認知症等の意思無能力者がいる場合
- 審理において「遺言の執行がその相続人に不利益を及ぼす可能性がある」と家庭裁判所が判断した場合、成年後見人や特別代理人の選任を先に行うよう指示される可能性があります。
- 特に、包括遺贈などで相続人の相続分が減るような場合には、慎重な審理がなされる傾向があります。
相続人に行方不明者がいる場合
- 申立て自体は可能ですが、選任後の遺言執行の実務(たとえば財産の処分など)で、不在者財産管理人の選任が別途必要になることがあります。
- 登記や金融機関での名義変更を進める際に手続が止まるのを防ぐため、早期にその可能性を見越しておくことが重要です。
このように、申立てのハードル自体は高くないものの、相続人の状況次第では“周辺手続”が派生してくる可能性があることに注意が必要です。
どんな人を遺言執行者に選べるのか?
遺言執行者選任申立てを行う際は、「この人を遺言執行者にしてください」という希望(候補者)を申し立てることができます。
- 親族(長男、兄弟など)
- 相続に詳しい第三者(弁護士・司法書士など)
申立人の希望を基に、家庭裁判所が「信頼性」「利害関係」「遺言内容との適合性」などを総合的に勘案し、適任と判断された人物を選任します。
特に相続人間で対立がある、または財産が多岐にわたる場合には、専門家を執行者に選任しておくことで、公正かつ円滑な執行が可能となります。
3-3. パターン③:包括遺贈の場合、受遺者が単独で対応できるケースも
遺言の内容によっては、遺言執行者がいなくても、受遺者が単独で一部の相続手続を行えるケースがあります。
特に該当するのが「包括遺贈」と呼ばれる類型です。
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、遺言によって「相続財産の○分の1を遺贈する」といったように、
財産全体の一定割合や、すべての財産をまとめて受け取るよう指定する遺贈のことをいいます。
たとえば次のような文言です。
- 「遺産の3分の1を〇〇に遺贈する」
- 「全財産を〇〇に遺贈する」
このような包括的な遺贈を受けた人は、法律上、相続人に準じた立場として扱われます。そのため、一定の手続については、受遺者が単独で行える場合があるという特徴があります。
ただし、実務では完全に単独で手続できるとは限らない
包括遺贈があったとしても、実際の金融機関や法務局の運用では、相続人の同意書や補足資料を求められるケースも少なくありません。
たとえば以下のような場合です。
- 不動産登記で法務局が他の相続人の関与を確認しようとする
- 金融機関が内部規定により、他の相続人の印鑑証明や同意書を求めるケースがある
- 他に財産を取得する相続人や受遺者がいて、分配が交錯する場合
特に、受遺者が相続人でない(たとえば友人や孫など)場合や、遺言書の文言自体が包括遺贈として明確かつ具体的でない場合(財産の内容が特定されていないor一部しか書かれていない、財産の分配割合が明記されていないなど)には単独手続ができるかどうかを事前に弁護士に確認することが望ましいでしょう。
4. 【実務編】手続ごとに見る進め方と注意点
遺言執行者がいない状態で相続手続を進める場合、個別に対処法を理解しておくことが重要です。
以下では、特によく取り扱われる主要な手続きについて、実務的な流れと注意点を整理します。
4-1. 不動産:相続登記・遺贈登記の実務フロー
不動産は、法務局で「相続登記(もしくは遺贈登記)」を行うことで名義を変更します。
遺言執行者がいない場合は、以下の点に注意が必要です。
① 相続人が取得する場合:相続登記
たとえば遺言書に「○○市所在の土地は長男に相続させる」と記載されている場合、これは「相続分の指定」とされ、長男は相続人として相続登記を単独で申請できます。
必要書類の例(公正証書遺言の場合)
- 登記申請書
- 公正証書遺言の謄本または正本
- 被相続人の除籍謄本(出生〜死亡)
- 被相続人の住民票除票(本籍の記載があるもの)
- 申請人(相続人)の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税(不動産評価額×0.4%)
→この場合、他の相続人の同意や印鑑証明は不要です。
自筆証書遺言の場合
- 上記に加えて、家庭裁判所による「検認済証明書(または検認調書謄本)」が必要です。
② 受遺者が取得する場合:遺贈登記
一方、遺言書に「○○市所在の土地を△△に遺贈する」と書かれており、△△が法定相続人でない場合(例:友人、孫など)は、特定遺贈に基づく遺贈登記となります。
この場合、受遺者は単独で登記申請ができず、相続人の協力が必要になるのが原則です。
よく求められる追加書類
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の同意書または遺産分割協議書(簡易形式)
- 相続関係説明図(登記官による家系図的確認のため)
受遺者が相続手続を進める際は、法務局の運用上、「遺言に基づいて登記をすることについて相続人が異議を唱えていない」ことの確認書類が求められる場合があります。
特定遺贈で執行者がいないケースでは、特にこの点がネックとなるため、事前に弁護士や司法書士に相談をされてください。
4-2. 預貯金:金融機関とのやり取り・必要書類
金融機関での相続手続は、銀行や金融機関ごとに異なる独自のルールがあります。
遺言執行者がいない場合、一般的には遺言書と戸籍書類に加え、相続人全員の関与を示す以下の書類が必要とされます。
よく求められる書類
- 遺言書(原本または検認済みの写し)
- 被相続人の戸籍(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 金融機関所定の相続手続依頼書
- 相続人全員の同意書(形式は銀行により異なる)
特に、受遺者が相続人でない場合(第三者への遺贈)は、原則として相続人全員の同意が必要とされることが多いため注意が必要です。
4-3. 株式・証券:証券会社での手続
有価証券の名義変更や移管は、証券会社の相続センター経由での対応が一般的です。こちらも実務上は預金と似ており、以下の点に注意が必要です。
- 遺言執行者がいない場合、受遺者単独での手続が認められないケースが多い
- 相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要とされることが標準
- 移管先の証券会社を指定する「受入書類」などの調整も必要
遺言執行者がいない場合は、相続人全員の協力の下での相続手続が原則となることに留意が必要です。
4-4. 生命保険・貸金庫・会員権などの対応
上記以外での資産や手続についても、以下のような注意点があります。
生命保険
保険金の受取人が明示されている場合は相続財産ではなく、遺言書に関係なく支払われるのが原則。
→ ただし、受取人が「相続人」など包括的指定の場合は実務上の確認が必要。
貸金庫
開扉に相続人全員の同意が求められることも。
→ 遺言執行者がいれば単独で可能な場合があるが、そうでない場合は相続人単独での手続きが困難な場面も多い。
会員権やゴルフ会員権
名義変更にクラブ側の承認が必要。遺言があっても、実質的に相続人の同意が前提となるケースが多い。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言執行者がいないと、すべての手続が止まってしまうのでしょうか?
いいえ、遺言執行者がいない場合でも、遺言自体は有効であり、すべての手続が不可能になるわけではありません。 ただし、相続人や受遺者が単独で動けるかどうかは、遺言の内容や財産の種類、そして金融機関や法務局の運用方針に左右されます。 相続人全員の協力が得られるなら進められる手続も多いですが、1人でも非協力的な相続人がいると停滞しやすいため、その場合は遺言執行者の選任が有効な対応策となります。
Q2. 自筆証書遺言を法務局に保管していても、遺言執行者がいなければ意味がないのでしょうか?
法務局に保管されている自筆証書遺言は、「検認不要」という大きなメリットがあります。 ただし、執行者が指定されていない場合、相続実務の進行には他の相続人の協力が必要になる点は変わりません。 遺言内容が明確であり、財産が限定的で相続人全員の協力が得られる場合にはスムーズに進むこともありますが、そうでない場合は遺言執行者の存在が手続の円滑化に繋がります。
Q3. 遺言書に「遺言執行者をAに委ねる」と記載されている場合、その人は自動的に執行者になるのですか?
原則として、遺言書に「遺言執行者に指名する」と明記されている場合、その人は就任の意思を確認したうえで正式な遺言執行者として就任できます。 ただし、指定された人が就任を辞退することもできますし、就任しないまま相続が進むと、結局「遺言執行者がいない状態」になります。 このような場合には、家庭裁判所に対して新たな遺言執行者の選任を申し立てることができます。
Q4. 遺言執行者がいない場合、葬儀や納骨などの死後事務は誰がやるのですか?
葬儀・火葬・納骨など、いわゆる「死後事務」は相続手続とは区別される分野であり、法律上は誰がやるかが定まっていません。 一般的には、配偶者や同居していた子などが実施しますが、あらかじめ「死後事務委任契約」などで第三者に依頼しておくことも可能です。 当事務所では、相続対策の一環として生前の死後事務契約や任意後見契約、財産管理委任契約の整備も承っております。
遺言執行者がいない場合でも、遺言書の内容が無効になるわけではありませんが、とくに相続人間の協力が難しい、財産が多岐にわたる、受遺者が第三者である、といったケースでは、相続手続を進めるうえでは専門的な視点が不可欠です。
遺言の内容を円滑に実現するためにも、まずはご自身の状況を整理し、早めに弁護士にご相談ください。