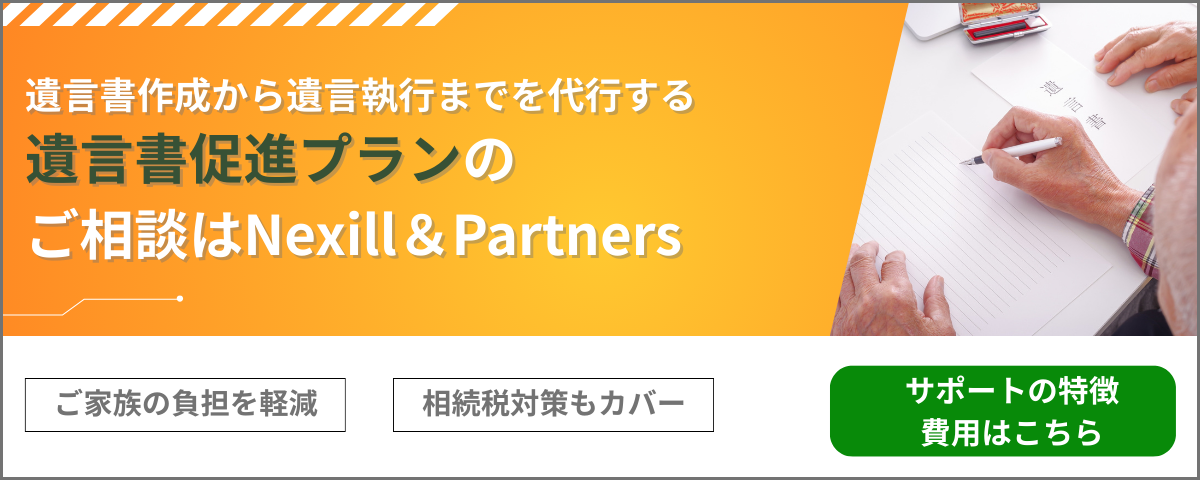遺言執行を行う際には、財産目録を正しく作成することが重要です。
とくに相続人や利害関係人への開示義務の問題は、トラブルを避けるためにも見落とせません。
しかし、どこまで詳しく書くべきなのか、開示義務にはどのような規定があるのか……実際に遺言執行を進める際、わからないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、遺言執行において「財産目録」作成がなぜ必要か、具体的な作成手順やポイント、さらに開示義務の位置づけなどをわかりやすく解説します。
あわせて、当事務所の専門家がどのようにサポートしているかもご紹介いたします。
ぜひご一読いただき、スムーズな遺言執行・相続手続きにお役立てください。
1.遺言執行で財産目録が必要な理由とは
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するという重要な役割を担います。
実際には、不動産や預貯金、有価証券など被相続人(亡くなった方)のあらゆる相続財産を確認し、それがどれだけの価額なのか、誰にどれだけ配分するのかという点を把握・管理しなければなりません。
そこで不可欠になるのが、財産目録の作成です。
1-1. 財産目録で利害関係を明確化する
財産目録は、被相続人の財産をリストアップし、その価額や所在などを整理した書面です。
たとえば、
- 不動産の地番や家屋番号、固定資産評価額など
- 銀行預金の口座、残高や満期日など
- 株式や投資信託など有価証券の銘柄、数量、評価額
- 借入金・ローンといったマイナス財産の内容
といった情報を一元的にまとめます。
これによって、相続人や利害関係人の皆さんは「どんな資産が存在するのか」を視覚的に確認しやすくなりますし、遺言書に記載された内容と財産の実態との整合性を検証することが可能になります。
1-2. 財産目録の作成・交付は遺言執行者の義務として定められている
法律上、遺言執行者は相続人や受遺者に対して財産目録を作成して交付する義務があるとされています。
民法上の規定では、遺言執行者に選任された人は、就任後すみやかに相続人全員へ財産目録を交付することが義務づけられています(民法1011条など)。
これは、遺言執行が不透明にならないよう、相続人の権利を守るための重要な仕組みです。
2.財産目録に記載する内容
財産目録には、被相続人の生前に所有していた**あらゆる財産(プラスの財産・マイナスの財産)**を列挙します。具体的には次のような情報を整理しましょう。
2-1. 不動産、預金、有価証券などのプラス財産
- 不動産:土地・建物の所在地、地番・家屋番号、固定資産評価額、登記情報など
- 預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、残高、定期預金なら満期日など
- 株式・投資信託・債券:銘柄、数量、評価額や発行体情報
- 動産・貴金属類:価値のある宝石や美術品など
- 生命保険金:受取人や保険金額(ただし「みなし相続財産」として扱われるケースもあり)
2-2. 借入金などマイナス財産の記載
相続税の計算や相続人間の協議においては、被相続人が抱えていた負債(マイナスの財産)も重要です。
たとえば、
- 借入金:金融機関からの借入、消費者金融、クレジットカードの残高など
- 未払金・未払税金:医療費や電気料金の未払分、所得税・住民税等の残額
- 連帯保証債務:被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合
こうした負債についても、財産目録にきちんと掲載しておく必要があります。
相続税の観点では、この負債による債務控除が認められる場合もあるため、大切な情報です。
3.財産目録の開示義務とは
民法1011条1項などで「遺言執行者は、就職後遅滞なく、遺言の内容を示し、各相続人に対して財産目録を作成し交付する」と定められているように、遺言執行者は財産目録の作成と開示の義務があります。
3-1. 開示義務を怠った場合のリスク
遺言執行者が正当な理由なく開示を怠った場合、遺言執行者と相続人の間での信頼関係にも関わってきます。
不信感が高まると、解任請求や相続紛争に発展しかねませんので、適切に対応を行いましょう。
3-2. 開示された財産目録に対する相続人の対応
相続人や利害関係人は、財産目録の内容を受け取ったら間違いや漏れがないかを確認し、疑問点があれば遺言執行者に質問できます。
もし、ご自身が開示を受ける立場だった場合、内容に納得できなければ記載内容についてきちんと説明を求めることや、専門家に相談の上で内容の再精査をしてもらうようにしましょう。
4.財産目録作成の進め方と注意点
財産目録を作成する際には、まず遺言書に記載された財産をベースにしながら、被相続人のあらゆる資産・負債を漏れなく洗い出します。
作業の流れは以下のようなイメージです。
- 1.戸籍や遺言書の確認:相続人の範囲と遺言内容を把握
- 2.金融機関・証券会社などの調査:被相続人が取引していた口座の残高証明、解約手続き等
- 3.不動産の登記情報収集:法務局で登記情報を取得
- 4.負債状況の調査:ローン契約書やカード利用履歴などを確認
- 5.書面化:取得した情報を一覧表にまとめ、評価額を記載
4-1. 遺言書の内容と整合性を確認する
遺言書に「長男に土地を相続させる」と書かれていても、その土地が複数筆に分かれていたり、建物が複数存在したりするケースは珍しくありません。
財産目録で不動産を精査し、遺言書の記載内容と完全に合致しているかを入念にチェックすることが必要です。
また、遺言書に書かれていない財産がこの段階で判明することもあり、結果として再度遺産分割協議が必要になるケースもあります。
4-2. 相続人や利害関係人への対応
財産目録を作成し終えたら、速やかに相続人全員へ交付します。
交付後、相続人から「株式の数が合わない」「財産に不足があるのではないか」などの紛争の火種になりそうな疑問が出ることがあります。
迅速かつ正確に回答するためにも、必要であれば専門家によるサポートを得るのが望ましいでしょう。
4-3.遺産にデジタル資産や海外財産が含まれる場合の注意点
近年は、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)や海外の預金口座、不動産といった「従来とは異なる形態の財産」も増えています。
このようなデジタル資産や国外資産を含む場合、遺言執行で作成する財産目録に記載する手順や調査手法がさらに複雑化するため注意が必要です。
たとえば、暗号資産の保有状況や残高は、取引所の口座データや専用ウォレットのアクセス権限を確認しないと正確な額面を把握しにくいほか、海外不動産や海外口座を相続財産として取り扱うには、現地の法規制や税制にも注意を払わなければなりません。
こうした多様な財産が含まれる場合は、専門家に相談の上で進められることをお勧めします。
5.本コラムのまとめ:財産目録を正しく作成して、円滑な遺言執行を
遺言執行において財産目録の作成は、遺言執行者の義務でもあり、適切な作成を実施しなければ相続人同士の紛争リスクにもつながってしまいます。
専門的な知識や法的な見解が必要な局面も多いため、弁護士など専門家の関与が大きなメリットをもたらします。
当事務所は、相続分野に注力する弁護士を中心に、税理士・司法書士も在籍するワンストップ体制で、遺言執行に伴う財産目録の作成から相続税申告・不動産登記まで一貫してサポート可能です。
「どのような財産をリストアップすればよいのか」「遺言の内容と矛盾しないか」「相続人への説明方法がわからない」といったお悩みがあれば、お早めにご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。