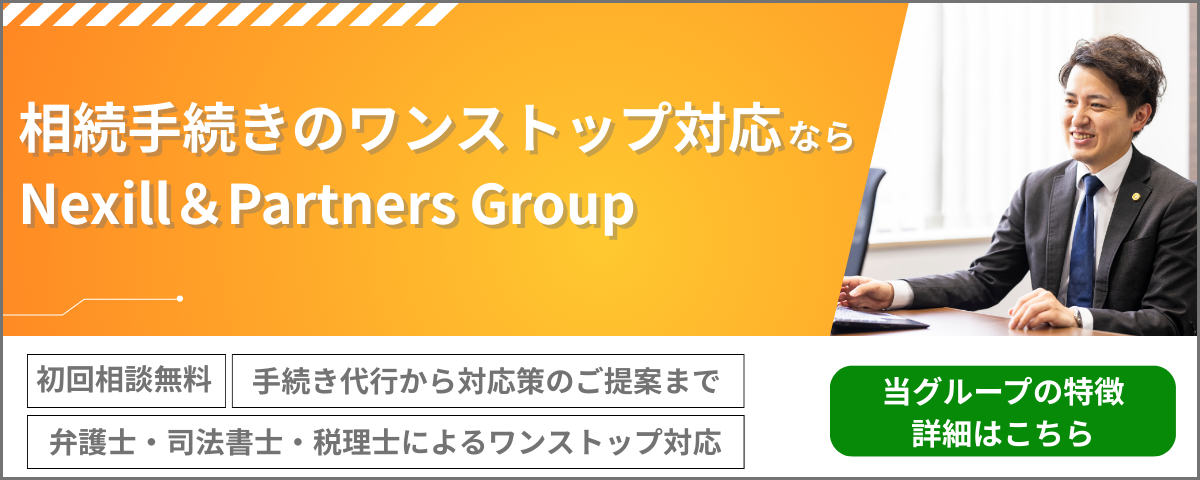相続が発生した際、誰が相続人になるのかを正確に把握するために相続人調査を行う必要がありますが、被相続人の家族構成が複雑であるケースや、戸籍の内容がわかりにくいケースでは、相続人調査を自分で行うよりも、法律の専門家に依頼したいと考える方が増えています。
とはいえ、「弁護士に相続人調査を依頼したら費用はいくらかかるの?」「他の専門家と何が違うの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、弁護士に相続人調査を依頼する場合の費用相場や他士業との違い、弁護士に依頼すべきケースについて、わかりやすく解説します。
1. 相続人調査とは?その目的と重要性
1-1. 相続人調査の必要性とタイミング
相続人調査とは、「亡くなった方(被相続人)に法的な相続権を持つ人物が誰か」を調べる作業のことです。 通常は、相続が発生した後に行われますが、遺言書を作成する際や生前の相続対策を検討するタイミングでも必要になるケースがあります。
1-2. どのような情報を調べるのか
相続人調査の主な進め方としては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)の収集をしたうえで、そこからさらに辿りながら相続人の現在の戸籍謄本の取得を行っていきます。
この際、相続人の中で既に死亡している人がいた場合は、その更に下の相続人(代襲相続人)まで辿る必要があります。
また、被相続人が認知している子がいたり、養子縁組をしていたりする場合は、そこも含めて戸籍謄本の収集を行っていきます。
2. 弁護士に依頼する場合の費用相場
2-1. 相続人調査にかかる弁護士費用とは?
弁護士に相続人調査を依頼する場合、費用は以下のような内訳が一般的です。
| 費用項目 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 着手金 | 調査開始時に必要な基本費用 | 5万〜15万円程度 |
| 実費 | 戸籍謄本取得、郵送料、交通費など | 1万円〜2万円程度 |
弁護士に相続人調査を依頼する場合、費用は「着手金」と「実費」が中心となります。一般的な目安としては、調査対象人数や複雑さにもよりますが、着手金はおおよそ5万円〜15万円前後となるケースが多く、戸籍の取り寄せや住民票取得にかかる実費が1万円〜2万円程度発生します。
弁護士事務所によっては、取得する戸籍の通数によって金額を設定しているところもありますので、実際の費用については、ご相談に行かれた際に確認をされてみられてください。
また、弁護士がそのまま遺産分割協議や遺留分侵害対応にも関与する場合は、追加費用が必要となることもありますが、最初の相談時に全体像と費用構成を提示する事務所も増えています。当事務所でも、初回相談は無料で対応し、費用感を提示のうえでご納得いただいた場合にのみ着手いたします。
2-2. 他士業との費用比較(司法書士・行政書士)
以下は、弁護士以外の士業との費用相場比較です。
| 士業 | 調査以外での対応可能業務範囲 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人調査+法的アドバイス+紛争対応 | 5万〜15万円+実費 | 裁判所対応含めて、紛争リスク部分まで対応可能 |
| 司法書士 | 相続人調査+相続登記 | 3万〜8万円程度 | 相続登記はできるが、裁判所対応は不可 |
| 行政書士 | 相続人調査のみ | 2万〜5万円程度 | 相続人調査以外の業務対応はできない |
費用だけで見れば行政書士や司法書士が弁護士よりも安価な場合もありますが、その後の手続がどこまで必要かという部分を考慮すると、最初から弁護士に依頼しておいた方が良いケースもあります。依頼先を選ぶ際は、対応範囲や法的リスク対応の可否を総合的に判断することが大切です。
3. 弁護士に依頼すべきケースとメリット
以下のようなケースでは、初めから弁護士に依頼することが適切です。
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 他の相続人から遺留分侵害請求の予告がされている
- 将来的に遺産分割協議で揉める可能性がある/すでに揉めている
このように、法律的な争点が含まれる可能性がある場合、弁護士以外の士業では対応が難しく、結果的に後から弁護士に再度依頼をしなければならないケースが見受けられます。
最初から弁護士に調査を依頼しておくことで、その後の法的対応についてもそのまま継続して対応ができますので、将来的に弁護士が関わりそうな場合は相続人調査も含めて弁護士へご相談されることをお勧めします。
4. 相続人調査を実施した結果:行方不明の相続人がいる場合の対応
4-1. 調査をしても相続人の所在が不明なときはどうなるのか
相続人調査を行った結果、戸籍上では相続人であることが確認できたものの、その人物の現在の居所がわからない、長年音信不通で連絡手段がない――こうした「行方不明の相続人」がいるケースは、実務上も決して珍しくありません。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹やその子どもが相続人となる代襲相続のケースでは、日頃の交流がないため所在が不明という事態が起きやすいです。 相続手続、とりわけ遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて有効とされるため、行方不明者が1人でも含まれていると、協議を成立させることができません。
この場合は、所在不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加する人(不在者財産管理人)を選任する手続きが必要となります。
4-2. 弁護士による不在者財産管理人選任の実務対応とメリット
不在者財産管理人を選任してもらうには、裁判所に対して戸籍・住民票除票・調査報告などの資料を整え、「この相続人は実在するが、現在の所在が確認できない」ことを示す必要があります。相続人調査から継続して弁護士に依頼することで、これらの申立書類の準備から提出、裁判所とのやり取り、必要に応じての期日対応についてもそのまま一貫して任せることができます。
なお、申立代理人となった弁護士が不在者財産管理人に就任すること自体は可能ですが、その場合は他の相続人の代理人を兼ねることはできませんので注意が必要です。
5. 相続人調査を実施した結果:認知症や判断能力の低下がある相続人への対応
5-1. 判断能力に不安がある相続人が含まれていた場合のリスク
相続人調査の過程で、相続人の一部に高齢や病気などにより意思能力に不安のある方が含まれていることが判明するケースがあります。
この場合、本人の意思が確認できない状態で遺産分割協議を行うことはできないため、成年後見人を立てたうえで遺産分割協議を実施しなければなりません。
5-2. 弁護士による成年後見制度の活用と実務対応
認知症などで判断能力を欠いている相続人がいる場合、遺産分割協議を有効に行うには、家庭裁判所に「成年後見人の選任申立て」を行う必要があります。成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加し、本人にとって不利益にならない内容であれば協議に合意することができます。
弁護士に相続人調査を依頼していれば、判断能力に問題のある相続人がいた場合、そのまま成年後見申立ての準備・提出を一括で任せることも可能です。
なお、申立人の弁護士がそのまま後見人に就任することもできますが、その場合、後見人は他の相続人の代理人を兼ねることはできない点には注意が必要です。
6. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 相続人調査はどのくらいの期間がかかりますか?
A. 戸籍の取得に要する日数や相続人の人数・構成によって異なりますが、一般的には1か月程度が目安です。ただし、被相続人の転籍が多い場合や、結婚・離婚が複数回にわたっている、代襲相続が発生している、などの複雑な場合であれば、数か月かかることもあります。
Q2. 調査後に判明した相続人が遺産分割協議に応じてくれない場合はどうなりますか?
A. 当事者同士での遺産協議が成立しない場合には、弁護士を入れたうえで再度協議を行うか、家庭裁判所での調停や審判の手続に移行することを検討する段階になります。相続人調査の後、遺産分割協議まで一括して弁護士に依頼することもできますので、まずは弁護士に対応方針を相談されてみてください。
Q3. 弁護士と行政書士・司法書士の違いは何ですか?
A. 行政書士・司法書士も戸籍の収集や相続人の特定を行うことは可能ですが、依頼者の代理人としての交渉や裁判所での対応を行えるのは弁護士のみです。特に行方不明者や認知症の相続人がいる場合など、調査結果を受けて法的対応が必要になるケースでは、最初から弁護士に依頼することで手戻りが防げます。
Q4. 相続人調査だけ依頼することもできますか?
A. はい、可能です。当事務所では「相続人調査のみ」のご依頼もお受けしています。ただし、相続人調査は手続全体の入口であるため、相続登記や相続税申告、遺産分割協議など、その後の対応まで見越してご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、必要に応じて、司法書士・税理士と連携して一括対応できる体制を整えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。