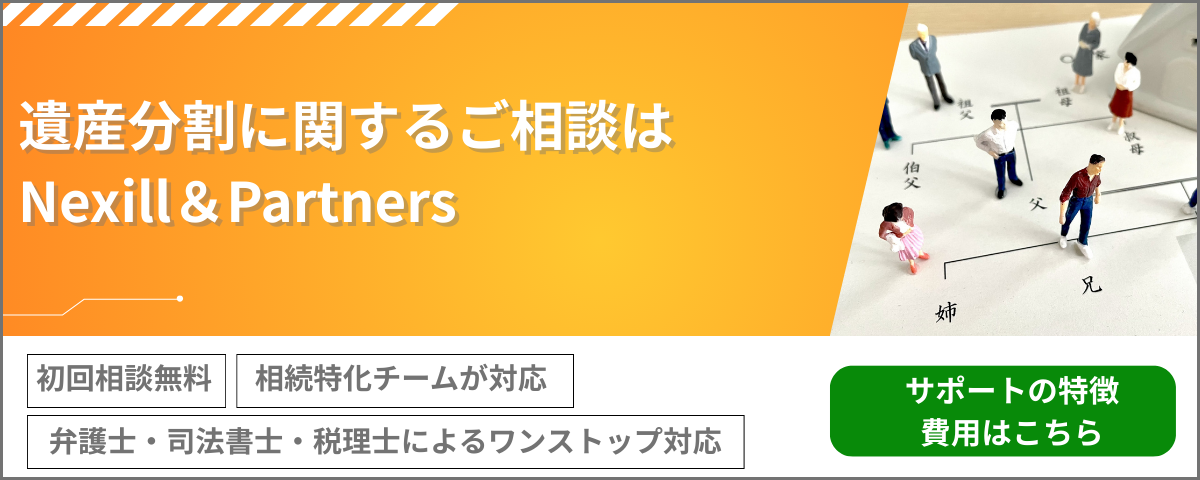相続手続を進める中で突然「遺産分割調停申立書」が家庭裁判所から届いた——。
こうした状況に直面すると、多くの方は「どう対応すればいいのか」「調停に出なければいけないのか」「弁護士に依頼すべきか」といった不安や戸惑いを抱えます。
この記事では、調停を申し立てられた場合にまず何をすべきか、調停の手続の流れ、相手方とのやり取りの注意点、そして弁護士への相談の必要性まで、相続実務に詳しい専門家の視点からわかりやすく解説します。
1. 突然の「調停申立書」──どうすればいい?
1-1. 家庭裁判所から届く書類の中身と意味
調停申立書が届くときは、通常以下のような書類が同封されています。
- 遺産分割調停申立書
- 調停期日呼出状
- 申立人の主張書面(財産目録や主張書付き)
- 進行に関する案内文や問い合わせ先
この時点であなたは「相手方(被申立人)」という立場に置かれており、家庭裁判所の調停手続に関与する必要がある状態です。
1-2. 応答期限・出席義務・無視した場合のリスク
「知らなかったふりをすればいいのでは?」「面倒だから調停なんて行きたくない」そう考えて放置してしまう方も中にはいらっしゃいますが、それは非常に危険です。
遺産分割調停は、民事訴訟と異なり、初回の期日は“出頭義務”はないものの、2回目以降は正当な理由なく欠席すると「調停不成立→審判(裁判所の判断)」へ進む可能性があります。
さらに、出席せずに手続が進んだ場合、自分にとって不利な内容で調停が成立することもあるため、書類が届いたら“すぐに専門家に相談”することが極めて重要です。
1-3. よくある「誤解」と心構え
遺産分割調停と聞くと、「揉め事が大ごとになった」というイメージを持つ方も多いですが、
実際には、「相続人同士で協議ができなかったので、裁判所に間に入ってもらう」ための制度です。
必ずしも相手方が敵意を持っているとは限りませんし、調停を通じて冷静な話し合いが可能になるケースも多くあります。
とはいえ、法的手続である以上、自身の主張や資料を整理せずに参加するのは非常に危険です。
まずは「調停=裁判所を通じて話し合いをする制度」であることを理解したうえで、
自分の立場を明確にし、適切に準備を進めることが求められます。
2. なぜ調停を申し立てられるのか?
2-1. 調停が申し立てられる背景パターン
調停が申し立てられる状況には、大きく2つのタイプがあります。
1つは明らかな対立や協議の行き詰まりがあるケース。もう1つは、本人としては「特に揉めていないつもり」でも、他の相続人が“協議困難”と感じて申し立てをしたケースです。
以下は、調停申立てをする背景としてよく見られる場面です。このような状況では、自分たちだけでの話し合いでは埒があかないと感じ、家庭裁判所という第三者を介した解決を図ろうとするケースが多くなります。
調停を申し立てられる背景の一例
- 相続財産の分け方についての話し合いが平行線になっている
- 一部の相続人が協議に応じない、連絡が取れない
- 生前贈与や預金の使い込み(使途不明金)があると疑われている
- 「遺産の範囲」「不動産の評価」「共有の解消」などで意見が合わない
- 自分の知らない間に手続が進められていたことに相手が不信感を持っている
2-2. 調停を申し立てられたら自分が不利になるのか?
調停の申立書を受け取ると、多くの方が「自分は責められているのではないか」「訴えられたのか」といった不安や戸惑いを抱かれます。
しかし、調停における「申立人」と「相手方」という区分は、対立構造や勝敗を前提としたものではなく、あくまで当事者の役割を整理するための呼称にすぎません。
家庭裁判所での手続を円滑に進めるために形式上定められているものであり、どちらかが有利・不利になるということではありません。
むしろ、調停は「相続人同士で話し合いがまとまらない」「連絡が取れない」など、協議が困難になった場面で、公平な第三者(裁判官・調停委員)が間に入って冷静な解決を図ることを目的とした制度です。
そのため、相手方として調停に呼び出されたからといって、必要以上に委縮したり、防御的になりすぎたりする必要はありません。
大切なのは、自身の立場や主張をしっかり整理し、適切な準備をした上で臨むことです。
調停では、相手の主張だけが先行しないよう、自分の考えや希望をきちんと伝えることが重要です。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談し、代理人として資料や説明の組み立てをサポートしてもらうことが、結果的にご自身の権利を守ることにつながります。
3. 遺産分割調停の全体像:どんな手続が行われるか
3-1. 家庭裁判所での進行イメージ
遺産分割調停は、家庭裁判所で行われます。手続としては以下のような流れで進行します。
2. 裁判官と調停委員が交互に当事者の意見を聴取
3. 財産の内容、分割案、主張の確認
4. 当事者の合意を目指し、何度か期日が設けられる
5. 合意に至れば調停成立、不成立の場合は審判へ移行
調停は原則として非公開で行われ、法廷のような公開の場ではなく、会議室に近い雰囲気の部屋で双方の当事者が交互に呼ばれて話をする形式です。
3-2. 裁判官と調停委員の役割・雰囲気
調停には、1人の裁判官と、2名の調停委員が関与します。
- 裁判官は調停の法的な枠組みを監督し、調停が不成立だった場合にはその後の審判を担当します。
- 調停委員は当事者の事情を丁寧に聞き取り、公平な立場から意見調整や現実的な分割案の提示を行います。
雰囲気としては、厳しい詰問というよりは「和やかに、冷静に話を聞く」姿勢で進められることが一般的です。
3-3. 申立人とのやりとりと注意点
調停では、申立人(相手方)と直接対話する機会は原則としてありません。
各当事者が交互に調停室に呼ばれ、調停委員に対して自分の意見を述べる形式です(対面方式ではない)。
しかし、相手方の主張に対して反論や説明が必要な場面も多く、その場で正確に伝える準備が求められます。
調停での発言は記録として残るため、感情的に言い返す、何が言いたいかが分からないような主張は調停委員の心証を悪くすることもあります。
そのため、特に感情的対立がある相続人間での調停では、弁護士の同席が大きな安心材料となります。
4. 調停が成立した場合・不成立だった場合の違い
調停に出席し、話し合いがまとまった場合と、合意に至らなかった場合では、その後の法的・実務的な対応が大きく変わってきます。
4-1. 調停で話し合いがまとまった場合(調停成立)
遺産分割調停が成立すると、調停内で合意した内容を記載した調停調書という正式な裁判所の文書が作成されます。
この調書は、判決と同様の効力を持ち、不動産の登記変更や預貯金の解約など実際の相続手続の際に「相続人間の合意内容を証明する書類」として利用できるほか、調書内に金銭の支払義務が明記されている場合などでは、債務名義として強制執行の根拠にもなります。
たとえば、調停調書に「長男は次男に対し、〇〇銀行の預金から500万円を支払うものとする」といった内容が記載されている場合、長男が履行しないときは、調書を根拠に預金の差押え(強制執行)を行うことも可能です。
4-2. 調停で話し合いがまとまらなかった場合(調停不成立)
調停はあくまで話し合いによる解決を目的としているため、合意に至らなかった場合は、調停は不成立として、家庭裁判所の判断によって遺産の分け方を決定する審判手続へと移行します。
審判では、各当事者の主張と証拠をもとに、裁判官が遺産分割の内容を決定します。
審判の特徴
- 最終的には裁判所が遺産分割の内容を決める
- 家庭の事情や関係性よりも、法的な構成・証拠重視で進む
- 納得できない場合は抗告(上級審への不服申立て)となり、さらに時間とコストがかかる
なお、調停が不成立になった場合でも、すぐに審判へ進まず、弁護士を介した任意交渉によって再び合意が成立するケースも多くあります。
このように、調停が一度不成立となっても「交渉の余地が完全になくなるわけではない」ことは知っておいたほうがよいポイントといえるでしょう。
5. 弁護士に依頼すべきか?判断ポイント
遺産分割調停は「裁判所の話し合いの場」ではありますが、法律的な主張や証拠が重要な役割を果たす正式な法的手続です。
そのため、弁護士に依頼するべきかどうかについて悩まれる方も多いですが、状況に応じては「早めに依頼する」ことが極めて重要です。
5-1. 単独で調停に臨むリスク
調停は和解の場ですが、実際には次のようなリスクが潜んでいます。
- 相手の主張が過剰・事実と異なる内容で書かれていても、即座に適切に反論できない
- 適切な分割案や法的根拠を知らないまま交渉に臨むと、不利な条件で合意してしまう
- 感情的に揺さぶられ、重要な判断を焦って下してしまう
特に、相手側に弁護士がついている場合、法的な対話力や交渉力に差が出るため、結果として一方的な展開になりやすいというのが実務の現実です。
5-2. 弁護士に依頼することで得られる支援
弁護士に依頼すると、以下のような支援が受けられます。
- 相手の主張内容の法的妥当性を判断
- 客観的な資料整理と事前戦略の立案
- 調停当日の同席・代弁による精神的負担の軽減
- 相続法・判例に基づく適正な分割案の提示
- 交渉や合意形成の過程における適切な主導・主張
とくに、「寄与分・特別受益」「預金の使途不明金」など、法的争点を含む相続には弁護士の支援が不可欠です。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 調停は1回で終わりますか?
基本的に、遺産分割調停は1回で終わることはほとんどありません。 財産の全容が確認できていないケースや、各相続人の希望・主張に開きがある場合、3回〜5回程度(半年〜1年程度)にわたって続くことも珍しくありません。 ただし、当事者間である程度方向性が一致している場合や、弁護士が早期から介入して論点整理がなされている場合には、初回や2回目で調停成立する例もあります。
Q2. 遠方に住んでいても、裁判所に行かないといけませんか?
原則として、調停期日には相手方として家庭裁判所に出頭する義務があります。 しかし、遠方に住んでいる・高齢で移動が困難などの理由がある場合、事前に裁判所へ相談することで、電話会議やオンライン調停に切り替えてもらえる可能性があります。 また、弁護士に依頼していれば、本人の代わりに出頭・主張してもらうことも可能です。 身体的・地理的に難しい場合は、対応方法を早めに検討しておくことが大切です。
Q3. 他の相続人が財産を勝手に使っていたのですが、調停で取り戻せますか?
調停の中で、他の相続人による預金の引き出し・使途不明金などが問題となることはよくあります。 この場合、「使った金額をどう評価するか」や「遺産に戻すべきかどうか」は、調停の中で交渉・判断されます。 事実関係が不明確な場合でも、通帳記録・領収書・生前の介護状況などを整理し、調停委員に丁寧に説明することが重要です。 また、必要であれば弁護士を通じて「不当利得返還請求」や「使途不明金の開示請求」などを別途提起することも検討されます。
Q4. 相続放棄をした人が調停に入っているのですが、これは正しいのでしょうか?
原則として、相続放棄をした人は「初めから相続人でなかったもの」として扱われるため、遺産分割の当事者にはなりません。 そのため、調停に参加する資格はないはずですが、家庭裁判所側が事情を把握しておらず、誤って通知が届くケースもあります。 このような場合には、速やかに「相続放棄申述受理通知書」などを提出して手続から外してもらう必要があります。
Q5. 調停では、どのように相続財産が評価されるのですか?
調停では、不動産については固定資産評価額や路線価、時価査定(不動産業者の意見)などを用いて評価されるのが一般的です。 預金・株式などは残高や時価、解約返戻金などが基準になりますが、明確な評価基準が定まっていない場合は、当事者間で合意できる評価方法を探すことになります。 また、調停委員が独自に評価額を提示することはなく、各自が提出した資料に基づいて調整が進められるため、事前準備と専門家の関与が重要です。
7. まとめ:調停を申し立てられたら、まず冷静に・そして早めに動く
遺産分割調停を申し立てられたとき、大切なのは過剰に構えすぎないこと、そして無視せず、きちんと対応することです。
特に、申立人側にすでに代理人として弁護士が就いている場合は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、ご自身の権利と希望を的確に守ることができます。
当事務所では、弁護士に加え、税理士・司法書士が在籍しており、相続に関するあらゆる課題をワンストップで対応しています。
具体的には、以下のような支援が可能です。
- 遺産分割調停の代理人としての出廷・交渉
- 相続税の申告
- 相続登記の実行や名義変更
- 自社株や事業承継が絡む複雑な案件にも対応可能
調停を含めた遺産分割協議の代理から、税務や登記を含めて遺産分割内容が確定した後の相続手続までを一体で支援できますので、まずは一度ご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。