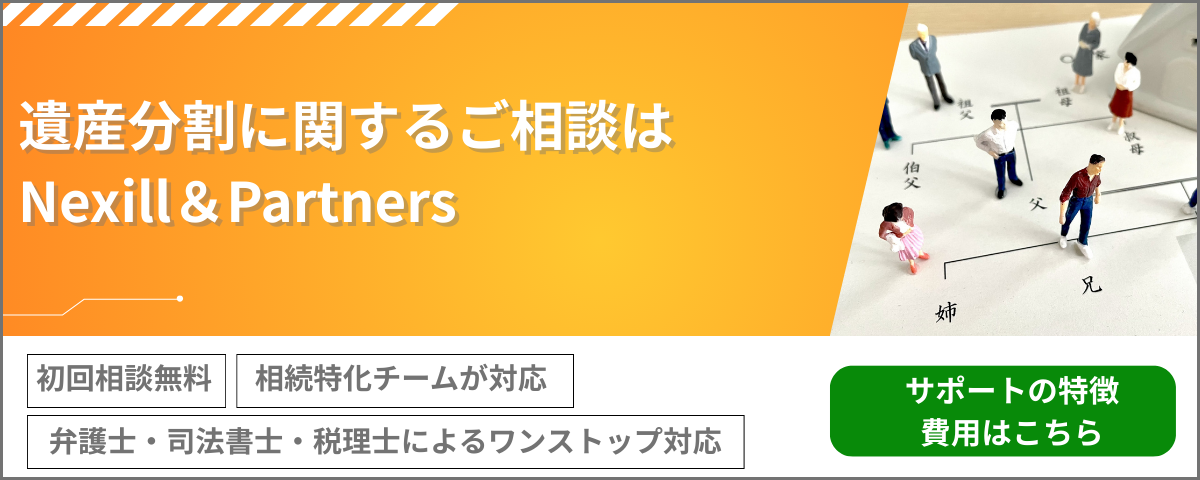相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の判断に委ねる「遺産分割審判」という手続へ進むことになります。
では、裁判所はどのような基準で遺産分割の内容を判断するのでしょうか?
法定相続分はどのように扱われるのでしょうか?
この記事では、審判に至るまでの経緯、審判の流れ、判断基準、審判後の実務対応までを、相続実務に強い弁護士の視点からわかりやすく解説します。
1. 遺産分割審判とは?|協議・調停との違い
1-1. 遺産分割における3つの段階:協議 → 調停 → 審判
遺産分割の解決方法には、大きく分けて以下の3つがあります。
協議
相続人全員の話し合いによる合意形成
調停
家庭裁判所の調停委員を交えての話し合い(合意ベース)
審判
調停を経ても合意できなかった場合に、裁判所が一方的に内容を決定
このように、審判は協議や調停を経た“最後の分割手段”であり、もはや相続人間の任意の合意が困難であることが前提となります。
1-2. 審判は「合意が成立しなかった場合の最終手続」
審判は、家庭裁判所が一方的に遺産分割の内容を決める手続であり、相続人の希望や感情とは無関係に法的基準と客観的事情に基づいて判断が下されます。
そのため、調停とは異なり、各相続人の主観的な納得感が得られにくいという側面があります。
また、審判によって確定した内容には法的拘束力があり、不服がある場合でも原則として裁判所の判断に従う必要がある点に注意が必要です。
このように、調停と審判は目的も進行方法も大きく異なるため、手続きの違いをよく理解しておくことが、相続トラブルをこじらせないためにも重要です。
2. 審判に至るまでの手続の流れ
先ほどもお伝えした通り、遺産分割審判は、あくまで「話し合いではどうしても解決できなかった場合の最後の手段」です。
そのため、いきなり審判を申し立てることはできず、原則として段階を経たうえで審判手続に進む必要があります。
ここでは、協議から調停、そして審判へと移行するまでの流れと注意点を解説します。
2-1. 相続人間の話し合いが第一段階|協議が基本
遺産分割は、まずは相続人全員の合意によって進める協議が基本です。
当事者同士が話し合い、全員の合意をもとに遺産分割協議書を作成することで、法的にも有効な遺産分割が成立します。
しかし、相続人間の関係性が悪い、財産の分け方に大きな意見の食い違いがある、特別受益や寄与分を巡って対立しているといった事情があると、協議ではまとまらないケースも少なくありません。
そうした場合、次のステップである家庭裁判所の調停手続に進むことになります。
2-2. 協議が不成立の場合は調停へ|調停前置主義の原則
相続人同士で遺産の分け方について話し合った結果、どうしても意見が一致しない場合は、遺産分割調停の申立てを行います。
この調停手続は、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進め、合意を目指す制度です。
協議が長期化しても解決の見込みがないときには、早い段階で調停を申し立てることが、結果的に手続きを前進させる近道になることもあります。
なお、日本の家庭裁判手続では、「調停前置主義」が採用されており、遺産分割審判を申し立てるには、原則として事前に調停を経る必要があります。
話し合いがまとまらないから裁判所に決めてもらいたいと思っても、初めから審判の手続をとることはできないので注意が必要です。
調停の段階で遺産分割方法の合意が成立すれば、合意内容での調停調書にて内容が法的に確定し、審判に進まずに遺産分割は完了します。
2-3. 調停が不成立だった場合に審判へ移行
調停手続においても相続人間の合意が成立しない場合、家庭裁判所は調停不成立を宣言し、そのまま「審判」手続に移行します。
このとき、相続人から改めて審判を申し立てる必要はなく、調停が終了したことを受けて自動的に審判手続が開始されます。
家庭裁判所では、調停不成立後すぐに審判書作成に移行するとは限らず、以下のような理由から「審判手続に形式的に移行したうえで、実質的に調停的な進行を続ける」ことがあります。
- 財産目録や評価書などの資料が未提出で、心証形成が困難
- 相続人の一部に態度未定者がいる
- 解決直前まで話し合いが進んでいた経緯がある
- 争点整理のために追って意見書を提出する約束がある
このような場合、家庭裁判所は「一応調停は打ち切った」という形式をとりつつ、関係当事者に追加的な提出や最終的な協議を求める姿勢を取ることがあるのです。
3. 遺産分割審判の基本的な流れ
3-1. 調停不成立から審判への自動移行
調停で合意が得られなかった場合、家庭裁判所は「調停不成立」として調書に記録し、そのまま同じ事件として審判手続に移行します。
新たな申立てをする必要はなく、調停期日までに提出された書類や主張内容は、原則としてそのまま審判手続にも引き継がれます。
3-2. 審判期日の指定と呼出し
審判に移行した後、裁判所から相続人に対して「審判期日」が指定され、出頭の呼出し状が送られます。
この期日では、以下のような内容が進められます。
- 書面の提出状況や争点の整理
- 財産目録の確認と修正
- 裁判所が心証を形成するための事実関係の確認
- 分割案に対する各相続人の意見聴取
調停段階でも一通り主張は済んでいる状態ではありますが、整理されていない点を中心に、審判では改めて主張や証拠の明確化が求められることが一般的です。
3-3. 分割案の調整と最終意見聴取
審判といっても、裁判所はできる限り相続人間の実情や希望を考慮しながら、実行可能な分割案を作成しようと努めます。
そのため、裁判官から以下のような意見照会や提案がなされることがあります。
- 「この案で合意できる余地はあるか」
- 「この財産は別の分け方で分割することを検討できないか」
- 「この主張を維持する場合、その主張を裏付ける具体的な証拠をどの程度提出できるか」
なお、このような意見聴取や最終調整が行われても、相続人全員の合意が得られない場合には、最終的には裁判所の判断により、法的拘束力を持つ審判が下されることになります。
3-4. 審判書の送達と確定のタイミング
裁判所が分割内容を決定すると、「遺産分割審判書」が作成され、各相続人に送達されます。
この審判書には、以下の事項が記載されています。
- 誰がどの財産を取得するか
- 分割に伴い発生する代償金の支払い内容
- 申立ての一部却下など(必要に応じて)
相続人がこの審判内容に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告(上級裁判所への不服申立て)を行うことができます。
抗告がなければ、2週間経過後に審判が確定し、法的効力を持つことになります。
3-5. 審判確定後の注意点
審判が確定すると、分割内容に基づいて各種相続手続(登記、預金解約、税申告など)を進めることができます。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 審判内容が現実的に履行困難な場合(代償金が支払われない等)は、強制執行の検討が必要になることもある
- 審判確定後に財産の漏れが発覚した場合は、再度分割手続が必要
審判確定後、何らかの事情により審判で決まった内容が履行できない場合は、一度弁護士にご相談ください。
4. 審判における判断基準と法定相続分の扱い
4-1. 審判では「実質的公平」が重視される
遺産分割審判における最大のポイントは、形式的な平等(=法定相続分どおりの分割)に固執するのではなく、実質的な公平を重視するという点です。
これは、民法906条に明記された「遺産分割の基本的考慮事項」に基づき、裁判所が以下の観点を総合的に踏まえて判断することを意味します。
- 各相続人の年齢・職業・生活状況
- 遺産の種類や性質(不動産、株式、事業資産など)
- 特別受益(生前贈与等)や寄与分の有無
- 共有や共同相続による不都合の有無
- 分割後の管理・利用・処分の実現可能性
裁判所が審判内容を決定する際も、まずは法定相続分に基づいた概算的な分割案を土台としたうえで、そこから上記観点を踏まえた調整を加えて実質的公平を図るという手順を踏みます。
したがって、法定相続分は無視されるものではありませんが、そのまま機械的に適用されるわけではなく、個別具体的な事情によって大きく修正される可能性があるという理解が必要です。
4-2. 希望どおりにならない場合もある|審判の性質に留意
審判は「最終的な法的決定」であるため、相続人の希望や感情よりも、法律と証拠に基づいた判断が優先されます。
そのため、次のようなケースでは相続人の希望がそのまま通らないこともあります。
- 「どうしても自宅を相続したい」と希望していたが、他の相続人の相続分を侵害するため採用されなかった
- 「生前に被相続人を手伝ってきたから遺産を多めにほしい」と主張したが、証拠がなく寄与分としては認められなかった
- 不動産を複数人で共有したいと申し出たが、管理上不適切と判断され共有は却下された
このように、審判ではあくまで第三者である裁判所の視点から、遺産分割の内容を法的に決めるため、相続人個々の希望がすべて反映されるわけではないという現実を理解しておく必要があります。
5. 審判確定後に必要な相続手続と実務対応
遺産分割審判が確定すると、いよいよ具体的な相続手続きに移る段階に入ります。
この章では、審判確定後に相続人が行うべき代表的な各種手続きと、その際の注意点について解説します。
5-1. 不動産の名義変更(相続登記)の実施
審判により相続人が取得することとなった不動産については、審判書をもとに相続登記の申請を行います。
2024年4月の法改正により、相続登記は「相続を知った日から3年以内の申請義務」が課されるようになったため、遅延には注意が必要です。
相続登記に必要な主な書類
- 審判書および確定証明書
- 登記申請書(司法書士に依頼可)
- 固定資産評価証明書
- 法務局への登録免許税(課税価格の0.4%)の納付
必要であれば早期に司法書士に相談して、登記申請ミスや期限超過による過料の発生を防ぎましょう。
5-2. 預貯金・有価証券の名義変更と解約手続きの実務
審判で預貯金や証券などの金融資産について分割が命じられた場合には、確定した審判書をもとに、それぞれの金融機関で解約・名義変更の手続きを行います。
ただし、取得者が誰であるか、審判が確定しているかによって、手続きの進め方が大きく変わるため注意が必要です。
① 審判確定後は取得者本人が単独で手続可能
審判が確定している場合は、審判書に記載された取得者が単独で金融機関に対して払戻しや解約の申請を行うことが可能です。
このとき、以下の書類が必要になるのが一般的です。
- 審判書の正本または謄本
- 審判確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍(生存を確認するため)
金融機関によっては、独自の所定様式への記入が求められることもありますので、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。
② 投資信託や株式の名義変更・売却手続も注意が必要
相続財産の中に株式や投資信託が含まれている場合、証券会社を通じて名義変更または売却処理を行う必要があります。
この手続も原則は審判書に基づいて行いますが、以下の点に注意が必要です。
- 一部の証券会社では、審判書に「具体的にどの銘柄を誰が取得するか」が記載されていないと分割対応ができない場合がある
- 分割できない単元株や、分割に伴う価格評価・譲渡処理に時間がかかることもある
- 手続きには、証券会社所定の「相続手続請求書」「相続人全員の関係説明図」などが必要になる場合もある
そのため、審判の段階で株式や投資信託の分割方法が明確にされているか、または証券会社の対応可否を事前に確認しておくことが望まれます。
5-3. 相続税申告や修正申告が必要となるケースも
すでに未分割の状態で相続税申告を済ませていた場合は、審判により分割内容が確定したことで「更正の請求」や「修正申告」が必要になるケースがあります。
たとえば、
- 小規模宅地等の特例が適用可能になった → 更正の請求(税額減)
- 審判により相続財産の配分が変わった → 修正申告(税額増)
いずれも、審判確定後は速やかに税理士と相談し、相続税の申告内容が適切かを再確認することが重要です。
6. 遺産分割の審判に関連するよくある質問(FAQ)
Q1:遺産分割審判の内容に不満がある場合、やり直す方法はありますか?
A:審判書が届いた日から2週間以内であれば「即時抗告」という不服申立てが可能です。これは上級の高等裁判所に対し、原審判の取り消しや変更を求める制度です。ただし、即時抗告が認められるためには、法律や事実の明確な誤りがあることを具体的に主張する必要があります。単なる「納得いかない」では取り消しは難しいのが実情です。
Q2:審判で遺産を取得しても、負債の引き継ぎはありますか?
A:審判はあくまで「遺産(プラスの財産)」の分割手続です。負債(借金など)については民法の原則に基づき、法定相続分に応じて当然に相続人全員が分割で引き継ぐ形になります。つまり、審判で不動産だけを取得したからといって、負債から免れることにはなりません。負債が多い場合は、遺産分割を進める前に相続放棄などの判断をする必要がありますので、まずは弁護士に相談をされるようにしてください。
Q3:審判手続中に相続人が亡くなった場合はどうなりますか?
A:遺産分割審判の途中で相続人の1人が亡くなった場合、その人の法定相続人(いわゆる「次の相続人」)が当事者として手続きを承継することになります。
手続としては、以下のような対応が必要となるのが通常です。
- 承継人となる法定相続人の戸籍一式や相続関係図の提出
- 裁判所による承継確認のための「当事者変更の申出書」の提出
- 複数の承継人がいる場合には、代表者1名を選定するか、全員を共同当事者として関与させる
また、被承継人(亡くなった相続人)の主張や提出資料がすでに存在する場合、裁判所はその内容を引き継ぐかどうかについて、承継人に意向確認を行うことがあります。
出頭の要否や、書類の補正・訂正の要否はケースバイケースで、裁判所の判断によって柔軟に進められます。
なお、審判の内容が最終的に確定すれば、その取得分については被承継人ではなく、新たな承継人が取得することになります。
そのため、「誰が分割財産を受け取るのか」という最終的な帰属にも影響が及ぶ点に留意が必要です。
7. まとめ|遺産分割審判は最終手段。納得できる結果のために協議の段階から弁護士にご相談ください
遺産分割審判は、法定相続分を起点としながらも、特別受益や寄与分、財産の性質などを加味し、実質的な公平を目指して判断が下されます。
ただし、審判は証拠や法的主張が重視されるため、希望通りの結果が得られるとは限りません。
また、審判確定後には不動産登記、預貯金の名義変更、相続税の修正申告など多くの実務が待っています。
だからこそ、調停や審判に進む前の段階から、弁護士をはじめとする専門家に相談し、戦略的に準備を進めることが重要です。
当グループでは、弁護士・司法書士・税理士が在籍し、社内連携の上で相続問題にワンストップで対応できる体制を整えております。
遺産分割調停・審判の代理人としての対応から、調停・審判後の実際の相続手続まで、総合的にサポートを行っております。
「遺産分割の協議が進まずそのままになっている」「相続人間での調整が難しい」とお悩みの方は、まずは一度当事務所にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。