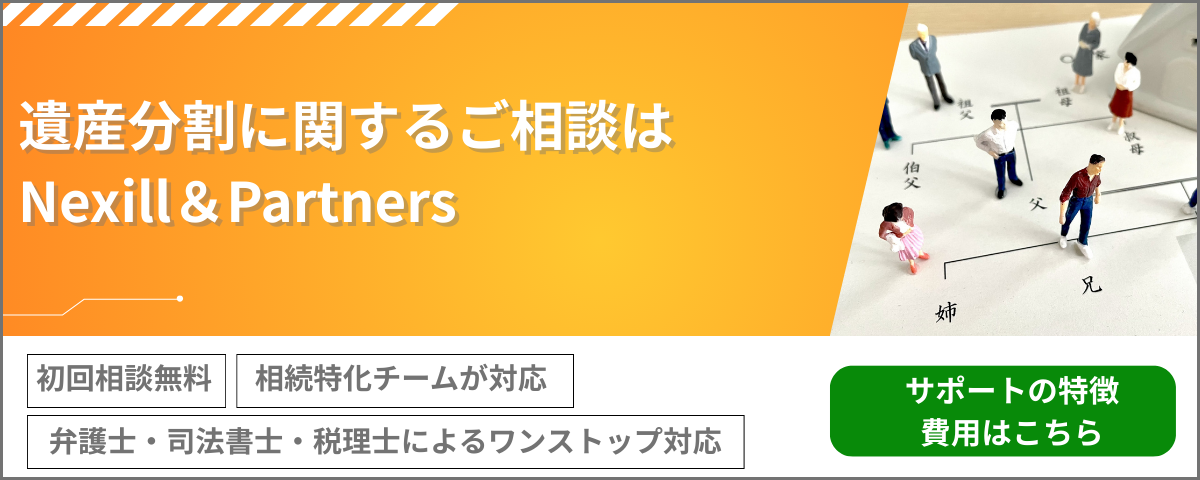相続と離婚——一見別々のライフイベントのようですが、実際の法律相談の現場では、これらが密接に関係していることが多くあります。特に、「相続で不動産や預貯金を得たが、その後離婚することになった」といった場合、「相続で得た財産も離婚時に財産分与しなければならないのか?」という疑問は、多くの方が抱える不安の一つです。本記事では、相続によって取得した財産は、離婚時にどこまで財産分与の対象となるのか、どのような例外的取扱いがあるのかなどを弁護士が解説します。
1. 離婚時の財産分与とは何か?
離婚にあたって行われる「財産分与」とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、原則として公平に分け合うための制度です。
財産分与には、大きく次の3つの目的があります。
① 清算的財産分与
夫婦が婚姻期間中に築いた財産を清算・分配するもの(最も一般的)。
② 扶養的財産分与
一方の生活が著しく困窮する場合に、扶養的な観点で一定の給付を行うもの。
③ 慰謝料的財産分与
離婚原因を作った配偶者に対する慰謝料の性質を含む分与。
このうち、今回のテーマである「相続財産は財産分与の対象になるのか」という問題は、主に①の清算的財産分与に関わります。
清算的財産分与の対象となるのは、
- 夫婦の一方または双方が、
- 婚姻中に、
- 協力して形成・維持した財産(共有財産)
です。
ここで重要なのが、財産が「夫婦の協力によって形成されたものかどうか」「婚姻期間中に取得されたものかどうか」です。これらの基準によって、財産分与の対象となるか否かが判断されます。
2. 相続財産の法的性質とは?
では、相続で取得した財産は、法律上どのような位置づけにあるのでしょうか?
民法上、相続財産は相続人固有の「特有財産」として扱われるのが原則です(民法762条1項)。特有財産とは、夫婦いずれかが婚姻前に有していた財産や、婚姻中であっても一方が相続や贈与によって単独で取得した財産のことを指します。
たとえば、夫が婚姻中に父親から不動産を相続した場合、この不動産はあくまで夫の特有財産であり、財産分与の対象とはならないのが基本的な考え方です。これは、夫婦の協力によって築かれたものではないため、共同財産とはみなされないという理屈です。
ただし、以下のような例外的な事情がある場合は、評価が分かれる可能性があります。
- 相続財産をもとに取得した別の財産(買い替えや改築など)
- 相続財産の管理・維持に配偶者が実質的に関与していた
- 相続財産から得られた収益(例:賃貸収入など)を夫婦共有財産として運用していた
このように、形式的には特有財産であっても、実質的な運用や形成経緯によっては、分与対象と判断される余地があるため、慎重な判断が求められます。
また、遺産分割前の状態(相続人全員が法定相続分に基づき共有している状態)においては、その持分が確定していないことも多く、離婚手続との関係では判断が難しくなる場面もあります。遺産分割が終わっていない場合は、「財産分与の対象になる/ならない」という結論すら出せないというのが実務的な対応です。
3. 相続財産が財産分与の対象になるかどうかの判断基準
相続財産が離婚時の財産分与の対象になるかどうかは、原則と例外を区別して考える必要があります。
まず原則として、婚姻中に相続した財産は「特有財産」であり、財産分与の対象には含まれないとされています(民法762条1項)。これは前章で述べたとおり、相続財産は夫婦の協力によって得たものではないためです。
しかし、実務においては以下のような事情があれば、例外的に分与の対象とされることがあります。
① 相続財産をもとに新たな財産を形成したケース
たとえば、妻が婚姻中に取得した相続財産を原資として、夫婦で新築住宅を建てた場合などです。この場合、住宅そのものは相続財産ではありませんが、「相続財産の影響を強く受けている」といえます。特に夫婦の共有名義で登記されている場合は、相続による取得分が事実上混在している可能性があり、分与対象に含めるか否かは争点になります。
② 相続財産の維持管理に配偶者が関与していたケース
たとえば、相続人が得た不動産を夫婦でリフォーム・維持しながら使用していた場合、「実質的には共有のような性質を帯びている」と主張されることがあります。このようなケースでは、名義は一方であっても、貢献度の大きさから部分的な分与が認められる可能性もあるため注意が必要です。
③ 相続財産によって生じた派生的な財産がある場合
相続した預金を元に運用益や利息が発生し、それが夫婦の生活費や貯蓄に組み込まれていた場合は、当初の相続財産とは別に形成された共有財産があると評価される余地があります。
このように、不動産や預貯金の名義がどちらか一方になっていても、それだけでは判断できないのが実務です。名義と実際の資金の出所、維持管理の状況、使用実態を総合的に見て、財産分与の対象に含めるか否かを裁判所が判断します。
なお、裁判所は、「形式的な取得原因(相続)」だけではなく、「婚姻中にどれだけ夫婦双方の協力があったか」「実質的な共有性があるかどうか」を重視する傾向があります。
そのため、「相続で取得した財産だから共有財産からは除外される」と安心するのは危険です。逆に、相手方が過剰に権利を主張してきた場合も、法的な根拠をもとに整理・判断することが求められます。
4. 遺産分割協議中・相続登記未了の不動産がある場合の注意点
相続財産を巡る手続きの途中で離婚問題が浮上すると、判断がより複雑になります。たとえば、「親が亡くなって相続が発生したが、遺産分割協議がまだ終わっていない」「不動産の登記も故人のまま」——このような状態で離婚協議に突入した場合、財産分与をどう扱うべきかは慎重な判断が必要です。
4-1. 遺産分割未了の場合、相続人の権利は“法定相続分に応じた共有”
この段階では、相続人全員が法定相続分に基づいて権利を持っている状態です。つまり、まだ「この人がこの土地を取得した」とは法的に確定していません。よって、離婚時点では分与対象の財産とするかどうかを明確に決めきれないケースがあります。
4-2. 持分相続であることを理由に財産分与を主張されるリスク
法定相続分に基づいて、不動産の一部が実質的に「持分」で取得されている状態であると、相手方配偶者から「これはあなたが婚姻中に得た財産だから分けるべきだ」と主張されることがあります。ただし、このような場合も、前提としては相続財産であり、法的には特有財産に分類されることが原則です。
4-3. 登記がないまま離婚調停に入ると、財産の評価が不安定に
調停で財産内容が不明確だと、調停委員会も適切な助言ができません。協議が不透明になると、結果として争いが長引く原因となり、双方にとって不利益です。
そのため、できる限り早めに
- 相続人間での分割協議を済ませておく
- 不動産については持分・名義の状態を明確にしておく
ことが望まれます。
5. 財産分与と相続税・贈与税の関係
離婚に伴う財産分与と、相続・贈与といった他の財産取得行為が重なるとき、税務上の取扱いにも注意が必要です。「相続財産を財産分与として渡したら、相手に贈与税がかかるのか?」「二重課税のような状態にならないか?」といった疑問がよく寄せられます。
5-1. 財産分与自体は原則非課税
まず基本として、離婚に伴う財産分与は原則として非課税です。(所得税・贈与税ともに)
これは、財産分与が民法上の権利に基づくものであり、あくまで婚姻中に形成した共有財産の清算であるためです。これは国税庁の公式見解でも明記されており、通常の財産分与であれば税金の心配をする必要はありません。
5-2. ただし「不相当に多額の分与」は贈与税の対象になることも
一方で注意すべきなのは、「財産分与」の名目であっても、分与額が不相当に多額である場合や、夫婦間の財産形成に見合わない一方的な財産移転がある場合には、税務署が「贈与」とみなす可能性があるという点です。
たとえば、総資産5000万円のうち4800万円を一方が受け取るような財産分与や、明らかに婚姻期間中の形成とは無関係な財産まで含めている場合には、贈与税の課税対象になる可能性があります。
形式的な名目だけで判断されるのではなく、分与の内容や背景、形成過程を税務署は実質的に見て判断するため、注意が必要です。
5-3. 相続財産を財産分与に使うときの注意点
相続で取得した財産を、離婚時の財産分与の中で相手に渡すこと自体は、理論上は可能です。
しかしこの場合、すでに相続税の対象となっていた財産を、さらに「財産分与」として相手に移転させる行為となるため、贈与税との関係で注意が必要です。
たとえば、妻が相続によって取得した不動産や預金を、離婚協議における財産分与の一環として夫に渡したとします。
このとき、形式上は「財産分与」として処理していても、税務署側が「実質的には贈与にあたるのではないか」と判断する可能性があります。
すると、相手方(元配偶者)に対して贈与税が課されてしまうおそれがあるのです。
しかも、妻が相続の際に相続税を支払っていた場合、その財産を分与したことで夫が贈与税を負担することになれば、事実上「二重課税」が発生している状態になります。
これは、当事者双方にとって大きな不利益です。
このような事態を避けるには、財産分与の金額の妥当性や合理性が重要になります。
この点は弁護士だけでなく、相続と贈与に強い税理士と連携して対応することが不可欠です。実質的に贈与と評価されないよう、協議書の文言や経緯説明の整理、分与方法の選択などを慎重に進める必要があります。
相続財産を分与に含めることを検討している場合は、必ず事前に専門家へ相談するようにしましょう。
5-4. 財産分与に伴うその他の税金(不動産取得税・登録免許税)
相続財産に不動産が含まれており、それを離婚時の財産分与の一部として相手に渡す場合には、不動産取得税や登録免許税など、別途発生する税金にも注意が必要です。
不動産取得税
原則として、離婚による財産分与で取得した不動産にはかかりません(非課税扱い)。
登録免許税
不動産の名義変更をする際には、原則として固定資産税評価額の2%相当額が課税されます。
これらの税金を誰が負担するかについても、離婚協議書や財産分与合意書に明記しておくことが望ましいでしょう。
6. 相続財産と離婚時の財産分与に関連するよくある質問(FAQ)
Q1:離婚前に親が亡くなったのですが、相続放棄をすれば財産分与の対象にはなりませんか?
A:相続放棄をすれば、その財産は最初から「相続しなかった」ものとして扱われるため、当然ながら離婚時の財産分与の対象にもなりません。ただし、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。また、放棄後はその相続分が他の相続人に回ることになるため、単なる財産分与回避目的での相続放棄には慎重な判断が求められます。
Q2:相手が私の相続財産を勝手に使い込んでいたことが離婚後に判明しました。取り返せますか?
A:状況次第では取り返せる可能性があります。たとえば、婚姻中に配偶者があなたの名義の相続預金を無断で引き出して生活費以外に使用していたような場合、不法行為や不当利得返還請求が認められる可能性があります。ただし、既に離婚が成立している場合は、時効や証拠の確保が問題になることもあるため、できるだけ早期に弁護士に相談することをおすすめします。
Q3:遺留分侵害額請求を受けている最中ですが、離婚の財産分与にも影響しますか?
A:原則として、遺留分の問題と離婚の財産分与は別問題として扱われます。
ただし、遺留分侵害額請求によって得られる金銭(または支払義務)は財産価値としてカウントされるため、分与対象となる財産の総額に影響する可能性はあります。
また、支払義務者側は将来の負債として考慮されることもありますので、財産評価にあたっては弁護士の助言を受けることが望ましいです。
Q4:離婚と相続の手続は、どちらを先に進めた方がよいですか?
A:一概にはいえませんが、以下のような観点で判断されます。
- 相続財産の整理が不十分な状態で離婚協議を進めると、財産分与の対象財産が不明確になり、協議が長期化する可能性があります。
- 一方で、既に婚姻関係が破綻しており、共有財産の分与だけでなく、親権や扶養など急ぎの問題がある場合は、先に離婚を進めることも検討されます。
相続財産の整理状況と、離婚の優先度を見てバランスを取ることが大切です。
Q5:親の相続でもらった実家に住んでいたのですが、離婚後は出ていくべきですか?
A:その実家があなた個人の特有財産であれば、原則として使用権限はあなたにあります。
ただし、婚姻中は配偶者にも「居住権に準ずる保護」があると考えられる場面もあるため、離婚成立までの間は、勝手に相手を追い出すことがトラブルの原因になり得ます。
居住権や使用料の取扱いについては、財産分与と併せて慎重に話し合う必要があり、調停等での整理が求められるケースもあります。
7. まとめ:相続と離婚を“別問題”と考えないために
離婚と相続という二つの出来事は、それぞれ別個の法律制度に基づいて動くものですが、現実の生活では複雑に絡み合うことが多く、明確に切り分けることは困難です。
特に、
- 相続した財産を財産分与に含めるべきかどうか
- 相続登記が終わっていない不動産がある
- 税務上のトラブルや法的リスクを避けたい
といった場合には、法律・税務・手続きの視点を一体的に整理することが不可欠です。
早い段階で弁護士を中心とした専門家へ相談しておくことが、安心で公正な解決に直結します。まずは一度ご相談ください。