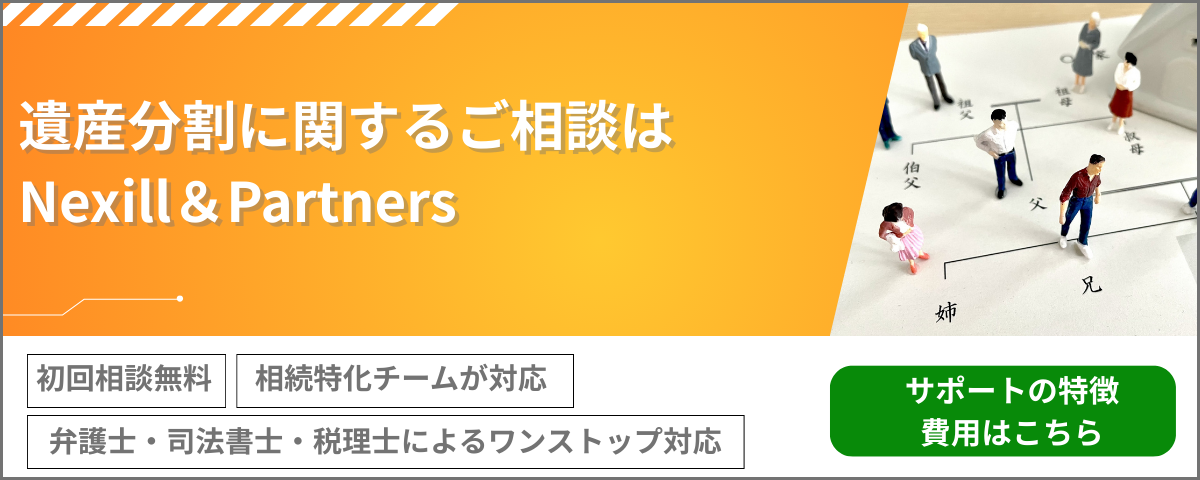遺産分割の方法としては、代表的な4つの手法があり、それぞれに特徴と注意点があります。
本記事では、遺産分割の全体像と4つの方法の違いやメリット・デメリット、どういうときに向いているのか?というところまで、実務経験豊富な弁護士の視点から丁寧に解説します。
1. 遺産分割とは?まず押さえるべき基礎知識
1-1. 相続財産と遺産分割の関係性
相続が発生した際、まず必要になるのが「相続財産の把握」です。 被相続人(亡くなった方)が保有していた不動産、預貯金、有価証券、生命保険金、車や骨董品、借金など、プラスの財産もマイナスの財産も含めて洗い出す必要があります。
このうち、相続人の間で「誰が何をどのように相続するか」を決める手続きが「遺産分割」です。
なお、相続財産のすべてが、遺産分割協議の対象になるわけではありません。
たとえば、受取人が指定された生命保険金や死亡退職金などは、法律上、特定の人に直接帰属するため、遺産分割の話し合いでは対象外となります。
遺産分割の対象とならない財産の例
- 生命保険金(受取人指定がある場合)
- 死亡退職金(会社が遺族に支給するもの)
- 遺言で「特定の人に与える」と明記された財産
- 祭祀財産(墓地・仏壇など)
- 被相続人の死亡後に発生した財産(相続後の利息など)
1-2. 遺産分割のタイミングと手続きの流れ
遺産分割は、相続開始後すぐに行うものではなく、相続人全員が確定し、相続財産が一覧化されてから進めるのが一般的です。
遺産分割の大きな流れとしては次のようになります。
遺産分割の流れ
2. 相続人の調査・確定(戸籍調査など)
3. 相続財産の調査・評価
4. 遺産分割協議の開始
5. 協議成立後、各財産の名義変更・分配手続きへ
このうち「4. 遺産分割協議」の段階で、どの方法を使って誰に何を渡すかを話し合うことになります。
協議の結果は必ず「遺産分割協議書」として文書化する必要があります。
1-3. 遺産分割には相続人全員の同意が必要
遺産分割協議は、相続人全員の同意があって初めて成立する手続きです。 1人でも反対や不参加がいると、協議は無効となります。 これは「全員で合意する」という民法の基本原則に基づくもので、相続人の人数が多ければ多いほど、話し合いが複雑になる傾向があります。
また、「話し合いがまとまらない場合」は、家庭裁判所に「遺産分割調停」や「審判」を申し立てることで裁判所を通じて話し合いを行い、最終的な遺産分割の内容を決めることになります。
2. 遺産分割の4つの方法とは?
遺産分割には、法的に認められた4つの代表的な方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、相続財産の種類や相続人の希望によって最適な選択肢が異なります。
この章では、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つの基本的な分け方について、それぞれの特徴を解説します。
2-1. 現物分割:財産を“そのまま”分ける方法
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人が分け合う方法です。 たとえば、長男が自宅不動産を取得し、次男が預金を相続する、というような分け方です。
現物分割は、相続財産に不動産や高額な動産が含まれている場合に多く用いられます。
実物をそのまま引き継げるため、シンプルで費用がかからない反面、分け方に差が出やすいという面もあります。
向いているケース
- 財産の種類が多く、それぞれに価値がある
- 各相続人が特定の財産に強い希望を持っている
- 相続人間での話し合いが可能で、スムーズに財産の分け方が決められる
2-2. 換価分割:財産を売却し“お金で”分ける方法
換価分割とは、相続財産をいったん売却して現金化し、その代金を相続人で分け合う方法です。 たとえば、不動産を売却し、売却代金を法定相続分に応じて分配するケースが該当します。
換価分割は、分けにくい不動産や高額な動産がある場合に、もっとも“公平感”を保ちやすい手段です。
ただし、売却にかかる時間や手数料、譲渡所得税などの負担も発生するため、費用面と納税の準備を含めた総合的な判断が必要になります。
向いているケース
- 不動産を誰も引き継ぎたくない/引き継げる人がいない
- 平等な分配を重視したい
2-3. 代償分割:1人が財産を取得し“代償金”を支払う方法
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償として金銭を支払う方法です。 たとえば、自宅を長男が単独で取得し、その見合いとして次男に1000万円を支払う、といったような形が例としてあげられます。
この方法は、不動産を維持・活用したい相続人がいる場合に有効ですが、代償金を支払えるだけの現金を確保できるかが実現のカギになります。
向いているケース
- 実家や事業用資産を引き継ぎたい(引き継がせたい)相続人がいる
- 相続人間で「取得したい人」が明確になっている
- 財産の保全や継続利用を優先したいとき
2-4. 共有分割:ひとつの財産を複数人で“共有”する方法
共有分割とは、相続財産の所有権を相続人全員で共有とする方法です。 たとえば、兄弟3人がそれぞれ3分の1ずつ自宅不動産の持ち分を取得するといったケースが該当します。
一見、シンプルで柔軟な方法に見えますが、後のトラブルが起きやすく、相続実務では注意が必要な方法です。
というのも、売却・修繕・活用などの意思決定にすべての共有者の合意が必要になり、次世代に相続されるとさらに複雑化するおそれがあるからです。
実務上はどうしてもという場合以外はできるだけ共有分割以外の方法で進めることが望ましいといえます。
向いているケース
- 一時的な措置として共有にせざるを得ないとき
- 相続人全員が仲がよく、将来的な方向性にも合意があるとき
2-5. 各分割方法のメリット・デメリット比較
遺産分割の方法は、どれか一つが「正解」というわけではなく、相続財産の内容や相続人の関係性、今後の管理方針などによって、最適な手段が異なります。
以下、ここまでに紹介した4つの方法それぞれについて、メリットとデメリットを具体的に整理し、選ぶ際の判断軸を明確にしていきます。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 |
|
|
| 換価分割 |
|
|
| 代償分割 |
|
|
| 共有分割 |
|
|
このように、各分割方法には一長一短があり、「平等さ」を優先するか、「財産の性質」に合わせるか、「将来の管理」を見据えるかによって、最適な選択肢は変わってきます。
特に不動産が含まれる場合には、「そのまま誰かが引き継ぐべきか」「売却して分けるべきか」といった判断が悩ましいところです。
3. 実際にはどう決めることが多いのか?分割方法の選び方の実務
3-1. 財産の種類・金額・相続人の関係性が判断基準
遺産分割の方法は、理屈だけでなく、実際の財産構成や家族間の関係性によって現場で柔軟に選ばれています。 たとえば、不動産の割合が大きく現金が少ない場合には、現物分割や代償分割が選ばれやすく、 逆に相続人の人数が多くて公平性を重視する場合には、換価分割が適しています。
また、相続人の一部が高齢・無職・遠方在住などの場合には、「将来的な管理や処分が難しい財産は避けたい」といった事情から、分け方が大きく左右されることも少なくありません。
相続分は法定割合で均等でも、実態として“何を受け取るか”を調整する必要が出てくるため、相続財産の種類・評価額・換金性・管理のしやすさなどが、選択の基準になります。
3-2. 複数の方法を組み合わせるケースも多い
現場では、1つの分割方法だけで完結するケースはむしろ少数派です。 たとえば、不動産は換価分割、預金は現物分割、車は共有して後日売却、といったように、複数の方法を組み合わせて進めるのが現実的な対応です。
また、どうしてもという場合は当初は共有分割として登記だけ済ませておき、数年後に売却または持分買取という形で将来的に代償分割や換価分割に移行していくこともあります。(ただ、共有状況にしておくことでのデメリットがあるので、あまりお勧めはしておりません。)
弁護士が関与する場合、相続人間の意向や財産ごとの特性を整理したうえで、段階的に複数手法を組み合わせて最適解を導くという場面が多く見られます。
3-3. 専門家の介入でスムーズになる場面とは
遺産分割では、「財産の価値をどう評価するか」「誰が管理するか」「将来的にどう処分するか」といった点を話し合う必要があり、単なる“感情の話し合い”では解決できない局面が多々あります。
たとえば、不動産を売却した場合に生じる譲渡所得税の計算、代償金を払う資金計画、贈与税や二次相続への影響など、法律と税務の視点が必要になる場面では、専門家が入ることで全体像を整理しやすくなります。
また、第三者が介入することで、冷静に話し合える環境が整い、感情の衝突を避けやすくなるという効果もあります。
「家族だから話し合える」は理想ですが、実際には「家族だからこそ言えない・聞けない」ことが多いのも相続の現実です。
専門家の関与は、“押し付ける”ものではなく、“中立に整理する”手段と考えると、よりスムーズな分割に近づけるはずです。
4. 遺産分割についてのよくある質問(FAQ)
Q. 遺産分割の方法を一度決めた後に、やり直すことはできますか?
基本的に、遺産分割協議書に全員が署名・押印して遺産分割協議が成立した後は、原則やり直すことはできません。 ただし、「協議の際に重大な事実が隠されていた」「無効な意思表示だった」などの事情があれば、遺産分割のやり直しを主張できる可能性もあります。遺産分割の内容に不満がある場合は、早い段階で弁護士に相談のうえで、対応の可否を判断してもらうことが望ましいでしょう。
Q. 遺産分割が終わる前に相続財産を処分してしまっても問題ありませんか?
基本的にはNGです。遺産分割協議が完了するまでは、相続財産は相続人全員の“共有状態”にあるとされており、勝手に処分することはできません。たとえば、相続人の一人が勝手に不動産を売却したり、預金を全額引き出して使ってしまったりした場合、他の相続人から損害賠償や返還請求を受ける可能性があります。
なお、葬儀費用などの支払いで一時的に現金が必要になった場合は、預貯金の仮払い制度を使用することで一定額の引き出しは可能となります。(この場合、引き出した預貯金については、遺産分割時に調整がなされます。)
預貯金の仮払い制度を含めて、遺産分割が終わる前に財産を処分してしまった場合は、相続することを承認したとみなされて、相続放棄ができなくなるケースもありますので、財産の処分は慎重に実施しましょう。
Q. 今回の遺産分割が、次の相続に影響することはありますか?
はい、一次相続(たとえば父の死亡)での分け方は、次に起こる二次相続(たとえば母の死亡)に大きく影響します。 たとえば、「一次相続で配偶者に多く渡したことで、二次相続の課税額が高くなってしまう」「兄弟間の取得額に大きな差がついた」というような事例はよく見られます。
そのため、遺産分割を考える際には、「今回の分け方で家族関係や相続税のバランスがどうなるか」まで視野に入れることが大切です。
この辺りは弁護士だけでなく税理士にも相談の上で、長期的に見てリスクが少ない遺産分割方法を設計されてみてください。
5. 当事務所のサポート体制と対応実務
当事務所では、弁護士だけでなく、税理士・司法書士が在籍し、「遺産調査・遺産分割設計・遺産分割協議支援・相続登記・相続税申告」までワンストップ対応が可能です。
また、遺言書がある場合・ない場合、生前贈与がある場合、二次相続(次に起きる相続)まで見据えた分け方など、幅広いケースに対応したサポートプランをご用意しています。
「今はまだ問題が起きていない」という段階でもご相談いただけますので、少しでも不安や迷いがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。