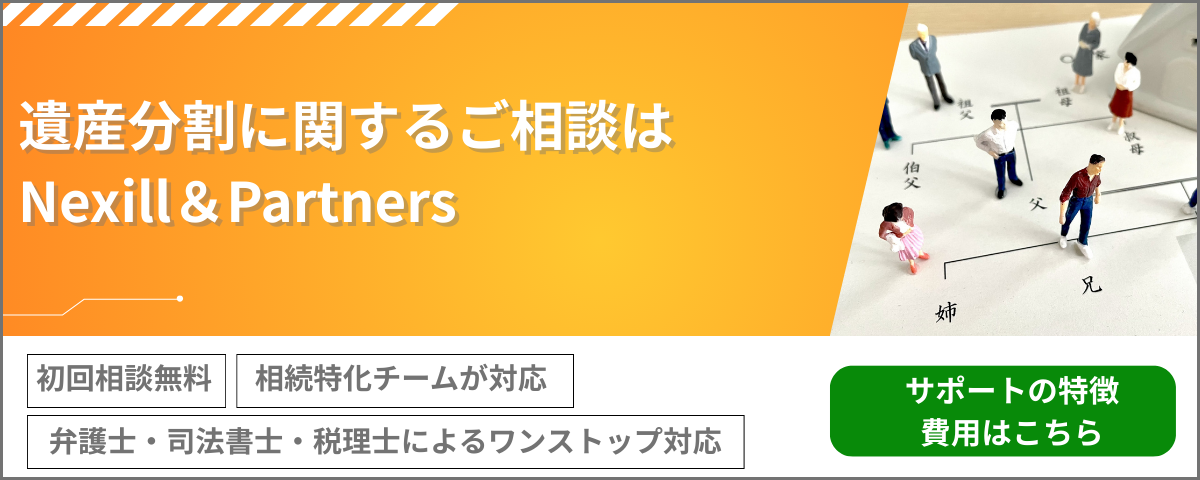相続が発生すると、まず目に見える形で気になるのが「銀行の預貯金」の扱いです。
「遺産分割協議が終わっていなくても預金は引き出せるのか?」「通帳に残された金額が思ったより少ない、不審な出金がある」など、預貯金の遺産分割における考え方や法的ルール、銀行での手続きの流れ、注意すべき実務ポイントを弁護士の視点から解説します。
1. 銀行預貯金は原則として「可分債権」=遺産分割の対象
被相続人名義の銀行預貯金は、原則として「相続財産」に該当しますので、法定相続人全員で協議して分け方を決める対象となる財産です。
預貯金は現金化しやすいため、他の財産と比べて分割しやすいという特徴がある一方で、使い込み等を巡ってトラブルになりやすい財産でもあります。
遺言がある場合には、内容に従って預貯金を特定の相続人に引き継がせることができますので、遺言に基づき特定の相続人単独での払い戻しが可能となります。
一方、遺言がない場合には、払い戻しには相続人全員の合意(=遺産分割協議)が必要です。
2. 相続開始後、口座凍結解除に必要な書類と手続の流れ
被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、その時点で預貯金口座は凍結されます。
これにより、預金の引き出しや振込、解約などが一切できなくなります。
凍結を解除し、預貯金を払い戻すためには、以下のような書類を提出する必要があります。
預貯金払戻しの一般的な必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書(公正証書遺言など)
- 銀行所定の相続手続き書類(口座解約申請書など)
手続きの詳細や書類の要否は金融機関ごとに異なるため、対象の金融機関に事前確認の上で進められてください。
一般的に、金融機関に書類提出を行ってから2週間~1か月程度を目安に払い戻しが完了します。
3. 必要に応じて、凍結解除前に預貯金の一部の引き出しができます(法定払戻制度)
民法の改正により、法定相続分に基づいて、一定額まで単独で引き出せる制度が創設されました。
この制度では、以下の条件を満たせば、遺産分割協議が未了でも、1金融機関につき150万円まで払い戻しを受けることができます。
法定払い戻し制度の要件
- 支払いを求める相続人が、法定相続人であること
- 払い戻しの金額:相続開始時の口座残高 × 法定相続分 × 1/3 ≤ 上限150万円
法定相続分に基づく金額であること、かつ相続人1人あたりの総額ではなく「金融機関ごと」の上限である点がポイントです。
利用にあたっての実務上の注意点としては、この制度の利用=利用した相続人の相続分の確定ではないということです。
仮に預貯金を引き出しても、それが「自分の取り分になった」わけではありません。後の遺産分割協議で、引き出した分を差し引いて精算する必要があります。
なお、遺産分割を進めるにあたって、相続人にてこの制度を利用すること自体に“法的なデメリット”は基本的にありません。
ただ、「勝手に引き出された」と感じる相続人が出ることもあり、遺産分割協議前に独自で動いたことが後々の協議に影響を及ぼす可能性もあるため、他の相続人と情報共有を行ったうえで制度利用をすることをお勧めします。
法定払戻制度は、葬儀費用や当面の生活資金などを確保するために有効な制度です。
ただし、制度の性質と他の相続人への配慮を誤らないことが、後々のトラブル防止につながります。
単なる引き出しではなく、「後で清算する前提の仮払い」であることを理解して活用しましょう。
4. 遺産分割協議がまとまらないときの預貯金の扱い
4-1. 家庭裁判所での遺産分割調停・審判の申立て
相続人間での協議がどうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行うことで、裁判所での遺産分割の協議に移行します。
調停はあくまで裁判所での話し合い(協議)になりますので、ここでも相続人同士での合意ができなければ調停は不成立となってしまいます。(調停で何らかの強制力のある命令が出るわけではありません。)
調停でも遺産分割の方法が決まらなかった場合は、自動的に「審判」に移行し、ここで初めて裁判所が法的基準に基づいて預貯金の分け方を判断します。
なお、調停・審判では遺産の分配だけでなく、引き出し済みの預貯金や生前贈与の有無などの遺産の範囲の確定を含む周辺事実も審理対象となります。感情的対立がありご自身のみでの協議が難しい場合ほど早期の調停申立てが望ましいと言えます。
4-2. 使い込み・単独引き出しがあった場合の対応
相続開始前後に、一部の相続人が被相続人の預金を勝手に引き出していた場合、それが不当利得や不法行為と評価されることもあります。
通帳や取引明細を見て明らかに多額の引き出しが多発している、被相続人が自分自身で引き出しができない時期に引き出しが継続しているなど、他の相続人が不正取得を疑った場合は、早急に弁護士に相談し、不当利得返還請求や調停申立てなどの法的措置を含めて対応方法を検討してもらってください。
逆に使い込みを疑われている場合は、何のために使ったのか(被相続人に頼まれて生活費として使用していたなど)を証明しなければならないため、領収書やその他資料などから私的に利用したものではないことを説明できるような準備が必要です。(もちろん、本当に私的に利用していた場合は遺産分割の際に調整されるべき対象の財産となります。)
5. 相続税との関係|預貯金の分け方が税額に与える影響
5-1. 誰がいくら取得するかで課税額が異なる
相続税は「相続人ごとの取得財産の価額」に応じて計算されます。
そのため、預貯金を誰がどれだけ取得するかによって、相続税額が変動します。
たとえば、配偶者が預貯金を多く取得した場合は、配偶者の税額軽減により非課税になる可能性もあります。
5-2. 特例(配偶者控除・未成年控除等)との関係
預貯金を相続する際にも、相続税の特例は適用されます。主な特例は次の通りです。
相続税の主な特例
配偶者の税額軽減
1億6,000万円または法定相続分まで非課税
未成年者控除/障害者控除
相続人の年齢や障害の程度に応じた減税
相次相続控除
前回の相続から10年以内に再び相続が発生した場合の軽減
これらを活用することで、課税負担を抑えながらの遺産分割が可能になります。
関連:預貯金を納税資金として確保しておくことの重要性
相続税は原則「現金で一括納付」が求められるため、納税期限までの納税資金の準備が課題となります。
不動産や非上場株式など早急な現金化が難しい資産ばかりを取得すると、納税資金に困るケースもあるため、遺産分割の中で一部を預貯金として確保することが求められます。
相続人が預貯金などの流動資産を十分に取得していない場合、急きょ資産の売却や借入れを検討しなければならなくなるおそれもありますので、可能であれば生前から相続税の予測を行っておき、その金額を賄えるだけの納税資金が預貯金で確保できるような準備をしておくことが望ましいでしょう。(預貯金の確保、株式運用、生命保険の活用など)
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. 預貯金の法定払戻制度は、どの銀行でも必ず対応してくれますか?
法定払戻制度は民法で定められた制度なので、金融機関には対応義務があります。
ただし、運用にあたっては銀行ごとに必要書類や審査の手順が異なることがあり、即日対応されるとは限りません。
実際には、戸籍謄本や相続人の印鑑証明などを揃えた上で、所定の申請書類を提出し、数日〜2週間程度かかるのが一般的です。
Q. 使い込みが疑われる引き出しについて、どこに相談すればよいですか?
相続人の誰かが生前または相続開始後に無断で預金を引き出していた場合、まずは残高証明書や通帳の履歴を確認することが第一歩です。
そのうえで、不当利得返還請求や遺産分割調停に含めるべきかどうかを判断する必要があります。
このような状況では、弁護士に相談して法的な整理をしたうえで対応するのが望ましいです。
Q. 被相続人と同居していた人が管理していた通帳の履歴は調べられますか?
はい、可能です。相続人の一人として、金融機関に対して被相続人の預貯金に関する残高証明書や取引履歴の開示請求ができます。
請求には、被相続人の死亡を証明する戸籍と、自分が相続人であることを示す書類の提出が必要です。
Q. 通帳やキャッシュカードを相続人の誰かが勝手に持ち出していたらどうすれば?
まずは金融機関に状況を伝え、口座凍結の有無を確認しましょう。すでに引き出されていた場合には、引き出し履歴をもとに不当利得として返還請求を検討することになります。
相続人同士の話し合いでは解決が難しい場合には、弁護士介入を検討するタイミングです。
預貯金は一見分けやすい財産ですが、誰かが先に引き出していた、金額に納得できない、通帳や履歴が不明といった状態があると、相続人同士のトラブルに発展しやすい側面もあります。
また、相続税などの実務面を考慮すると、ご自身の状況に適した分配と円滑な手続を実現するためには、法的・税務的観点からのサポートが不可欠です。
当事務所では、相続案件に特化した弁護士を中心に、税理士とも社内連携の上で預貯金を含めた相続財産全体を考慮しながらの遺産分割をサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。