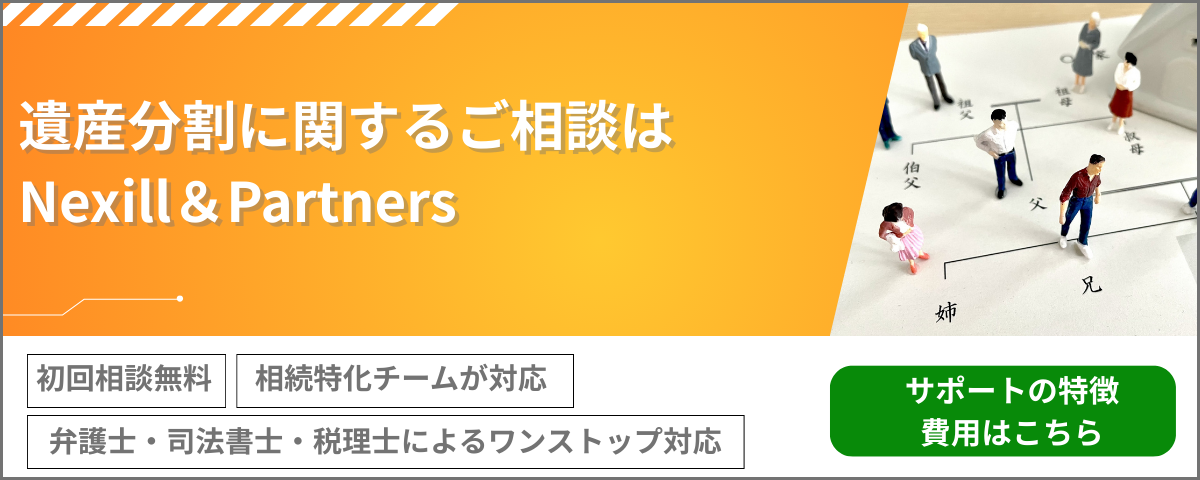相続が発生した際、多くの方が最初に疑問に感じるのが「遺産をどうやって分ければよいのか?」という点です。
民法には「法定相続分」が定められていますが、実際の遺産分割では相続人間の話し合いによって、異なる割合で分割することも可能ですが、分割割合を決める際には注意点も伴います。
本記事では、遺産分割時の相続割合の基本である法定相続分の仕組みから、話し合いで自由に割合を決めるときの注意点まで、弁護士が実務経験をもとに解説します。
1. 遺産分割における「相続割合」とは何か?
1-1. 相続人それぞれが持つ“取り分”をどう考えるか
相続が発生すると、まず考えるべきなのが「誰が、どのくらい遺産を引き継ぐのか」という点です。
この「取り分」のことを、実務では「相続割合」「相続分」と呼びます。
相続割合は、単に相続人の数を等分すればよいというものではなく、民法で定められた基準(=法定相続分)を起点としつつ、話し合い(遺産分割協議)によって相続人全員の合意のもとで自由に変更することもできます。
1-2. 財産の種類によって割合の扱いを変えることも
現金や預貯金のように分けやすい財産であれば、相続割合をそのまま反映して配分することが容易です。
しかし、不動産や非上場株式など、分けにくい財産が含まれている場合は、評価額や利用実態をふまえて相続割合と異なる配分を選択することも多くなります。
そのため、「法律上の相続割合」と「実際の分け方」を必ずしも一致させる形で遺産分割協議をまとめるとは限らないことを理解しておくことが重要です。
2. 法定相続分とは?民法で定められた分割基準
2-1. 配偶者・子・兄弟姉妹・直系尊属の相続割合
民法では、以下のように「法定相続分」が定められています(民法900条)。
| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子全体で1/2(複数いる場合は等分) |
| 配偶者と直系尊属(親) | 2/3 | 親全体で1/3(両親健在の場合は父母が1/6ずつ) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4(複数いる場合は等分) |
| 配偶者のみ | 1(全額) | |
| 子のみ(配偶者なし) | 1(子全体で全額) |
なお、養子、認知された子なども法定相続人として扱われます(一定の制限あり)。
補足:法定相続人に該当する子の範囲と注意点
民法上、「子」として相続人に該当するのは実子だけではなく、養子や婚外子(非嫡出子)なども含まれます。それぞれの法的立場によって相続権の有無や取扱いに違いがありますので、相続割合を判断する前提として、子の法的範囲を整理しておきます。
認知された非嫡出子(婚外子)
被相続人に認知された非嫡出子は、嫡出子と同等の法定相続権を持ちます。
かつては相続分が嫡出子の1/2とされていましたが、民法改正によりこの差は廃止され、現在は法定相続分も完全に同等です。
普通養子
普通養子は、養親と法律上の親子関係を持ち、相続においても実子と全く同じ法定相続権を有します。
民法上、何人でも普通養子縁組は可能であり、相続割合の計算上もすべての養子が「子」として扱われます。
ただし、相続税の計算上に限っては、基礎控除や生命保険の非課税枠などで「法定相続人の数」に含められる普通養子の人数には制限があります(実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで)。
この制限は、相続税の計算に影響するものであり、民法上の相続権(=割合や分割協議への参加)には一切影響しません。
特別養子
特別養子は、家庭裁判所の審判によって成立し、養親とのみ親子関係を持ち、実親との法的親子関係が完全に終了する点が特徴です。
したがって、養親の相続においては、特別養子も実子と同じ相続権を持ちますが、実親(出生親)の相続人にはなりません。
なお、特別養子は、相続税法上も実子と同様に扱われるため、人数にかかわらずすべての子が法定相続人としてカウントされます。
配偶者の連れ子(養子縁組なし)
被相続人の配偶者の連れ子がいた場合、被相続人と養子縁組が成立していない限りは法定相続人には該当しません。
長年同居していたとしても、法律上の親子関係がなければ、相続権は認められませんので、連れ子を相続人に含めたい場合は、生前に正式な養子縁組を行っておくことが必要です。
2-2. 特別受益・寄与分があるときの修正の考え方
法定相続分はあくまで“基本形”ですが、次のような事情がある場合は、実質的な取り分(具体的相続分)が調整されることがあります。
特別受益がある場合
生前贈与や住宅資金援助など、被相続人から特定の相続人が大きな援助を受けていたときは、その分を相続財産に加算して、他の相続人との公平を図ることがあります。
寄与分がある場合
被相続人の療養看護や事業運営に特に貢献していた相続人がいれば、その貢献度を評価して相続分を加算することができます。
これらは協議で決めるか、まとまらない場合は家庭裁判所に申し立てを行い裁判所での調整を図ることになります。
3. 実務上は「法定相続分どおりに分けない」こともある
3-1. 相続人間の話し合いによる割合変更の自由
民法上の法定相続分は「遺産をどう分けるかの基準」として機能しますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。
たとえば、次のような事情で割合を変更することがあります。
- 長男が両親の介護を担っていたため、他の兄弟より多く取得する
- 配偶者が自宅に住み続けるため、土地・建物をすべて相続する代わりに預金は他の相続人に分ける
- 特定の相続人がすでに生前贈与を多く受けていたため、実際の取得割合を抑える
これらはすべて、「遺産分割協議」という相続人全員の合意によって成立します。
合意がある限り、必ずしも民法上の相続割合に縛られる必要はありません。
3-2. 法定相続分と異なる分け方が選ばれる背景
現実には、法定相続分のままでは不公平感や生活上の支障が生じるケースも多くあります。
たとえば、以下のような背景がある場合には、割合を柔軟に調整することが実務上推奨されます。
- 相続財産が不動産中心で、等分が物理的に難しい
- 相続人の生活状況(同居・単身・障害の有無など)に差がある
- 紛争を避けるために譲り合いの協議が成立している
これらの事情を無視して法定相続分どおりに進めてしまうと、結果として相続人間の感情的な対立を引き起こす可能性もあるため、合意の柔軟性が非常に重要になります。
3-3. 配偶者が自宅に住み続ける場合の特例的配分
相続割合を調整するよくあるケースとしては、「配偶者が自宅に住み続けたい」という希望がある場合です。
この場合、配偶者が土地・建物をすべて相続し、その代わりに現金や金融資産は他の相続人が取得する、といった法定相続分以外での分け方を選択することが多いです。
さらに、配偶者が自宅を相続する場合には、小規模宅地等の特例(330㎡まで評価額を80%減額)が適用され、相続税額の面でも有利になることがあります。
このように生活維持と税務を両立した分割案を選択することも可能ですので、可能であれば弁護士に相談をされながら遺産分割を進められることをお勧めします。
4. 相続割合を自由に決めるときの実務と注意点
4-1. 税務リスク(贈与とみなされるおそれ)
遺産分割は、相続人全員の合意によって法定相続分とは異なる割合でも自由に進めることができます。
通常、初回の遺産分割協議で不均衡な分け方をしても、相続人全員の合意に基づいたものであれば、相続税の課税対象とされ、贈与税の対象にはなりません。
ただし、次のようなケースでは実質的に贈与とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあるため注意が必要です。
① 遺産分割協議が一度成立した後、再分割を行って財産を再配分した場合
一度有効に成立した遺産分割協議によって各相続人に財産が確定・移転した後に、「やはり配分を変えよう」として財産を返還・再配分した場合、その追加取得部分はもはや相続による取得とは評価されず、贈与とみなされる可能性があります。
これは実務上も非常に重要なポイントで、再協議を行う場合は慎重な判断が求められます。
② 初回の分割で極端に不均衡な配分を行い、その合理的な説明がつかない場合
たとえば、兄弟3人のうち1人が全財産を取得し、他の2人がまったく何も取得しないような分割がなされた場合、税務署が「実質的には贈与」と判断するリスクはゼロではありません。
ここで言う「贈与」とは、財産を取得しなかった相続人が、本来の法定相続分に相当する権利を、他の相続人へ無償で渡したと評価される場合に、財産を取得しなかった相続人から取得した相続人への贈与とみなされることを意味します。
このようなケースでは、分割協議の経緯や背景事情、贈与ではないことを説明できる資料の整備が重要です。
4-2.家庭裁判所の審判まで進むと法定相続分に近い割合での分割となる傾向に
遺産を分ける割合について、相続人全員の同意が得られない場合は、話し合いによる自由な割合の分割はできません。
この場合、どうしでも当事者同士で割合が決められない場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割割合を決めていくことになります。
裁判の手続としては、まずは調停での解決(合意形成)を図り、それでも合意ができなかった場合は審判によって裁判所が割合を決定します。
裁判所は法定相続分をベースに割合を決定することが一般的なので、財産の種類などがそこまで考慮されずに、ほぼ法定相続分通りの分割割合となってしまうような場合もあります。
任意での割合で財産を分けたい場合は、できるだけ協議→調停までの段階で遺産分割協議を完了させることが望ましいでしょう。
4-3.相続人に判断能力がない場合は、家庭裁判所の後見手続が必要
相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力がない方がいる場合は、その方自身が有効に遺産分割協議に参加することはできません。
このような場合は、家庭裁判所に「成年後見人」や「特別代理人」の選任を申し立て、代理人を立てて協議に臨む必要があります。
代理人の関与なしに進めた遺産分割協議は無効となるおそれがあるため、判断能力の有無は遺産分割の割合を決める協議の前に必ず確認することが必要です。
5. 相続割合に関する質問FAQ
Q. 遺産が不動産だけの場合の分け方は?
相続財産が不動産しかない場合、法定相続分どおりに共有にすることはできますが、後々の処分や利用が困難になるリスクがあります。
そのため、誰か1人が不動産を相続し、他の相続人には現金や預金を渡す「代償分割」もしくは不動産を売却し現金化したうえで法定相続分通りに分けるという方法を検討するのが一般的です。
代償分割であれば、法定相続分や協議で決めた相続割合を実質的に反映しながら、不動産を共有にしないという合理的な分割が可能となりますが、不動産を取得した相続人が代償金を準備する必要があるので、相続財産が不動産しかないケースであれば相続財産以外でのキャッシュが用意できる場合に限られてきます。
Q. 法定相続分どおりに分けたほうが税務上有利なのですか?
相続税の計算は「誰がどれだけ財産を取得したか」に基づいて個別に行われるため、法定相続分どおりでなければ不利になるということは必ずしもありません。
むしろ、相続人の属性や取得する財産の種類によっては、法定相続分からあえて外れた割合で分けた方が相続税の総額を抑えられるケースもあります。
たとえば、配偶者には「配偶者の税額軽減」という強力な特例があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までの取得には相続税がかかりません。
この制度を活かすために、他の相続人の同意を得て配偶者に多めに財産を寄せることで、相続税の総額を抑える戦略的分割が実務上はよく行われます。
また、小規模宅地等の特例や障害者控除なども、誰が何を相続するかによって適用の可否や節税効果が大きく異なります。
ただし、極端に不均衡な配分で合理的な説明がつかない場合には、税務署から一部を贈与とみなされるリスクもあるため、事前に税理士など専門家と十分に設計を行うことが重要です。
相続における割合は、法定相続分を起点としつつも、相続人全員の合意があれば柔軟に決定できます。
ただし、分け方によっては相続税の特例の適用可否や贈与認定といったリスクが生じるほか、不動産など現預金以外の財産の取り扱いによっては後の財産処分がやりにくくなるようなケースもありますので、財産の種類に応じて誰がどう取得するかの割合を検討することが望ましいです。
できるだけ早い段階で弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、最適な遺産分割方法と割合を設計することをお勧めします。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。