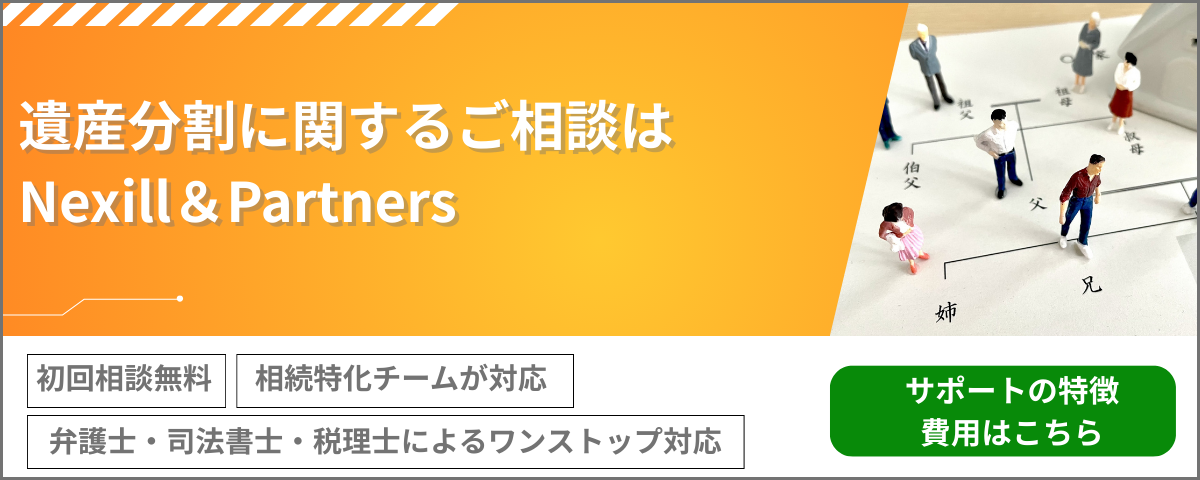相続が発生した際、「生前に兄が家を買ってもらっていた」「長女だけが学費の援助を受けていた」など、特定の相続人だけ生前に贈与や援助を受けているケースがあります。
生前贈与がある場合の遺産分割について、他の相続人とのバランスをどのように調整するのか、この記事では、特別受益の法的な考え方から、どのような贈与が該当するかの判断基準まで、税務面も含めてわかりやすく解説します。
1. 生前贈与と遺産分割の関係
1-1. 生前贈与とは何か?相続との違い
生前贈与とは、被相続人(亡くなった方)が生前に財産の一部を特定の人へ贈与することを指します。
不動産や現金、学費や住宅取得資金など、名目や方法はさまざまですが、贈与契約が成立していれば贈与として法的に有効とされます。
相続が「死亡に伴い開始される法律上の手続き」であるのに対し、生前贈与は生きている間に任意で行われる点が大きな違いです。
1-2. 相続が発生した後に生前贈与が問題になる理由
たとえば、相続人のうち1人が生前に多額の援助を受けていた場合、他の相続人から「不公平ではないか」という声が上がることがあります。
たとえば、兄が生前に土地を贈与されていたのに、遺産分割協議ではその贈与を考慮せずに均等分配を求められた場合、弟や妹は納得できないでしょう。
このようなときに使われるのが「特別受益」という考え方で、すでに受けている生前贈与分を加味して遺産を公平に分割する仕組みが民法上に用意されています。
2. 「特別受益」とは何か?民法の考え方を理解する
民法では、共同相続人のうち被相続人から生前贈与等にて特別な利益(特別受益)を受けていた者がいる場合には、その受けた利益を相続財産に加算し、全体の遺産を再評価した上で分割する「持ち戻し」の制度が定められています。
この制度の目的は、生前にすでに多くの財産を受け取っていた相続人が、相続の場面でも同じように受け取ることで、他の相続人との間に著しい不公平が生じるのを防ぐことにあります。
なお、生前贈与があった=すべてが特別受益になるというわけではありません。
民法上、特別受益は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての生前贈与」というような定め方になっていますので、この要件に該当しない生前贈与であれば特別受益にはあたらないことには注意が必要です。
2-2. 特別受益にあたる贈与の例
実務上、以下のような贈与は「特別受益」とされやすい例です。
特別受益とみなされやすい例
- 住宅取得資金の援助
- 結婚資金の援助(持参金など)
- 高額な学費の支援(大学・留学費用など)
- 不動産そのものの贈与
- 相続人に無償で不動産を使わせる権利(使用貸借)
特別受益に該当するかどうかは、単に「贈与があったかどうか」ではなく、その内容が他の相続人と比較して特別に優遇されていると評価できるかどうかが重要なポイントになります。
金額の大きさや、援助の内容、贈与を受けた時期、対象が他の相続人にも等しく与えられているかどうかといった事情を総合的に見て、被相続人から“相続財産の前渡し”にあたるような性質があるかを判断します。
また、贈与という形式を取っていなくても、被相続人名義の不動産を無償で使用させていたような場合には、その人が“実質的に利益を得ていた”と評価され、特別受益と見なされる可能性もあります。
2-3. 特別受益にあたらないとされる例
反対に、一見すると贈与のように見えても、相続においては「特別受益」とみなされない支援もあります。
代表的な例として、次のようなケースが挙げられます。
特別受益にあたらないとされる例
- 被相続人と同居していたことでの生活費の援助
- 被相続人の看護・介護に対する謝礼
- 扶養義務に基づく日常的な生活援助(食費・医療費の一部負担など)など
このような支援については、被相続人による通常の扶養義務や家族的な支援の範囲内と評価されることが多く、特別受益とならないケースが多いです。
2-4. 特別受益の持ち戻しの仕組みと計算方法
前項までで見てきたとおり、被相続人が生前に行った贈与のうち、「婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与」に該当し、かつ特別性があると評価されるものは、民法903条に基づき「特別受益」として扱われます。
この特別受益があった場合には、実際の遺産の額にその贈与額を加えた“みなし相続財産”を基準に相続分を計算するという方法がとられます。
この手法を「特別受益の持ち戻し」といい、法定相続分などによる配分を行う際の出発点となります。
たとえば、相続財産が2,000万円、相続人が配偶者と長男の2名、長男が生前に住宅資金として500万円を受け取っていた場合、
- 相続財産に長男がすでに受け取っている資金を足した2,500万円をみなし相続財産とする
- みなし相続財産を法定相続分で分けると、それぞれの取得分は1,250万円ずつ
- 長男はすでに500万円を受けとっているため、遺産からはその分を差し引いた750万円のみ受け取る
- 配偶者は遺産から1,250万円を取得する
というような流れで計算と相続分取得を行います。
3. 生前贈与が特別受益に該当するかどうかの判断基準
3-1. 名目より実態が重視される
贈与の名目に関わらず、実際に「特別受益」として扱われるかどうかは、贈与の実質的な性質に基づいて判断されます。
たとえば、被相続人が「これはお祝いだから贈与ではない」と言っていたとしても、住宅購入や事業立ち上げなど、明らかに経済的支援として機能していた場合には、特別受益と見なされる可能性が高いです。
一方で、形式上は贈与契約があっても、金額が極端に少ない、または生活費の一部である場合などは、特別受益とは評価されないこともあります。
つまり、「何のために」「どの程度の規模で」支援が行われたかが、本質的な判断基準になります。
3-2. 使途・金額・時期が判断材料になる
裁判例や実務では、以下のような要素を総合的に考慮して判断されていることが一般的です。
特別受益の判断材料の一例
使途
住宅取得、結婚、留学、開業資金などは生計の資本とされやすい
金額
一般的な生活援助を超えた“まとまった額”かどうか
時期
相続開始に近い時期か、相続を見越していたかどうか
相続人間の比較
他の相続人には同様の支援があったかどうか
このような要素を踏まえて、個別の支援が特別受益として「相続分の前渡し」にあたると評価できるのかどうかを状況ごとに検討する必要があります。
3-3. 被相続人の意思が考慮される場合も
特別受益にあたるかどうかは、贈与の性質や金額・使途などによって個別に判断されますが、もう一つ重要なのが、被相続人自身が「その贈与を遺産の取り分として扱うつもりがあったかどうか」という意思の有無です。
特に、特別受益に該当するような贈与があったとしても、被相続人が明確に「これは他の相続人と平等に扱う必要はない」との意思を示していた場合(=持ち戻し免除の意思表示)は、特別受益として考慮されない可能性があります。
この「持ち戻し免除の意思表示」は、明示的に遺言などで記載されているのが最も明確ですが、状況や言動から黙示的に読み取られる余地もあるとされています。
ただし、被相続人に特別受益を持ち戻す意思があったという明確な証拠がない場合は解釈が分かれトラブルの原因となりやすいため、専門家へ相談の上で取り扱うことが望ましいでしょう。
4. 相続税との関係|贈与と課税の関係に注意
ここまで、特別受益としての生前贈与が遺産分割に与える影響について解説してきましたが、生前贈与は「法的な相続分の調整」だけでなく、「税金の負担」にも大きく関係してくる財産です。
特に相続税の計算においては、生前に受けた贈与が一定の条件を満たすと、相続財産として加算され、税額に影響するという制度が存在します。
ここからは、生前贈与と相続税の関係について、制度上の仕組みと実務上の注意点を整理してお伝えします。
4-1. 相続開始前3年以内の贈与と「加算制度」
相続税法では、相続開始前3年以内に相続人へ行った贈与については、その贈与財産の価額を“相続税の課税対象となる遺産”に加算するというルールが定められています。
これは、相続税の回避を目的とした生前贈与を防止するための制度になります。
この取り扱いを失念し申告漏れになってしまうケースもありますので、対象期間内に生前贈与を実施した場合は税務申告時に注意をしておきましょう。
4-2. 特別受益と相続税申告上の取扱いの違い
特別受益の持ち戻し制度は、相続人間の公平を図るために、法定相続分の算定に際して生前贈与を「相続分の前渡し」とみなして調整するものです。
一方で、相続税は「実際に相続人が取得した財産額」に基づいて計算されるため、法的に調整された相続分と税務上の課税対象が一致しないことがあります。
たとえば、長男が生前に住宅資金として1,000万円の贈与を受けていたとします。
法的にはこれを特別受益として持ち戻し、みなし相続財産に加算して相続分を再計算することで、他の相続人との公平を保ちます。
しかし、相続税の申告では「実際に相続で取得した金額」に対して課税されるため、贈与された1,000万円は「過去の取得」として課税対象からは外れ、相続で取得した分のみが課税対象となります。
また、被相続人が「持ち戻し免除の意思表示」をしていた場合でも、税務上は依然として相続財産を取得したものとして扱われ、相続税の課税対象となることがあります。
このように、民法上の遺産分割と相続税法上の財産評価は制度目的が異なるため、処理の整合性が常に取れるとは限りません。
そのため、特別受益や生前贈与の有無がある場合には、法的手続と税務処理を別々に整理し、それぞれの観点から漏れなく対応する必要があります。
4-3. 贈与税と相続税の重複計算に注意
さらに注意したいのは、被相続人が生前に行った贈与について、すでに贈与税が課税されていた場合の取扱いです。
このようなケースでは、相続税の申告時に「相続財産としての加算」と「贈与税の納税実績」とが重複する可能性があるため、制度上の調整措置を正しく理解しておくことが重要です。
具体的には、「相続時精算課税制度」を利用していた贈与については、その贈与財産の価額を相続財産に加算し、相続税の対象としつつ、すでに納めた贈与税額を相続税から控除することが可能とされています。
これにより、贈与税と相続税の二重課税を避けられます。
ただし、相続時精算課税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しておく必要があり、相続発生後に制度をさかのぼって適用することはできません。
したがって、相続発生後に「この贈与について精算課税を使いたい」としても、それは制度上認められず、あくまで“贈与時点での計画的な選択と届出”が必須となります。
このように、贈与税と相続税が関係する場合は、単に課税対象の整理にとどまらず、どの制度をどう使うか、いつ選択しておくべきかという視点を含めて検討することが必要です。
そのためにも、贈与の段階から税理士や弁護士に相談し、長期的な税務設計を踏まえて対応しておくことが重要です。
5. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 生前贈与が特別受益と認定されると、どのように相続分が変わるのですか?
特別受益と認定された贈与は、民法上「すでに相続分の一部を受け取った」とみなされます。
そのため、実際の遺産分割においては、他の相続人とのバランスをとるために取得分が差し引かれる(持ち戻し)形になります。
ただし、最終的にどう分けるかは、相続人間の協議によって柔軟に決めることも可能です。
Q2. 特別受益になるかどうかはどのような基準で判断されるのですか?
単に金額が大きいから特別受益になるわけではありません。
贈与の使途が「婚姻、養子縁組、または生計の資本」とされるかどうかや、他の相続人との比較、贈与の時期・継続性などを総合的に見て判断されます。
裁判例では、「生活費の援助」や「介護への謝礼」などは特別受益に該当しないとされることが多く、贈与の目的と性質が重要な判断材料になります。
Q3. 特別受益があっても遺留分は請求できますか?
はい、可能です。たとえ特別受益があっても、他の相続人によって遺産がほぼ取得されてしまった場合などには、最低限の相続保障として「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
特別受益と遺留分は制度自体の趣旨が異なるため、まずは弁護士にご相談ください。
Q4. 贈与の記録や証拠がない場合、特別受益を主張しても意味がないのでしょうか?
証拠がない場合でも、通帳の出金履歴や、そのほかの資料などをもとに事実関係を積み上げて主張することは可能です。
ただし、証明責任は原則として「特別受益があった」と主張する側にあるため、交渉・調停を見据えると、客観的な証拠収集と論点整理が極めて重要になります。
ご自身のみでの対応に不安がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
生前贈与があり、それが法的に特別受益に該当する場合、相続分を調整する必要があるほか、税務上も課税対象となる可能性があります。
これに加えて、「生前贈与が特別受益にあたるのかどうか」という点については法的な評価をめぐって相続人同士の意見が対立しやすくなります。
特別受益に該当するか否かについての見解が分かれると、遺産分割協議自体が進まなくなり、相続手続全体の遅延や、裁判所での調停・審判に発展することも珍しくありません。
「生前贈与をめぐって相続人同士で揉めそう」「特別受益を主張したいが自分たちのケースではできるのか?」など、生前贈与と特別受益に関するお悩みがございましたら、どうぞ早めにご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。