
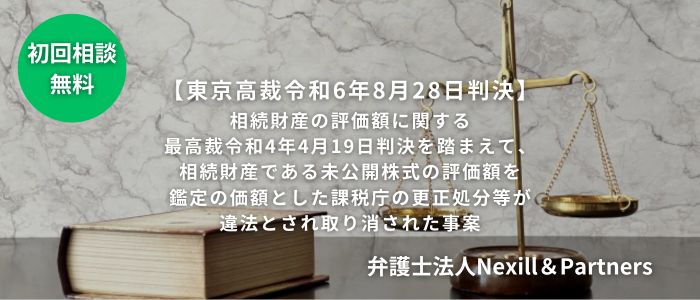
2024年(令和6年)8月28日、東京高等裁判所は、相続財産の評価額に関する最高裁令和4年4月19日判決(民集76巻4号411頁)を踏まえて、相続財産である未公開株式の評価額を、財産評価基本通達の定める方法による評価額でなく鑑定の価額とした課税庁の更正処分等を違法とし、取り消しました。
相続税に関する重要な裁判例の一つとなりましたので、その内容及び意義についてご紹介します。
なお、上記最高裁判例については、以前にご紹介しておりますので、詳細は、そちらをご覧ください。
前提として、相続税の評価に関する規定である相続税法22条と財産評価基本通達を再度みておきます。
前提1.相続税法22条
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
前提2.財産評価基本通達
1 財産の評価については、次による。
⑴ 評価単位
財産の評価は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
⑵ 時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
⑶ 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
それでは、2024年(令和6年)8月28日の裁判例について見ていきます。
1.事案の概要
- ○A(被相続人)は、甲社(調剤薬局業)を経営していました。
甲社の株式は未公開、譲渡制限付きとなっており、発行済み株式総数は6万株でした。
そして、Aが21,400株、B(Aの妻)が13,000株、X1(Aの子)及びX2(Aの子)がそれぞれ3,600株、X1の配偶者200株、X1の子600株、取締役らが合計17,600株を保有していました。 - ○平成26年1月16日、Aは、乙社(医薬品卸業)との間で、甲社株式を乙社に売却して資本提携する前提で協議を進めるに当たり、秘密保持契約を締結しました。
- ○同年5月29日、Aは、乙社との間で、甲社株式の譲渡に向けた協議を行うことについて、基本合意を締結しました。
<基本合意内容>
譲渡価格を63億0,408万円(1株当たり105,068円、譲渡予定価格)とする。
ただし、譲渡予定価格は、A及び乙社を法的に拘束するものではない。Aは、甲社の株式の全部を取りまとめ又は買い集めた上で、乙社へ譲渡する。
- ○甲社の買収監査(デューデリジェンス)が行われました。
- ○同年6月11日、Aが死亡しました。
****
- ○同月18日、甲社取締役会において、Bが代表取締役となり、乙社との間で甲社株式の譲渡の話を進めることにしました。
- ○同年7月8日、遺産分割協議により、Aの甲社保有株214,000株について、Bが10,700株、X1及びX2がそれぞれ5,350株を相続することになりました。
- ○同日、甲社取締役会において、B以外の全株主が、所有する甲社株式を、同月14日を譲渡予定日としてBに譲渡すること、この譲渡が実行されることを前提に、Bが、甲社株式6万株を、同日、乙社に譲渡することが承認されました。
- ○X1、X2は、Bとの間で、それぞれ、所有する甲社株式各8,950株を、9億4,035万8,600円(1株当たり105,068円)で譲渡する契約を締結し、他の株主も、Bとの間で、それぞれ、所有する甲社株式全部を譲渡することにしました。
- ○同月8日、Bが、乙社との間で、同月14日を譲渡予定日として、乙社に対し、甲社株式6万株を、63億0,408万円(1株当たり105,068円)で譲渡する契約を締結しました。
- ○同月14日、乙社が代金決済をし、Bは、乙社へ甲社株6万株を譲渡しました。
****
- ○平成27年2月27日、A相続人らは、S税務署に対し、相続した甲社株式について、財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)180により、その価額を1億7,518万0,400円(21,400株×1株8,186円)と評価し、相続税を申告しました。
- ○これに対し、S国税局長は、平成30年8月7日、A相続人らに対し、KPMG-FASが作成した株式価値算定報告書の平均値17億2,000万円(1株80,373円)を根拠に、評価通達6に基づき、相続した甲社株式の価額について、1株80,373円とする更正処分等をしました。
- ○X1、X2は、再調査請求、審査請求を経て、令和3年1月26日、Y(国)を相手に、本件更正処分等の取消しを求めて提訴しました。
2.第1審(東京地裁令和6年1月18日判決)
⑴ 本件相続開始日における本件相続株式の時価について
㋐ 最高裁令和4年4月19日判決(以下「最高裁令和4年判決」といいます。)の判断枠組み
(省略)※従前報告ご参照
㋑ 当てはめ
最高裁令和4年判決は、実質的には、特段の事情がある場合は評価通達6を適用することを肯定しているものと解されるが、当該特段の事情としてどのようなものが挙げられるかについて一般論として明示はしておらず、被相続人側の租税回避目的による租税回避行為がない場合について直接判示したものとは解されない。
もっとも、最高裁令和4年判決が租税回避行為をしなかった他の納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題にしていることがうかがわれる。
例えば、①被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っており、かつ、売却手続を完了することができたにもかかわらず、相続税の負担を回避する目的をもって、他に合理的理由もなく、殊更売却手続を相続開始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定しておいたりしたなどの場合②最高裁令和4年判決の事例のように、納税者側が、それがなかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていたという程度の事情が特段の事情として必要なものと解される。
㋒ 本件算定報告額による本件相続株式の評価の適否
本件では甲社株式の売却手続が進行中に本件被相続人が死亡しているところ、その手続が遅れたとか、本来は本件被相続人の生前に売却手続を完了することができたといった事情は認められない。
よって、本件において特段の事情はないものというほかはないから、本件相続株式の価額については評価通達の評価額によって評価すべきであり、評価通達6を適用して本件算定報告額を用いて本件相続株式を評価した本件各更正処分等は、最高裁令和4年判決の示した判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違反である。
⑵ 本件各更正処分等の適法性について
本件各更正処分における課税価額は、(中略)本件相続株式の価額を増額した部分は採用できず、(中略)本件各更正処分のうち申告時の課税価格及び納税すべき金額を超える部分は違法である。(中略)原告らに過少申告加算税は発生せず、原告らに対して行った本件各賦課決定処分も全部違法である。

3.控訴審(東京高裁令和6年8月28日判決)
⑴ 評価通達の保有価額と相続開始日における交換価値との間のかい離について
控訴人は、本件において評価通達6を適用すべき根拠として、本件相続株式につき、本件通達評価額と本件相続開始日における交換価値との間に著しいかい離があり、被控訴人らがそのことを十分に認識することは可能であった旨主張する。
しかし、取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得ないものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。
とりわけ、M&Aが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らないというべきである。
このことは、結果的に、専門的評価により交換価値と評価通達180に定める類似業種比準価額とのかい離の程度が著しいと判定された場合においても変わらないのであって、本件相続株式について、譲渡予定価格(10万5,068円)と本件算定報告額(8万0,373円)が比較的近く、これらが本件通達評価額(8,186円)と大きくかい離しているからといって、更正処分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとして、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存在していたということにはならない。
そして、評価通達6の適用に当たり、上記かい離の有無を公平に判断するためには、他の相続案件も含め、取引相場のない株式その他市場性のない相続財産の全てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的な理由がないのに、特定の相続財産のみについて専門的評価を行い、これを基にして課税処分を行うことは、平等原則に反するものというべきである。
⑵ 最高裁昭和61年12月5日判決との関係について
控訴人は、取引相場のない株式について、売買契約が成立し、その所有権が買主に移転する前に、当該株式の所有者である売主が死亡した場合、売主の相続財産は売買代金債権になり、その価額は原則として売買相金額で評価される(最高裁昭和61年12月5日判決)とした上で、相続開始時に売買契約成立に至っていなかったとしても、近い将来売買契約が成立し、売買代金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値が現実的に実現する蓋然性が高いものとして、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が一つの基準になり得るところであるとも主張する。
しかし、上記最高裁判決は、農地の売買契約が成立し、代金の相当部分の履行があったという場合において、農地法所定の要件が具備される前であっても、相続財産は売買残代金債権である旨判断したものであって、本件のように、売買契約が未だ成立していない場合とは明らかに状況を異にするというべきである。(中略)
したがって、控訴人の主張するような、近い将来における売買契約の成立及び売買代金債権への転化の蓋然性の程度を基準にすることは適切でない。
なお、仮に、上記蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したとしても、本件相続開始日において、被控訴人らと乙社との間で本件相続株式の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金債権に転化する蓋然性が高かったと認めることはできない。
すなわち、本件基本合意15条には、①同合意の目的が、合意時点における双方の共通の理解を確認するものであること、②甲社株式の譲渡に関する一部規定を除き、双方を法的に拘束するものではないことが定められていることが認められ、譲渡予定価格に法的な拘束力があることは明確に否定されているものであるし、本件基本合意の後に本件買収監査が行われ、これによる財務調査報告書が乙社に提出されたのは本件被相続人の死亡後である平成26年6月20日であり、さらに、同月25日には、乙社が甲社を今後運営するに当たっての法律上の問題点の有無についての調査結果が弁護士事務所から提出されているのであるから、乙社においても、本件被相続人が死亡した時点においては、甲社株式を譲渡予定価格により取得する確定的意思を有していたとは直ちに認め難い。
⑶ 最高裁令和4年判決のいう事情について
最高裁令和4年判決は、評価通達6の適用の有無に当たり、被相続人が、相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮しているところ、本件被相続人及び被控訴人らによるこれに類する行為があったとは認め難い。
すなわち、甲社株式は、一貫して定款による譲渡制限のある株式であったのであり、また、甲社株式の評価額を下げるような行為がされたことはうかがわれない。
そして、本件基本合意は、本件被相続人の生存中に売買契約が成立した場合、代金債権に転化し、又は代金が支払わることによって、相続税の負担を増大させる可能性を有するものであり、相続税の負担を減じ、又は免れさせるという効果は存しない。
本件被相続人又は被控訴人らが、相続税の負担を減じ、又は免れさせる行為をしたと認めることができない以上、本件被相続人又は被控訴人らの行為に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はない。
⑷ 売却価格を基準にすべきとの主張について
控訴人は、本件売却価格が本件相続株式の客観的交換価値を反映したものであるとも主張するが、そのようなことは、相続開始時における交換価値について専門家による判定を行わない限り認定し得ないものであることは、前記説示のとおりであり、評価通達6を適用すべき特段の事情に該当するとはいえない。
⑸ 最高裁令和4年判決の判示事項について
当審における控訴人の主張のうち、評価通達6の適用に当たり、租税回避行為があることは要件とならないとする点については、当裁判所はそのような要件が存するものと説示しているものではないから、同主張に対する判断の必要はない。
4.東京高裁判例の意義
本件は、最高裁令和4年判決後の裁判所の判断として、第1審段階から注目されていた事案でした。
結論として、第1審も控訴審も、本件の場合に評価通達6の適用をすることはできないとの判断がなされました。
そして、注目すべき点は、東京高裁判例が、「当審における控訴人の主張のうち、評価通達6の適用に当たり、租税回避行為があることは要件とならないとする点については、当裁判所はそのような要件が存するものと説示しているものではない」と判示した点です。
最高裁令和4年判決については、様々な評釈がなされており、租税回避行為がある場合に評価通達6の適用を認めたものとの評釈もありました。
しかし、本件の東京高裁判決は、租税回避行為がある場合に評価通達6の適用を認めるものではないと明示しました。
むしろ、本件の東京高裁判決は、「最高裁令和4年判決は、評価通達6の適用の有無に当たり、被相続人が、相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮している」とした上で、本件被相続人及び被控訴人らによるこれに類する行為があったとは認め難いと判示しました。
本件については、国が上告を断念したため、確定したので、最高裁の判断はありません。
しかし、最高裁令和4年判決の解釈について、東京高裁の判断が示された意義は大きいと思われます。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。


