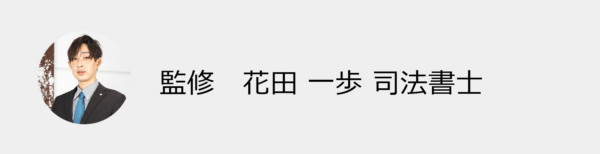
テレビのCMなどで「相続登記が義務化されました。」というお知らせを見たこと、聞いたことがありませんか?
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
1.相続登記義務化の理由
これは、所有者が亡くなったのに相続登記がされていないことにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じていることなどが社会問題となっているためです。
国土交通省の調査によると、所有者不明の土地は日本国土の24%を超えると推定されています。
所有者が亡くなっているのに、相続登記がされないまま、相続人も亡くなり、またその相続人まで亡くなった場合のように、相続人への名義変更をしない間に何度も相続が発生すると、相続人の特定に時間や費用がかかってしまいます。そうなると、顔も名前も知らない人同士が同じ土地の相続人になっているということも十分に起こり得ます。
このような問題を予防するために、相続登記が義務化されたのです。
2.改正後の相続登記の概要
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
この正当な理由とは、相続人が極めて多数であり、戸籍謄本等の資料収集や、ほかの相続人の把握に多くの時間を要する場合などを指します。

3.過去の相続分の登記はどうなるの?
令和6年4月1日(義務化の施行日)よりも前に発生していた相続についても遡及して適応されます。つまり、過去に発生した相続についても相続登記未了の不動産も登録義務化の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続が発生している場合は猶予期間3年となりますが、あくまでも義務化の対象となっていますので、相続登記が必要な方は、お早めに登記の申請を行いましょう。この場合でも、正当な理由なく期限内に相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となってしまいます。
4.過去の相続を放置したままの不動産も義務化対象になる?
相続登記の義務化と聞くと、多くの方は「新たに発生する相続だけが対象なのでは?」と思いがちです。しかし、前述したとおり、実際には過去の相続であっても登記が行われていない不動産については、原則として今回の義務化の対象となります。
もともと相続登記は任意で行うものとされてきましたが、全国に所有者不明土地が増え続けたことを背景に、法務省は「登記の義務化」を打ち出しました。
古い不動産ほど名義人が何代も前の人になっていて、行政としても所有者を把握できないため公共事業や防災上の問題が深刻化しており、今回の制度変更で一掃を目指す狙いがあるといえるでしょう。
どこまで過去の相続に戻って手続きを行う必要があるのか
問題は、ひとつの不動産に複数の相続(祖父→父→自分 といった連鎖)が蓄積してしまっている場合です。たとえば、30年前に祖父が亡くなったが当時は名義変更をしないまま父が実質的に使用し、その父もまた数年前に亡くなっているような状況では、各世代の相続を正しく処理し、最終的に現在の相続人へ名義を移すという作業を段階的に行う必要があります。具体的には、まず祖父の相続人を確定させ、当時の遺産分割協議または法定相続に基づいて父の名義に変更し、その後に父の相続を登記するというような手順での手続となります。さらに相続人が何人も存在し、すでに亡くなっている親族や行方不明の相続人が含まれるケースでは、家庭裁判所への不在者財産管理人の申立や、場合によっては調停が必要となるかもしれません。
複数の相続が発生していると何が大変になるのか?
古い相続をさかのぼって手続をする際、ネックになるのが相続人の確定とすべての相続人の同意取り付けです。相続の回数が増えれば増えるほど、相続人も増えますので、戸籍の収集と相続人の確定にも手間と時間がかかります。また、相続人が確定したうえで、相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成し、不動産の登記を進めなければならない点もハードルです。とくに共有持分となっている不動産では、「誰がどの割合を相続するか」という点を話し合う必要があり、途中で紛争に発展するケースも少なくありません。
当事者間での遺産分割協議が困難な場合は、話し合いをまとめるために家庭裁判所での調停を検討することが多いです。調停委員の仲介で合意がまとまれば登記に進めますが、合意が難しい場合は審判に移行してでも遺産分割をまとめる必要があります。名義変更ができない期間が長くなればなるほど過料がかかるリスクも上がるため、早めに動き出すのが得策です。
放置のリスクを最小化するためには
このように、過去の相続を何世代も放置してきた不動産を義務化のタイミングで処理するには、非常に手間がかかります。しかし、先送りすればするほど、相続人がさらに増え、遺産分割協議がより複雑に、より大変になります。
- 弁護士や司法書士に依頼して、戸籍収集や遺産分割、登記手続をサポートしてもらう
- 家庭裁判所の調停や不在者財産管理人選任など、必要手続きを迅速に把握する
- 残された親族には、「必ず相続登記をすることが法律で義務化された」旨を共有し、協力体制を作る
登記義務の放置のリスクを最小限にするためにも、必要であれば専門家に依頼をしながら、速やかに手続きを進めることが必要です。
登記が完了すれば、不動産の売却や活用、さらには次に相続が発生した時の手続もスムーズに行えるようになりますので、過去の相続がそのままになっている場合は一度専門家へご相談されることをお勧めします。
5.過去相続の登記でよくあるパターン別対処法
相続登記の義務化を機に、長年放置していた不動産の名義変更を進めようとする方の中には、「うちのケースはどうなるのだろう?」と感じている方も多いでしょう。実際、過去の相続が絡んでいると、単純に「相続人全員で協議して登記する」だけでは解決できない問題が山積みになるケースがあります。ここでは、代表的な4つのパターンを挙げ、それぞれの対処法を解説します。
パターンA:過去に遺言書はあったが放置していた
現状
- 「祖父(または親)が遺言書を残していた」とは聞いていたが、死後に正式な名義変更をしないまま数十年が経過
- 遺言書があっても実務的に反映されていないため、法務局の登記簿上は依然として被相続人名義になっている
問題点
- 遺言書に基づく遺言執行が行われなかった結果、死後の財産管理や承継が曖昧になっており、一部の相続人が実質利用しているだけの状態
- 遺言書の内容を今でも有効に使えるのか、書式に不備はないかを再確認しなければならない
- 遺言書が公正証書なら、書式不備のリスクは少ないので、そのまま遺言執行者(必要なら新たに選任)を立てて登記申請できる
- 自筆証書遺言の場合、死後に検認が必要だったが、まだ手続していないなら家庭裁判所の検認を経てから登記へ進む
- 遺言書自体が見つからない・形式不備があって無効になってしまった場合は、改めて相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある
- 誰かが亡くなって相続発生はしているが、「今さら分割協議をするまでもない」と長年放置
- その結果、相続人全員が法定相続分で不動産を共有している状態が継続し、登記は被相続人の名義のまま
- 今回の義務化によって「登記しないといけない」となっても、そもそも誰がどれだけ相続するのか話し合いをしていないので、登記の名義人を決められない
- 相続人が増えている可能性もあり、簡単に意見がまとまらないまま時間だけが経過するリスク
- まずは相続人を確定させ、遺産分割協議を行い、書面(遺産分割協議書)を作成する
- 全員の署名押印が揃えば、その協議書を基に登記申請が可能
- 連絡が取れない相続人がいるなら、「不在者財産管理人」の選任、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」に進むことも検討
- 親族の誰かが実質的に土地や建物を使っているが、正式には名義変更していないし、他の相続人の所在や同意が得られていない
- 義務化で登記しないと過料が課されるかもしれないが、行方不明の相続人がいるため協議が進まない
- 法律上、全相続人が協議に参加しないと遺産分割協議は成立しない。行方不明者がいる場合は話し合いができず、事実上登記申請もできない
- 連絡がつかない相続人がいるため、紛争が起きるリスクも高い
- 「家庭裁判所に申し立てて、『不在者財産管理人』を選任してもらう」手段を検討。これにより、行方不明の相続人を代理する管理人が協議に参加できる
- 協議書作成後、司法書士や弁護士のサポートで登記へ。市町村長申立を利用する場合もある
- 行方不明の相続人について、失踪宣告できるようなケースであればその手続も視野に入れる。
- すでに父母の世代で共有名義だった土地を、そのまま放置していた結果、父母の死亡で子ども達がまた共有を承継し、持分が細分化
- 何代にもわたって共有が連鎖し、最終的に何十人もの相続人が存在し、実質的に活用できない不動産が残っている
- 全員で共有状態を解消するか、誰かがまとめて取得して売却するかなど、意見をまとめるのが困難
- 義務化によって少なくとも名義を現相続人に移す必要があるが、協議が複雑すぎて先に進まない
- 一度「遺産分割調停」や「共有物分割請求」という法的手段を利用し、公平な形で処理するのが早道。
- 誰が不動産を取得し、代償金を払うのか、売却して代金を分けるのかなどの選択肢を整理。
- 法的手段の場合は弁護士に依頼して対応を進める方がベター。遺産分割協議がまとまった後に、登記申請を進める
対処法
パターンB:遺産分割協議すらしていない(法定相続状態のまま)
現状
問題点
対処法
パターンC:一部の相続人だけが使用しており、他の相続人がどこにいるか不明
現状
問題点
対処法
パターンD: 共有名義がさらに増え続けて複雑化
現状
問題点
対処法
このように、過去の相続が絡んだ登記は、単純なケースがほとんどありません。今回紹介した事例は一例に過ぎず、実際には問題点が複合することもあります。たとえば、「古い遺言書があったうえに、一部の相続人が行方不明で共有名義が何重にもなっている」など、複数の問題が同時に発生しているケースも珍しくありません。
できるだけ早く専門家のサポートを受けながら適切に対応を進めることが望ましいでしょう。
当事務所では、弁護士・司法書士によるワンストップでの相続サポートを行っており、遺産分割協議から調停や不在者財産管理人選任などの法的対応、その後の相続登記までを一貫して対応が可能です。
古い名義のまま数代にわたって連鎖した相続手続についても相続に特化した弁護士を中心にスムーズな解決方法をご提案いたします。
まずは初回無料相談をご利用ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。


