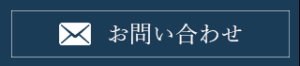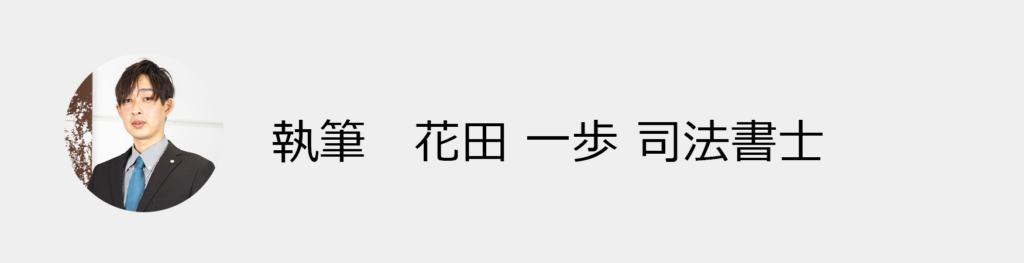
親や親族が亡くなり、自宅などの不動産を相続することになったとき、避けて通れないのが「相続登記」です。不動産の名義変更の手続きですが、「そもそも何をすればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の基本的な流れと注意点を、できるだけ分かりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。この手続きは法務局で行います。
たとえば、親が所有していた家を相続した場合、そのまま住み続けるにしても、将来売却するにしても、名義が自分のものになっていなければ何もできません。名義変更をすることで、初めてその不動産を「自分のもの」として法律上正式に扱うことができるのです。
相続登記の流れ
相続登記にはいくつかのステップがあります。簡単に説明すると以下のような流れになります。
1. 相続人の確定
まず行うのが「相続人を確定させること」です。これは戸籍を集めて確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要になります。
2. 相続する不動産の確認
次に、不動産の情報を確認します。固定資産評価証明書や登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得して、どの不動産が相続の対象なのかを明確にします。
3. 遺産分割協議(必要な場合)
相続人が複数いる場合は、「誰がどの財産を相続するのか」を話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。
4. 必要書類の収集
登記申請にはさまざまな書類が必要です。主なものは以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票や印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
必要書類は状況によって異なる場合がありますので、法務局や専門家に確認するのがおすすめです。
5. 法務局への申請
すべての書類が揃ったら、登記申請書を作成して法務局へ登記申請を行います。
相続登記は義務に
2024年4月から、相続登記は義務化されました。相続が発生したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
今までは「いつまでも名義変更せずに放置」しても罰則がありませんでしたが、これからはそうはいきません。相続登記を後回しにすると、相続人が亡くなるなどしてさらに手続きが複雑になる恐れもあります。早めの対応が安心です。
司法書士に依頼する場合
相続登記は、ご自身で行うことも可能です。ただし、戸籍の収集や書類作成、法務局への提出など、慣れていない方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。
もし手続きに不安がある場合や、書類の準備に時間をかけられないという場合には、専門家に依頼することも一つの方法です。確実かつスムーズに進めたい方には適しています。
まとめ
相続で不動産を受け継いだら、忘れずに相続登記を行うことが大切です。手続き自体は複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればご自身でも進めることができます。
義務化も始まりましたので、「よく分からないからそのままに…」とせず、できるだけ早めに対応しましょう。将来のトラブルを防ぎ、大切な財産をきちんと引き継ぐために、正しい登記手続きを行ってください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。