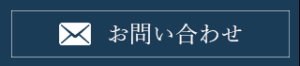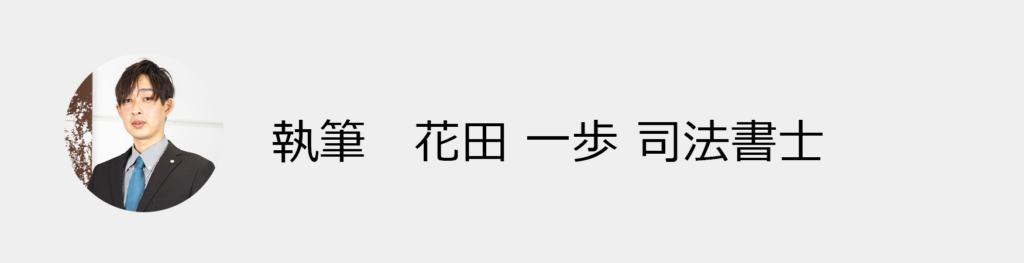
不動産を購入したり、相続で不動産を取得したとき、「共有名義」という言葉を耳にすることがあります。
そして、そこで重要になってくるのが「持分(もちぶん)」です。
今回は、不動産登記に関わる「持分」について、初めての方にもわかりやすくポイントを解説します。
「持分」とは?簡単に言うと…
「持分」とは、不動産を複数人で所有する場合に、それぞれの人がどのくらいの割合でその不動産を所有しているかを示すものです。
たとえば、夫婦で住宅を購入した場合、購入金額を折半していれば、通常「2分の1ずつ」の持分となります。これを登記簿に記載することで、法律上も正式に共有状態となります。
なぜ「持分」が大切なのか?
持分は、次のような場面で非常に重要な意味を持ちます。
1. 不動産の売却や活用に影響
共有名義の不動産を売却するには、全員の協力が必要です。仮に持分を持つ一人が反対すれば、不動産の所有権全部の売却はできません。
また、持分の割合によって、賃料収入の分配や固定資産税の負担割合などにも影響があるでしょう。
2. 相続のときに揉めやすい
相続によって共有になった不動産は、親族同士で持分を共有することになりますが、誰がどれだけの権利を持つのか曖昧なままにしておくと、将来的にトラブルの元になり得るため、注意が必要です。
どんなときに「共有名義」にするの?
以下のような場面で、共有名義の登記がされることがあります。
- 夫婦でマイホームを購入したとき
- 兄弟姉妹で不動産を相続したとき
- 親子で共同購入したとき
いずれの場合も、実際の出資割合や相続分に基づき、将来起こり得るリスクも考慮して、適正な持分を決め、それを登記に反映させることが大切です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回は不動産登記に関わる「持分」について、初めての方にもわかりやすくポイントを解説しました。
共有状態のまま放置していると、時間が経つにつれて相続によって共有者が増え、処分や活用が難しくなるケースも考えられます。
こうした事態を防ぐためにも、登記する段階で、出資割合や契約内容、将来のことを見据えたうえで、最適な登記方法を検討することが重要です。
「持分」は、不動産の所有権に関わるとても大切な要素です。
トラブルになりやすい「共有名義」こそ、最初の登記でしっかりと対応しておくことが安心につながります。
不動産の共有や持分に関して不安がある方、登記のやり方がわからないという方は、ぜひ専門家にご相談ください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。